| 執筆者 |
中室 牧子 (慶應義塾大学) 松岡 亮二 (統計数理研究所) 乾 友彦 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | サービス産業に対する経済分析:生産性・経済厚生・政策評価 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
産業・企業生産性向上プログラム (第三期:2011~2015年度)
「サービス産業に対する経済分析:生産性・経済厚生・政策評価」プロジェクト
本研究は、小学校低学年の子どもがテレビやゲームをする時間が増えると、その分勉強する時間が減るのか、という疑問に答えることを目的としている。逆に言えば、もしテレビやゲームを禁止すれば、子どもの勉強時間は増えるのだろうか。本研究では、21世紀出生児縦断調査(厚生労働省)という2001年に出生した子どもを長期にわたって追跡した大規模データを用いて、小学校低学年の子どもらの家庭での勉強時間がどういう要因によって決定されているのかについて検証を行った。
本研究の分析結果から得られた結論は、テレビやゲームは勉強時間を減らす効果を持つが、それは殆ど無視できるほどに小さいものであり、テレビやゲームの時間を制限したからといって、勉強時間を増やす効果を持たないというものである。具体的には、1時間の追加的なTV視聴やゲーム使用は、男子でわずかに1.86分、女子で2.70分の勉強時間を減らすにすぎない。
また、子どもや親に関する観察不可能な要因(子ども自身の能力や親の教育熱心さなど)を制御すると、兄弟や祖父母との同居などの家族構成や親の働き方は、子どもの勉強時間に影響しない。すなわち、母親が仕事をやめても、子どもの勉強ができるようになるわけではない。しかし、親が勉強について子どもとどのような関わりを持っているかということは極めて重要である。具体的には、「勉強するように言う」というのは効果が低くむしろ逆効果になる場合もあるが、勉強するのを横についてみていたり、勉強する時間を決めて守らせることの効果は高い。また母親のほうが父親よりも子どもの勉強に対して関わっているが、父親の関わりが子どもの学習時間を増加させる効果は高く、同性の子ども(息子)には特に効果が高い。
こうしたことから、本研究から導き出される政策的なインプリケーションは次のようなものであると考えられる。第1に、子どもの学習時間の増加のためには、親の関わり方が重要である。具体的には、勉強するのを横についてみていたり、勉強する時間を決めて守らせることが必要であるが、これは必ずしも血のつながった「親」である必要はない。そこで現在も全国約1万カ所で実施されている「放課後子ども教室」のような地域のボランティアが宿題の手助けなどを行う事業は、子どもの勉強に対する親の関わりを一部肩代わりしてくれ、子どもの勉強時間の増加につながる可能性が高い。また、勉強時間が親の関与の影響を強く受けるとすると、学校での学習時間を減らすと、家庭格差は学力格差となり、教育は格差の世代間継承の装置となってしまう。こうしたことはほかの研究でも指摘されており(たとえばKawaguchi 2013など)学校週5日制は子どもの学力の格差を拡大する可能性が高いため、同制度については見直しも含めて議論されるべきである。
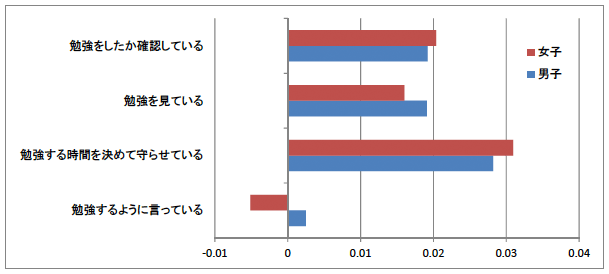
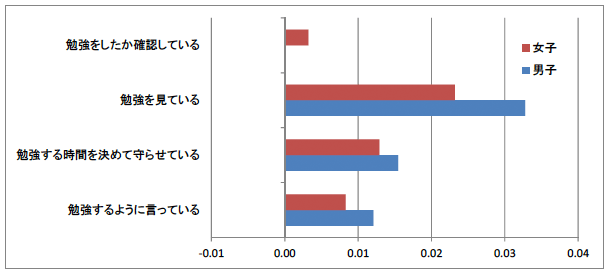
参考文献
- Kawaguchi, D. 2013. Fewer School Days, More Inequality. Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 271

