| 執筆者 |
橋本 英樹 (東京大学) 市村 英彦 (ファカルティフェロー) 清水谷 諭 (コンサルティングフェロー) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 社会保障問題の包括的解決をめざして:高齢化の新しい経済学 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
社会保障・税財政プログラム (第三期:2011~2015年度)
「社会保障問題の包括的解決をめざして:高齢化の新しい経済学」プロジェクト
1. リスク態度の「見える化」
標準的な「ミクロ経済学」の教科書には必ず書かれているが、経済理論では、リスク態度は時間選好とともに意思決定において最も重要なパラメータと位置付けられている。しかし個人がどの程度リスク回避的(あるいは愛好的)かを示すリスク態度自体は直接観察できない。このため、特に90年代から、仮想的な質問を通じてリスク態度を「見える化」し、リスク態度がどのような属性(所得や教育水準など)によって影響されるのか、どのような行動(喫煙、予防行動など)と結びついているかを検証する論文が多く発表されてきた。
しかしこれらの論文の多くは、リスク態度が時間によって変化しないという「仮定」をもとに実証を進めている。しかしリスク態度は生来のもので、一生の間変化しないのかどうかは、そもそも十分に検証されていない。最近では脳科学の発達によって、リスク態度が脳の特定の部位と結びついており、また学習によっても変化しうることがわかってきている。
2. JSTARのリスク態度の尺度
リスク態度は貯蓄・消費行動、労働供給、健康投資、精神的健康状態などにも直接結びつくため、中高年期において変化がみられるとすれば、個人の選択の全体が若年期と大きく変わりうることになる。
JSTARはリスク態度の経年的変化をとらえうる日本で数少ないデータだが、リスク態度自体を「見える化」するための工夫も施している。詳細は本文に譲るが、これまでHRSなどで採用されてきた方法(仮想質問)では、回答が矛盾しないように効用関数に非常に強い仮定を置いている。JSTARではより緩い仮定で、下のXXを100%から0%まで10%刻みで変化させて、AとBのどちらを選択するか、回答者に2択で答えてもらう。
A. XX%の確率で所得が50%増加、(100-XX%)の確率で所得が5%増加
B. 100%の確率で10%増加
次に、
A. XX%の確率で所得が50%増加、(100-XX%)の確率で所得が5%増加
B. 100%の確率で20%増加
の2択で答えてもらう。このことによって、2つの回答が単調性と凹性を満たしているかどうかもチェックできる。
3. 実証結果からわかること
本論文の実証結果は多岐にわたるが、以下、主な点を要約する。
・単調性と局所的な凹性を満たさない「不合理な回答」が、全体の1割から2割みられる(表)。
・「不合理な回答」は年齢、精神的健康(うつ)、教育水準あるいは地域(都市)によって、影響を受ける。
・「合理的な回答」に限ると、年齢が高いほど、あるいは教育水準が低いほどリスク回避的になるものの、性別や機能障害とリスク態度には有意な関係は見られない。また引退している場合にはリスク回避的となる一方、所得や資産が多いほどリスク愛好的になる。
・予想に反するが、喫煙や健康診断の受診とリスク態度との間には有意な関係は見られなかった。
・同じ個人を2時点の間で比較すると、年齢が上がるほどリスク回避的になるものの、健康状態(特定の疾病の罹患の有無など)有無はリスク態度に対して、影響を及ぼさない。
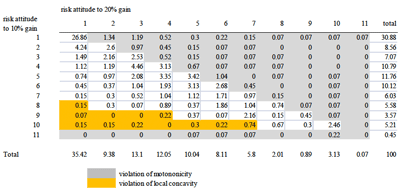
[ 図を拡大 ]
4. 今後の研究
本論文は、リスク態度は加齢によって回避的になるものの、大きな病気をしたといった健康状態はリスク態度に意外に影響を与えないことがわかった。ここで扱ったのは、加齢と健康が及ぶ影響だが、人生の中には、他にも大きなショックがあって、それがリスク態度を大きく変える可能性も否定できない。たとえば、JSTARでは、2009年(第2回)と2011年(第3回)を比較することで、東日本大震災という大きなショックが、仙台市あるいは仙台市以外の人々のリスク態度にどのような影響を与えたかを定量的に解析することができる。そうした実証研究の積み重ねによって、リスク態度といった経済理論の根幹となるパラメータの性質がよりよく理解されることが可能となる。

