| 執筆者 |
大橋 和彦 (一橋大学) 沖本 竜義 (一橋大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 輸出と日本経済:2000年代の経験をどう理解するか? |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
国際マクロプログラム (第三期:2011~2015年度)
「輸出と日本経済:2000年代の経験をどう理解するか?」プロジェクト
問題の背景
商品と株式や債券などの伝統的資産のリターンの相関は、今世紀に至るまで長期にわたり、低いものであったことが複数の先行研究によって示されている。また、異なる商品間の価格リターンの相関も、やはり低いものであることを指摘する先行研究も存在する。このようなリターンの相関の低さはポートフォリオ理論における分散投資効果の高さを意味するため、今世紀に入り、商品インデックス投資や商品デリバティブの普及に伴って、年金基金やヘッジファンド等による商品投資の急激な増大を生み出した。いわゆる、「商品の金融商品化(financialization of commodities)」が進んだのである。
商品の金融商品化が進む中、原油価格は前例のないレベルまで上昇し、その後リーマンショックを受けて急落し、再び急騰するという乱高下を経験した。その結果、価格変動がマクロ実物経済に与える影響も懸念され、その背景に新興国の経済発展に伴う需要の影響もあるものの、商品の金融商品化は、金融市場関係者のみならず一般事業者や政策立案者等多くの人々に印象付けられることとなった。それを受けて、商品の金融商品化が、金融市場の共変動に与えた影響を分析することも重要な研究テーマとなっている。例えば、商品の金融商品化以降、商品と株式のリターンの相関が上昇し、また原油とそれ以外の商品のリターンの相関も上昇し、これらが商品の金融商品化による可能性が強いとする結果などが報告されている。
本研究の主な結果
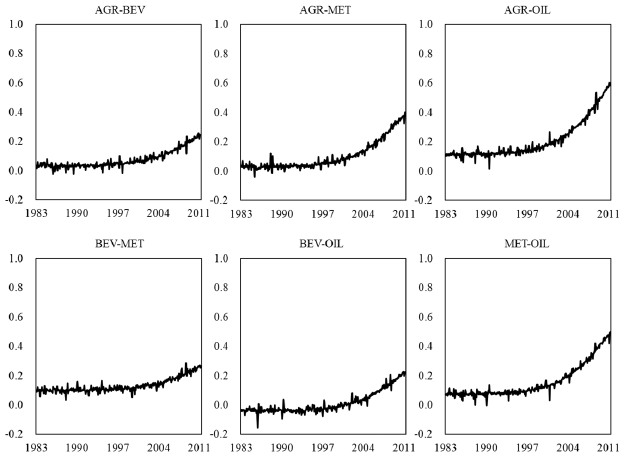
政策的インプリケーション
商品の金融商品化は、ある意味では、これまで分断されていた商品市場がより大きな株式や債券市場と統合され、より効率的なリスク配分が達成されていく動きと肯定的に捉えることもできる。その一方で、生み出された超過共変動の上昇は、異なる資産の売買が同時になされ、共通のマクロ経済要因とは無関係に価格が同方向に動くリスクが高まったことを意味する。これが政策立案者に対してもつインプリケーションも大きなものであり、たとえば、ポートフォリオの分散効果の低下により、市場価格の下落が金融システム全体にもたらす影響が増大していることが危惧されると共に、リスク管理の困難化を生み出している可能性も懸念される。また、この回路を通じた金融市場の実物市場への影響の増大も考えられ、今後こうしたリスクを注意深く見ていく必要があるであろう。

