| 執筆者 |
清水谷 諭 (コンサルティングフェロー) 小塩 隆士 (一橋大学経済研究所) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 社会保障問題の包括的解決をめざして:高齢化の新しい経済学 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
社会保障・税財政プログラム (第三期:2011~2015年度)
「社会保障問題の包括的解決をめざして:高齢化の新しい経済学」プロジェクト
1. 税制・社会保障制度と労働供給
税制や社会保障制度が労働供給に及ぼす影響は、経済学の中で比較的早くから注目され、理論化が進み、実証分析が多く蓄積されてきている分野である。これは現実の政策課題への処方箋を得る上でも、非常にrelevantな分野であり、現代の日本もその例外ではない。
日本の人口高齢化のスピードは諸外国に比べても早く、すでに2006年から人口減少が始まっている。人口減少は将来の労働力人口の減少を招き、経済成長に悪影響を及ぼしかねないという考えから、女性や高齢者の労働供給促進が喫緊の政策課題となっている。そのため、現行の税制や社会保障制度が労働意欲のある人たちの労働供給を阻害している場合、それがどの程度の大きさなのか、どのようなタイプの人々が労働供給を抑えているのかを実証的に明らかにすることは、制度改革の方向性を議論する上で欠かすことのできない前提となる。
具体的には、女性の労働供給の関係で議論されるのが配偶者控除制度(「103万円の壁」)あるいは第3号被保険者制度(「130万円の壁」)であり、高齢者の労働供給の関係で議論されるのが在職老齢年金制度である。
2. 60歳代後半の在職老齢年金制度の変遷
在職老齢年金制度とは、厚生年金の受給資格があっても、労働所得(あるいは労働所得と本来の年金受給額の合計)が一定程度を超える場合には、年金が減額される制度で、日本では1965年に導入された。
本稿で注目したのは、このうち65-69歳を対象とした在職老齢年金制度である。理由は主に2つである。1つは、定年延長が進み、「65歳定年制」を導入する企業も増加する中で、今後は60歳代後半の労働力率をどう引き上げていくかという点が焦点になってくると考えられるからである。もう1つは、60歳代前半に比べて、60歳代後半の在職老齢年金制度の方が分析上扱いやすいからである。具体的には、60歳代後半の在職老齢年金制度は1985年にいったん廃止された。それまでは労働所得が15.6万円を超えた部分について、年金額の20%が支給停止されていた。ところが2002年になって、財政上の理由で、形を変えて復活した。つまり、労働所得と2階部分の年金の合計が37万円を超えた部分について、年金額の50%が支給停止されるようになった。
3. 推定方法と結果
本稿は、60歳代後半の在職老齢年金制度の「廃止」(1985年)と「復活」(2002年)の効果を検証するために、既存のデータセットである厚生労働省「高年齢者就業実態調査」のマイクロデータを用いて、65-69歳の厚生年金受給資格者の賃金(あるいは賃金+2階部分の年金額)の分布を比較した。具体的には「廃止」のケースでは1983年調査と1988年調査を、「復活」のケースでは2000年調査と2004年調査を用いた。ただし、調査年の間隔が長いために、政策効果が他の要素と紛れてしまう可能性が高いばかりか、企業や労働者の属性自体が大きく変化してしまう可能性がある。そこでDiNardo-Fortin-Lemieuxによる分布分解の方法を用いて、観察できる属性が同質であると仮定した場合の仮想分布を推定し、在職老齢年金制度の影響の有無を解析した。
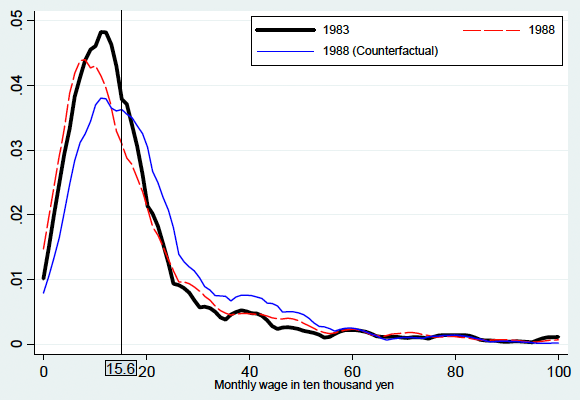
図1は1985年の「廃止」のケース(男性)の結果である。観察できる属性をそろえても、1983年に比べて1988年の分布は右にシフトしており、しかも「閾値」であった15.6万円を超えた部分の分布が膨らんでいる。これは「廃止」が労働供給を促進させた可能性があることを示している。女性の場合は男性に比べるとその影響はかなり小さい。一方、2002年の「復活」のケースでは、観察できる属性をそろえると、2004年の分布は2000年に比べて左に偏っているが、そのピークは閾値よりもかなり離れている。これを在職老齢年金制度が適用されない週30時間未満の労働者とそれ以外で分けると、前者の動きによってほぼ説明ができる。在職老齢年金制度による年金減額を避けるために週労働時間を抑えたケースもあるとみられるが、むしろ短時間労働者自体が増加した影響によるものだろう。このように、日本では在職老齢年金制度の「廃止」は労働供給を刺激したが、「復活」自体は労働供給を抑制したとは必ずしもいえないという結果になった。
4. まとめと留意点
本稿では過去の改革のエピソード前後の「高年齢者就業実態調査」を用いて在職老齢年金制度の影響の把握を試みた。在職老齢年金制度の改革を分析する上では、厚生年金の受給資格の有無の情報が不可欠で、過去の制度改革の効果を解析しようとすれば「高年齢者就業実態調査」は唯一無二のデータといっても差支えない。しかし(1)パネルデータではなく、調査年間隔の長いクロスセクションであるという点で扱いにくい、(2)健康や教育水準、家族構成といった変数に乏しいといった点で、自ずと大きな限界があるといってよい。また近年の実証分析で利用されている個人のPreference(時間選好率、リスク態度)や死亡確率などのデータも得られない。
また政策効果の分析をきちんと行うためには、個人がどのような選択肢に直面しているかを示す情報が不可欠である。その点、健康、経済、家族、社会参加など豊富なデータを集めながら個人を追跡調査するJSTAR(「くらしと健康の調査」)が継続され、その中で大きな改革が行われれば、在職老齢年金制度の定量的分析に飛躍的な質的向上をもたらすことは間違いない。

