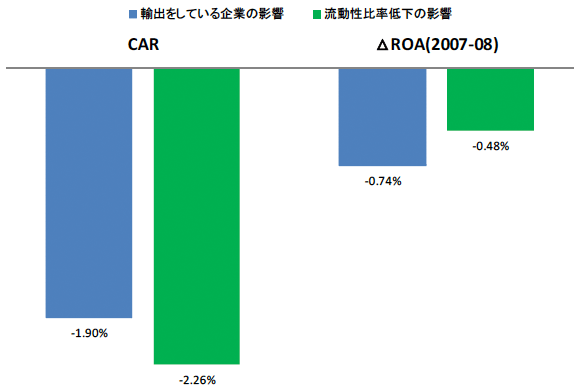このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
人的資本プログラム (第三期:2011~2015年度)
「労働市場制度改革」プロジェクト
問題意識
2007年からのサブプライムローン問題、そして2008年9月にリーマンブラザーズの破綻に端を発した米国発の金融危機は、グローバルな危機となり、その影響は全世界に波及した。日本の金融機関は、サブプライムローン関連からの損失は相対的に小さいものであったものの、日本の株価指数(TOPIX)は、米国、欧州およびアジアの株価指数と同程度下がり、日本の実質GDPは2009年に5.2%下がった。このGDPの下落は、主要国の中では最も大きく、特に、輸出の下落は日本が最も大きいものとなった。
本稿では、この世界金融危機の国際伝播の影響を、日本企業の株価の変化(CAR:累積超過収益率)を用いたイベントスタディと企業業績(ROAと売上)の変化を観察することで、どのような企業が今回の危機の影響を受けやすかったのかに注目し、分析した。
分析結果のポイント
以下では、危機発生国の輸入需要低下による輸出減退効果(所得効果)、危機発生国の為替が減価すれば、当該国の輸入が減退する一方、第三国向けでは当該国の輸出が為替減価で有利になることによる輸出減退効果(価格効果)などをまとめて「貿易リンケージ」と呼ぶ。また、危機の影響を受けた投資家が株式や他の危険資産を投げ売りして流動性を得ようとすることによる効果、金融危機による流動性の枯渇、資本市場の麻痺などをまとめて「流動性チャンネル」と呼ぶ。
本稿では、リーマン破綻(2008/9/16)から不良資産救済プログラム(TARP)が公表される前(10/10)までの期間(18日営業日期間)を分析期間とし、市場リスクを調整し計測した累積超過収益率(cumulative abnormal returns :CAR)と、2007年から2008年あるいは2009年までのROA、売上の変化を被説明変数とした回帰分析を行った。その結果、以下の点が明らかとなった。
CARの推計では、輸出ダミーの係数がマイナス、流動性資産比率がプラスとなった。これは、危機が「貿易リンケージ」、「流動性チャンネル」の双方を通じて、企業株価に影響を与えていることを示している。また以下の図より、そのインパクトは、「貿易リンケージ」より「流動性チャンネル」の方が大きいことがわかる。具体的には輸出をしている企業はそうでない企業と比べ、1.9%CARが低下し、流動性資産比率が平均より1標準偏差低い企業は、1標準偏差高い企業より、2.3%CARが低下している。
企業業績(ROAや売上高)の推計でも係数については、概ねCARと同様の結果が得られた。しかしながら「貿易リンケージ」の方が「流動性チャンネル」よりインパクトが大きく、CARの結果と量的な効果で違いがみられることが、以下の図よりわかる。具体的には、2007年から2008年の分析では、輸出をしている企業はそうでない企業と比べROAが、0.7%低下している。一方、流動性資産比率が平均より1標準偏差低い企業は、1標準偏差高い企業より、0.5%ROAが低下していることが示された。
インプリケーション
世界金融危機は、「貿易リンケージ」と「流動性チャンネル」の双方のチャンネルを通じて、日本企業の株価と業績に大きな影響を与えた。一方で、株価と企業業績とで、双方のチャンネルの影響度に違いがあり、株価は「流動性チャンネル」の、企業業績は「貿易リンケージ」の影響が大きいことが分かった。
危機後の企業業績(ROAや売上高)に注目すると、「流動性チャンネル」を通じた負の効果が小さくなっている点が指摘できた。金融危機後、日本銀行は2008年10月に政策金利の誘導目標を0.5%から0.3%に、2008年12月19日には0.1%に引き下げ、市場への流動性の供給に積極的な姿勢を示した。また、コマーシャルペーパー(CP)の買い切りオペも実施した。これは危機により大企業がCPでの調達が困難になり、銀行借入による資金調達を増やしたため圧迫されていた、中小企業への資金供給をサポートするものであった。こうした一連の金融緩和政策により、流動性が潤沢に供給されたことで、「流動性チャンネル(流動性資産比率)」の企業業績への負の影響が緩和されたとの解釈もでき、本稿の分析結果は当時の金融政策に対して一定の評価を下し得るものとなった。