| 執筆者 |
鎌田 康一郎 (日本銀行) 倉知 善行 (日本銀行) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 経済成長を損なわない財政再建策の検討 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
社会保障・税財政プログラム (第三期:2011~2015年度)
「経済成長を損なわない財政再建策の検討」プロジェクト
国債信用が失われれば、国民生活のさまざまな側面に多大な影響が及ぶ。特に、金融システムが不安定化すると、経済活動一般に及ぼす影響は計り知れない。低成長が続くわが国では、家計や企業が、安全嗜好の高まりから、借入需要を抑制する傾向にある。一方、銀行は、資金の運用難から、積み上がる預金を国債保有量の増加に当てている。こうした中、銀行の国債保有の累増がはらむ金利変動リスクに関心が集まっている。
国債金利の変動は、さまざまな経路を通じて、金融や経済に影響を及ぼす。国債金利の変動が金融システムの安定性に及ぼす影響を考察する際、次の3つの経路に着目することが重要である。(1)国債金利が上昇すると、債券の時価が低下し、銀行は評価損を抱えることとなる。(2)貸出金利や預金金利を変動させ、銀行収益に影響を及ぼす。(3)貸出金利や貸出量の変化を通じて実体経済に影響を及ぼし、それが銀行経営にフィードバックされる(金融と実体経済の負の相乗作用)。
まず、国債金利の上昇によって、債券評価損がどの程度発生するかを試算したところ、全ての年限で国債の金利が1%pt上昇した場合(パラレルシフト)、シミュレーション1年目の債券評価損が約5兆円に上ることがわかった。これはコア業務純益約4兆円(2010年度末)を上回っており、決して小さな数値ではない。しかし、自己資本に及ぼす影響を試算すると、Tier I比率でみて0.6%ptの低下にとどまる(資金利益、貸出金利、金融と実体経済の負の相乗作用の全てを考慮したベース)。銀行全体で見たTier I比率が11%を超えていることを考えると、これは銀行経営の屋台骨を揺るがすほどの影響ではない。
なお、国債金利上昇の実体経済への影響という点では、債券評価損のみの影響は大きくなく、貸出金利が上昇してはじめて、実体経済の抑制要因となる。これに関連して、わが国貸出市場に関する次のような特徴を頭に入れておくとよい。すなわち、金利が上昇すると債券評価損によって自己資本が低下するが、わが国の場合、それにも増してリスクアセットが縮小するため、Tier I比率がむしろ上昇する傾向がある。これは、銀行の自己資本比率からはあたかも健全性を維持しているようにみえても、経済全体をみると縮小均衡に陥っている可能性が高いことを意味する。国債金利の上昇シミュレーションを評価する際には、こうした点にも十分な注意が必要である。
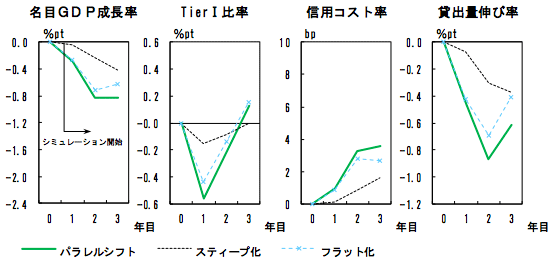
ところで、一口に国債金利が上昇すると言っても、イールドカーブの変動の仕方によって、銀行経営に及ぼす影響は異なり得る。一般に、マチュリティーが長いほど金利上昇が債券時価に及ぼす影響は大きい。しかし、邦銀の債券保有額をマチュリティー別に見ると、3年以下の短期ゾーンへの投資割合が非常に高い。したがって、短期ゾーンの金利上昇を抑えることができれば(スティープ化)、国債金利上昇の影響を抑制することができる。シミュレーション結果によると、スティープ化の場合、債券評価損は2兆円程度、Tier I比率は0.2%pt弱の低下にとどまる。
また、国債金利の上昇が、ソブリン・リスク・プレミアムによるものならば、市場金利一般が同時に上昇するとは限らない。金融機関が保有する公社債のうち国債の占める割合は約8割なので、仮に何らかの市場介入によって国債からその他の債券価格への影響が遮断されれば、債券評価損は最大で2割削減される。パラレルシフトのケースで比較すると、遮断が成功すれば、Tier I比率を0.2%程度押し上げることができる。
国債金利上昇のTier I比率への影響を評価する際、次のような「クッション効果」の存在に注意する必要がある。まず、国債価格が下落しても、有価証券評価益(株式の含み益を含む)が存在している場合には、ネットの債券評価損が小さくなる(2011年度上期末、対象行全体で1.9兆円の効果)。また、税効果(繰延税金資産)を勘案すれば、債券評価損のうち60%を損失としてTier I資本に反映させれば足りる(実効税率40%の場合)。もっとも、こうしたクッション効果は国債金利の上昇幅が大きくなるにつれて薄まっていく筋合いのものである。
最後に、バーゼルIIIへの移行に伴い、クッションの厚みが時間の経過と共に薄くなっていく(グランドファザリング、経過措置)点にも留意が必要である。また、資本の質の面でも、さまざまな資本性調達手段の自己資本への算入要件が厳格になる他、無形固定資産など資本控除される額も大きくなるため、Tier I資本の額は7割程度に減少すると考えられている(リスクアセットは1割程度増加)。したがって、もともと自己資本比率が低い銀行の場合、国債金利上昇に伴う債券評価損が銀行経営に何らかの影響を及ぼす水準にまで達しうる可能性はあながち否定できない。

