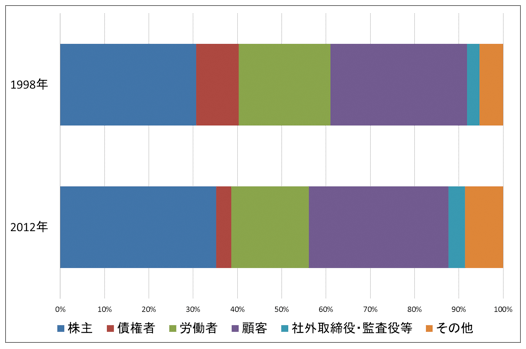| 執筆者 | 森川 正之 (理事・副所長) |
|---|---|
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
その他特別な研究成果 (所属プロジェクトなし)
問題意識
高度成長の終焉、さらにバブル経済の崩壊とともに、「日本的経営」の問題点が強く意識されるようになり、1990年代以降さまざまな制度改革が進められた。本稿は、企業に対するアンケート調査の結果を利用して、1990年代以降最近までの間の日本企業の変化について概観するものである。1990年代後半に実施された調査と同様の調査を新たに行い、日本企業の経営戦略、統治構造、内部組織、企業行動の面から「日本的経営」の変化を観察した。調査対象は、非上場企業や中堅・中小企業、製造業だけでなく非製造業を広くカバーしている。
結果の要点
日本の企業経営は徐々に変化してきている一方で、長期にわたり安定的な特徴も多い。経営の時間的視野が長いこと、従業員や取引先・顧客のステークホルダーとしての役割が相当に大きいこと、企業経営悪化時でも雇用調整が難しいこと、企業が従業員に対して企業業績向上へのインセンティブをさまざまな形で採用していることなどは法制度・経済環境の変化の下でも維持されている日本的経営の特徴といえる。
一方、業績指標として売上高よりも利益を重視する傾向が強まっている。また、利益処分、新分野への進出、不採算事業からの撤退、経営者の交代といった経営上の重要な意思決定に対する株主の影響力が拡大する傾向が見られ、債権者や労働者の影響力はやや低下している(図参照)。さらに、M&Aや不採算事業の売却といった大胆な事業再編が活発に行われるようになってきている。
政策的インプリケーション
近年の研究は、経営の質や経営慣行が国によってかなり異なること、それが企業の生産性に大きな影響を持つことを示している(Bloom and Van Reenen, 2010)。日本的経営の変化は、企業さらには日本経済全体の生産性を左右する可能性がある。
分析結果は、1990年以降に行われた会社法、独禁法、金融・労働関連制度等の累次の改正が企業の経営戦略、内部組織、市場行動に一定の影響を及ぼした可能性があること、日本経済全体の生産性を高めていく上で、基礎的な諸制度の設計の巧拙が重要な影響を持ちうることを示唆している。