このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
産業・企業生産性向上プログラム (第三期:2011~2015年度)
「東アジア産業生産性」プロジェクト
中国のように厳しい為替管理と外国為替市場への膨大な介入を行っている国では、自国通貨安の名目レートを長期に続けてもそれほど不思議ではない。しかし、そのような政策は国内物価の急上昇を引き起こし、異常な物価安(自国通貨安)は名目為替レートの騰貴ではなく、国内物価の上昇を通じて解消されるはずである。もしかすると中国では、何らかの構造的な要因の為に、均衡実質為替レートが大幅な自国通貨安の水準に留まっているのかもしれない。そこで我々は、購買力平価の視点から中国元がどれほど割安かを確認した上で、一次産業に労働余剰が存在するルイス・タイプの3部門経済成長モデルを構築し、経済発展の過程と絶対物価水準の関係を分析した。
図1は、中国、日本、韓国を含む世界各国の為替レート水準がその絶対物価水準と比べてどれほど割安・割高かを比較した結果である。1950年から2007年までの各国データをプールして比較している。バラッサ・サムエルソンの効果として知られているように、貧しい国ほど非貿易財の価格が安いため、この点を考慮しないと貧しい国の為替レートを過剰に割安に評価してしまう危険がある。そこでこの関係を直線で示した傾向線で把握し、各国の為替レートがこの傾向線からどの程度乖離しているかで為替レート水準を評価している。
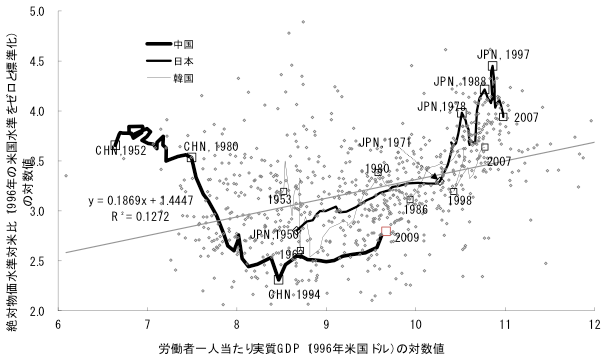
図を見ると、日本および韓国では1970年代前半のドルペッグ制の崩壊の頃を境に、市場為替レートで換算した国内物価が割高に(つまり自国通貨高に)推移してきたことが分かる。一方中国では、1980年代半ばに自国通貨が大幅に減価してのちは、一貫して傾向線の下に位置し(自国通貨安)、最近では傾向線との垂直方向の乖離が約30%と、非常に大きいことが分かる。
我々は次に、ルイス・タイプの3部門経済成長モデルを構築し、経済発展の過程と絶対物価水準の関係を分析した。その結果、一次産業に余剰労働が存在するルイス的な状況では、絶対物価は低い水準に留まること、中国のように製造業への労働移動の障壁が高く、また財・サービス純輸出対GDP比が高い経済では、労働者1人当たりGDPが十分に高くなるまで、このようなルイス的な状況からの離脱が起きないことが分かった。
中国では、元安を維持しようとする通貨政策だけではなく、以上のような構造的な要因の為に、均衡実質為替レートが大幅な自国通貨安の水準に留まっている可能性がある。この場合、将来構造的な要因が喪失したり、経済発展によりルイス転換点に到達した後は、強い元高圧力が生じ、現在のような介入政策による元安維持が狂乱物価を生み出す危険が飛躍的に高まる可能性が高い。なお、転換点到達までは、単純労働の賃金率上昇は抑制される。転換点到達を遅らせるような政策の多くはまた中国の所得格差問題を深刻にしていることにも注意する必要がある。

