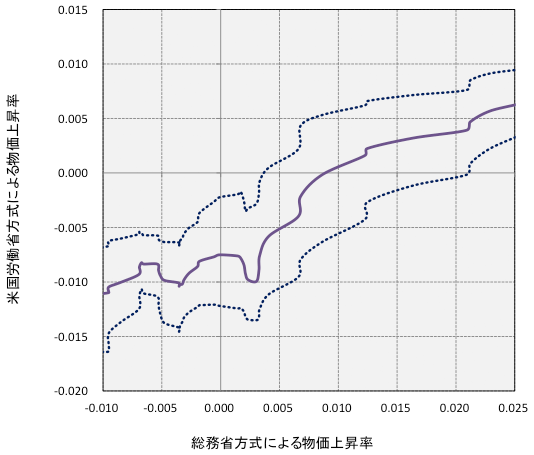| 執筆者 |
今井 聡 (総務省) 清水 千弘 (麗澤大学) 渡辺 努 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 日本の長期デフレ:原因と政策的含意 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
国際マクロプログラム (第三期:2011~2015年度)
「日本の長期デフレ:原因と政策的含意」プロジェクト
我が国では1990年代半ば以降、デフレが進行している。先進国でのデフレの発生事例は極めて限られているが、有名な例は1930年代の大恐慌期における米国である。このときには消費者物価が年間で約7%の速度で下落した。これに対して、我が国の消費者物価の下落率は年間で1%前後であり、激しい時期でも精々2%であった。米国大恐慌期のデフレと比べると我が国のデフレは緩やかといえる。では、日本のデフレ率はなぜ低いのか。日本の消費者物価が正確に計測されておらず、そのためにデフレ率が低く見えているに過ぎないとの指摘が聞かれる。とりわけ海外の研究者や実務家の間でそうした疑念が根強い。
消費者物価の計測方法を変えると数字はどれくらい変わるのだろうか。物価は経済の「体温」と言われるが、その喩えを使えば消費者物価統計は「体温計」である。1つの体温計が頼りにならないとすれば、別な体温計を試してみて、数値がどれくらい違うかを確認する必要がある。そうした問題意識から、この論文では「体温計」を取り換えて日本の体温を測り直すという実験を行った。具体的には、サンプル抽出方法として、(1)我が国の消費者物価統計を作成している総務省の方法に近いもの、(2)総務省の方法に似てはいるが特売価格の扱い方などいくつかの点で異なる方法、(3)米国の消費者物価統計の作成機関である労働統計局が採用している方法の3種類を試した。実験の結果、総務省方式に近い方法でサンプル抽出した場合には消費者物価の公表数字に近い数字が得られた。また、総務省の特売価格の扱いを変更するなどしてもさほど変わらなかった。しかし米国型のサンプル抽出を採用した場合は結果に大きな違いが見られた。
図の横軸は総務省方式で作成した物価指数の前年同月比を、また縦軸は米国方式で作成した物価指数の前年同月比を示している。たとえば、横軸で1%とあるのは総務省方式で前年比1%のインフレになった月という意味であり、それらの月において米国方式がどういう数字になっているかが縦軸に示されている。図の実線は中央値であり、横軸1%に対応する縦軸の値は0.1%だから、総務省方式で1%のときには米国方式の中央値は0.1%ということを示している。同様に、横軸2%に対応する縦軸の値は0.4%であり、総務省方式に比べて米国方式の数字が小さいという傾向がある。米国方式は対象商品を確率的に抽出するので、商品は抽出のたびに異なり得る。それに伴うばらつきがどの程度かを示すため、図では80%信頼区間を破線で示してある。たとえば、横軸の1%に対応する破線の値は-0.5%から+0.5%となっているが、これは総務省方式で1%の数字が得られたときに米国方式の数字は80%の確率でこの範囲にばらつくことを示している。
この結果は政策運営にどのような含意をもつだろうか。日銀が金融政策運営の目途(ゴール)としている消費者物価上昇率1%という水準についてみると、総務省方式で1%のインフレのときに米国方式の中央値はプラスである。これは1%の「のりしろ」を確保しておけば安全という日銀の主張と合致する。ただし、これはあくまで「平均」の話だ。信頼区間をみると、-0.5%から+0.5%とマイナス区間が含まれており、米国方式ではデフレ脱却がまだ達成されていない可能性があることを示している。図からわかるように、信頼区間の下限がゼロを上回るのは総務省方式の数字が2.1%に達したときである。つまり、どの体温計で測ってもデフレ脱却を果たせたと自信を持って断言するには、そこまで待つ必要がある。