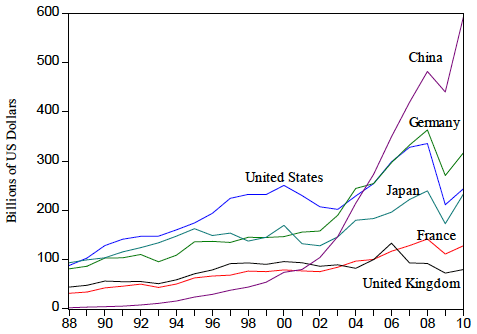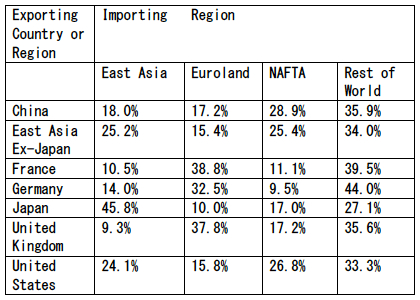| 執筆者 | THORBECKE, Willem (上席研究員) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | East Asian Production Networks and Global Imbalances |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
国際マクロプログラム (第三期:2011~2015年度)
「East Asian Production Networks and Global Imbalances」プロジェクト
資本財の輸出額は3兆ドルを超え、激しい動きを示している。過去20年間、資本財の主な輸出国は中国、フランス、ドイツ、日本、英国、米国である。図1は前述の輸出国による資本財・設備財の輸出額を示す。2003年までは米国が最大の輸出国であったが、その後ドイツと中国にとってかわられた。また、2008年の世界金融危機後に輸出が最も急減した国が米国であったことを示す。2008-2009年の間に米国の資本財輸出額は対数ポイントで46%減少した。米国に次いで減少率が大きいのが日本で、2008-2009年の輸出額は33%減少した。
資本財輸出の動きを理解する目的で、本稿は貿易弾力性を推定する。英国と米国の輸出は為替レートの影響を受けているが、ドイツとフランスの輸出は影響を受けていない。日本の場合、非アジア諸国向け輸出は為替レートに左右されているが、アジア諸国向けの輸出は、アジア諸国からその他地域への輸出に左右される。どの国の資本財輸出も輸入国側のGDPの影響を受ける。
資本財輸出は輸入国側の所得に左右されることから、輸出先を知ることは有益である。表1にこれを示す。フランス、ドイツ、英国はユーロ圏に最も依存している。中国と米国はNAFTA諸国により依存している。日本は地域サプライチェーンの川上にあり、資本財輸出額の46%が東アジア向けである。
本稿の推定結果は、ドル高と世界経済の成長鈍化によって2009年に米国の輸出額が急落したことを示唆している。また、日本の輸出量の急落は、円高、世界的な景気後退、アジア諸国の輸出急落という三重苦によると示唆している。2008-2009年の間の大幅なドル高と円高は、日米両国の資本財輸出額急落の原因となった。為替レートの行き過ぎがこのような悪影響を与える場合、金融当局は行き過ぎを制限する方策を考慮すべきである。