| 執筆者 | 武智 一貴 (法政大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | グローバル経済における技術に関する経済分析 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
貿易投資プログラム (第三期:2011~2015年度)
「グローバル経済における技術に関する経済分析」プロジェクト
本研究は、日本とアメリカの大規模医薬品企業の世界における供給パターンのデータを用い、それらが各国の知的財産権保護とどういった関係にあるかを明らかにしたものである。図はこれら医薬品企業が各国に供給している医薬品数およびライセンシングにより供給している医薬品数を表しており、その決定要因として知的財産権に着目した。分析では、医薬品の供給にはさまざまな要因が影響するため、市場特殊要因・医薬品特殊要因をコントロールした上で保護強化の影響を推定した。本研究の結果から、知的財産権保護が強化されている国ほど供給確率が低く、特に自社による供給確率が低くなる事が明らかになった。ライセンシングによる供給についてはそういった結果が得られておらず、保護の強化による供給の抑制というパターンが確認された。
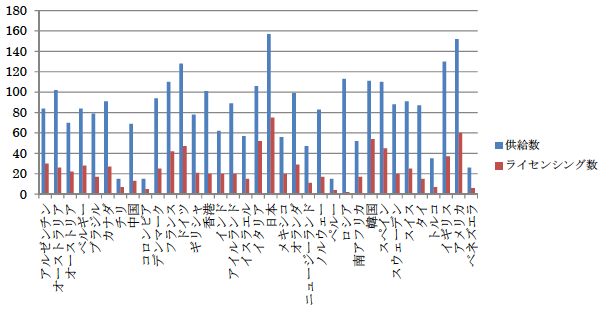
本研究の結果から、知的財産権保護の強化が一般に権利範囲の確定に役立ち、知的財産の取引の促進につながるという考えに対し疑問を呈することとなった。すなわち、累積的イノベーションの研究でも指摘されていることであるが、保護の強化がライセンサーの探索や交渉のコストを上昇させ、また、侵害リスクを不必要に高めることで、経済取引を阻害する要因になりうる事が明らかになった。従って、知的財産権の保護強化は経済活動にとって必ずしも望ましくない効果を生むことを示唆している。
また、これらの結果から、保護の強化の際には、知的財産権に関わる情報コストや法務コストを削減するような政策が同時に求められると考えられる。具体的には、各国における特許侵害に関わる手続きのハーモナイゼーションにより侵害手続の予見可能性を高め、侵害リスクと権利者保護のバランスを取った権利確定方法の採用(均等論(注1)の見直しなど)、国際的な取引に対する消尽論(注2)の積極的な採用などが考えられる。

