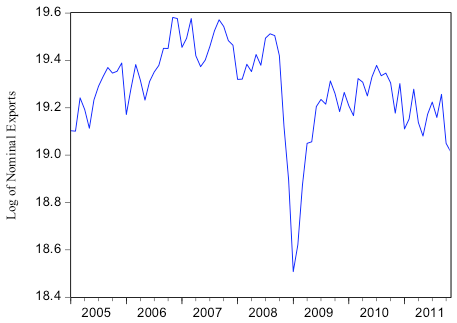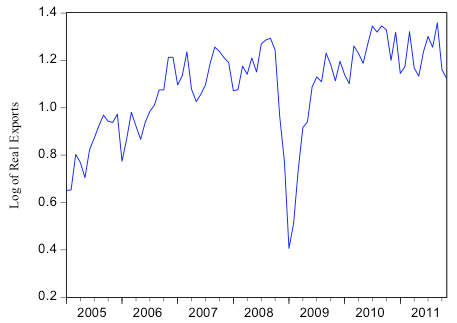| 執筆者 | THORBECKE, Willem (上席研究員) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | East Asian Production Networks and Global Imbalances |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
国際マクロプログラム (第三期:2011~2015年度)
「East Asian Production Networks and Global Imbalances」プロジェクト
世界金融危機以前、日本の輸出総額の約2割を電子製品が占めていた。こうした輸出の大半は東アジアの生産ネットワーク内向けであった。図1は日本から当該地域向けの電子部品輸出額を表している。2008年9月のリーマン・ショックから2009年1月の谷の間に輸出額は100%(対数ポイント。以下同じ)減少し、3年半を経た現在も平均輸出額はリーマン前の水準を約25%下回っている。図2は、日本から東アジア向け電子部品輸出量を表している。2008年8月から2009年1月の間に輸出量は88%減少したが、その後急速な回復を見せ、2010年にはリーマン・ショック前の水準を上回った。輸出量はリーマン・ショック前の水準を上回る一方で輸出額が回復していないという現状は、円建て輸出価格の下落を示唆している。2007年6月以降、円高に推移し始めると、電子部品・デバイス(ECD)の円建て輸出価格は円ベースのコストと比較して30%、情報通信機器(ICE)の円建て輸出価格は円ベースのコスト比較でそれぞれ20%も下落した。つまり、円高によって日本の電子部品産業の収益性が下がったことを示唆している。
本稿では、2007年6月から2011年末の間の円高によってECDの円建て輸出価格は25%、ICEの円建て輸出価格は20%以上も下落したことを示すエビデンスを提示する。つまり、円高によって電子機器産業の利益幅が大幅に圧迫されているのである。また、円高は電気計算機などの差別化製品より、シリコンウェハーといった汎用品の輸出価格を大幅に下落させたというエビデンスを示す。
最後に、10%の円高は最終電子製品の輸出量を10%減少させるというエビデンスを示す。