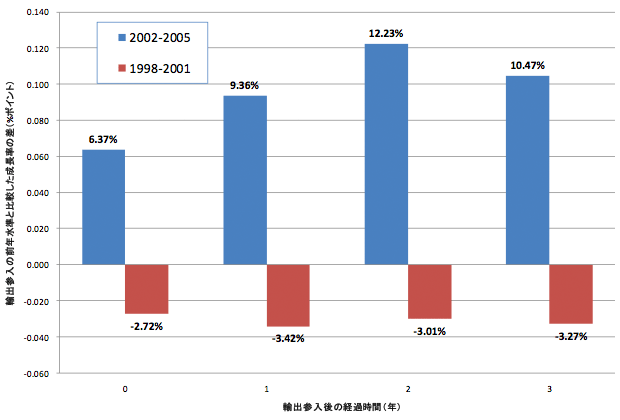| 執筆者 |
八代 尚光 (コンサルティングフェロー) 平野 大昌 (京都大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 企業活動の国際化とイノベーションに関する調査研究 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
基盤政策研究領域III (第二期:2006~2010年度)
「企業活動の国際化とイノベーションに関する研究」プロジェクト
問題意識
輸出を行う企業が国内企業に対し生産性が高いことは既定の事実として知られている。先行研究では、こうした輸出企業の優位性の形成について2通りの解釈が提示されている。1つは、輸出は大きな参入費用を伴うため、元から生産性の高い企業のみが自己選択的に輸出企業となるという見方である。もう1つは、輸出を通じた海外市場との接触が国内にはない知識や技術の吸収を通じてイノベーションを促進する結果、生産性が事後的に上昇するという考え方である。後者はしばしば「輸出の学習効果」と呼ばれ、輸出主導の経済成長を輸出主体である企業のレベルで解釈する視点として以前より指摘されてきたが、実際には各国の企業データを用いた実証分析では支持されないことも多く、解明の余地が大きい。近年の研究では、こうした学習効果が輸出経験の長さや外資企業との競合といったさまざまな要素によって規定されることや、学習効果とは別に、輸出参入が生産性を上昇させるイノベーション投資の期待収益率を引き上げる効果が報告されている。この研究では、輸出と生産性の関係を規定する新たな要因として輸出環境の違いに着目する。もし学習効果の発生には海外市場との継続的な接触が重要であるならば、それは良好な輸出環境の下でより実現しやすい。また、イノベーション投資の期待収益率は将来の期待輸出需要に依存するが、こうした期待形成は輸出環境の影響を受けるだろう。このような視点から、2002年から2005年までの輸出ブーム期とアジア通貨危機直後の1998年から2001年という、2つの対照的な輸出環境の下で、輸出参入が事後的な生産性の変化に与えた効果を検証した。
分析内容
経済産業省の「企業活動基本調査」における製造業企業の個票データを用いて、多くの先行研究で採用されている手法に沿って、Propensity Score Matchingにより輸出企業と輸出に参入する確率の近い国内企業のみを集めた後、Difference-in-Differenceにより輸出参入の生産性への事後的な効果を推計した。その結果、輸出に参入した企業はその後3年間にわたり、国内企業よりも最大で12%ポイント有意に高い全要素生産性の成長率を実現したが、こうした輸出参入の効果は好調な輸出環境の下でのみ認められた。輸出参入が生産性に与える効果には2つの期間の間で統計的に有意な差が存在する。こうした違いは堅調な輸出需要の有無による設備稼働率の違いに基づいている可能性もあるが、先行研究では稼働率の上昇による生産性への効果はきわめて短期的であると考えられている。また、「輸出の学習効果」の存在を主張した先行研究と同様、こうした輸出参入の効果は高所得市場へ輸出した企業のみが享受したことも分かった。さらに、輸出参入が研究開発支出をより増加させる有意な効果も検出されたが、これもやはり好調な輸出環境の下でのみ認められた。これらの一連の結果からは、輸出環境の違いが輸出参入とイノベーションの関係を規定していることが示唆される。本研究からは、中小企業振興の観点から政府が注力している海外進出支援は、より良好な輸出環境の下で行われる場合に、イノベーションを通じた中小企業の中長期的な成長に結びつく可能性がより高いと考えられる。