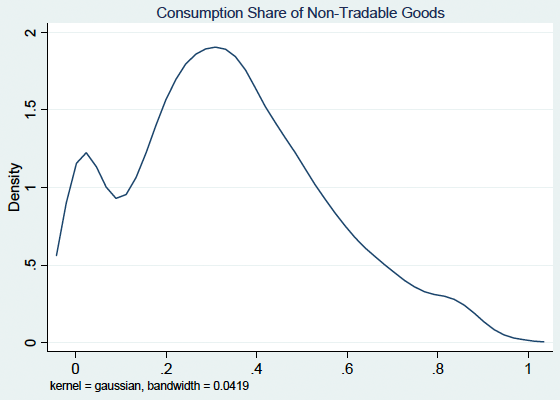このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
本稿は、ベトナムの村落コミュニティにおける助け合いの仕組みについて、特に自然災害に対するそうした仕組みの有効性という視点から実態把握を行ったものである。より詳細には、マクロ経済学の分野では標準的な議論となってきた「消費リスクシェアリング仮説」を「助け合いメカニズム」に関する理論的・実証的枠組みとして採用し、貿易財(交換財)と非貿易財(自家消費財)を明示することでモデルを拡張し、そうした理論の必要条件を、ベトナムで集計した独自の家計データを用いて検証した。
我々のデータによると、非貿易財(自家消費財)が各世帯の消費全体に占める割合はかなり大きい (図1参照)。こうした実態を踏まえた上で、自家消費財を明示的に考慮した上で、鳥インフルエンザや干ばつ、洪水等の自然災害が起こった場合の、リスクシェアリング(助け合い)を達成するうえでの市場・非市場メカニズムの有効性を検証した。精緻な実証分析を行った結果、ベトナム農村においては、リスクシェアリング仮説が棄却できないことが分かった。他方、非貿易財(自家消費財)を区分しない、従来の検証方法ではリスクシェアリング仮説が棄却されることもわかった。これらの分析結果は、リスクシェアリングを棄却した既存研究では過少定式化バイアスが生じていることを示唆している。また、我々は、借入制約はリスクシェアリングを阻む制約となっているとみられるのに対し、コミットメント制約はリスクシェアリングを阻む制約とはなっていないことが分かった。
これらの結果から、ベトナムにおける市場・非市場的なリスクシェアリングメカニズムの欠如が、自家消費の増減によって補填・調整されているということがいえるかもしれない。しかし産業化によって、自家消費の保険メカニズムとしての役割はおのずと減少すると予想されるので、自然災害に対する公的な保険メカニズムを事前に構築することは今後不可欠となろう。たとえば、農業生産と連動したインデックス型の保険契約などの新しい仕組みを構築してゆくことが、今後の研究で重要なトピックとなるであろう。