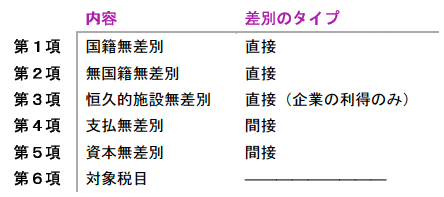| 執筆者 | 増井 良啓 (東京大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 通商関係条約と税制 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
日本国が締結した二国間租税条約には、ほぼ例外なく、無差別条項が置かれている。この規定は、所得税や法人税のみならず、他の税目にも適用範囲を拡張していることが多く、税制全体に与える潜在的なインパクトが大きい。
ところが、この条項は、二国間租税条約の趣旨目的との関係でその存在意義がはっきりしないのみならず、さまざまな点でもれやギャップを有している。そもそも、一定の差別を禁止するとはいっても、居住者と非居住者を区別してもよいことが暗黙の前提とされている。たとえば、日本の所得税は、居住者に対しては全世界所得に課税し、非居住者に対しては国内源泉所得に課税する。これが所得税制の根幹的ルールであり、日本国との人的つながりの大きさに応じて国内法上区別を行っている。このような基本構造が確固として存在するため、いくら租税条約の無差別条項が内外差別を禁止するといっても、国内法で合理的な内外区別を行うことは許容せざるを得ないのである。
よりこまかく規定の内容を検討すると、この条項の中核である第3項の適用範囲は、「恒久的施設」(たとえば、事業所)を通じて「企業の利得」を稼得する場合に限定されている。さらに、無差別条項のすみずみに、いくつものこまかい適用除外規定が明示的に設けられている。その結果、各国の税制上存在する内外区別について、この条項が果たしてどこまでのことを禁じているかについて、一貫した体系的指針に欠ける状態になってしまっている。
今後、OECD租税委員会を中心に、無差別条項の規定をどう改正していくべきかについて検討が進むものと予想される。そのような検討に際して、租税条約上の無差別条項の適用範囲の拡大を図る場合には、国内税制の基本構造との整合性に留意しつつ、国際課税ルールをめぐる全体構想の一部としてこれを論じていくことが望まれる。