| 執筆者 | 土居 丈朗 (慶應義塾大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 社会経済構造の変化と税制改革 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
我が国の税制改革論議の中で、消費税増税とともに、法人課税が国際的に見て負担が重いとの議論がある。ところが、消費税増税と法人税減税という政策パッケージは政治的に受け入れられないとの見通しもある。その背景には、消費税は主に消費者が負担し、法人税は主に法人が負担するとの直感がある。しかし、これは租税の転嫁と帰着の問題であるが、学術的な研究の裏づけが明確に示されないまま主張が展開されているように思われる。こうした現状から、本稿では、法人税負担の転嫁と帰着について、客観的な分析を可能にする動学的一般均衡理論を構築した上で、数値解析を試みた。
これまで、租税の転嫁と帰着に関する分析は、Harbergerらの先駆的な研究に端を発し、それを静学的分析から異時点間の資源配分も考慮した動学的分析に発展させて今日に至っている。ただ、企業が"going concern"で経営を続けることを念頭におくと、短期の効果だけを捉える静学モデルでなく、長期の効果をも分析できる動学モデルを用いる必要がある。さらに、Feldsteinらで提起された定常状態における租税の帰着に関する動学的分析があるが、この分析は定常状態における租税の帰着にとどまっており、動学モデルにおける移行過程での租税の帰着の分析はなされていない。そこで、本稿では、法人税の転嫁と帰着について、異時点間の資源配分の効率性をも考慮した形で、我が国のデータに基づいて分析した。
本稿の分析に用いる理論モデルは次の通りである。後述する数値解析を行う便宜上、離散時間モデルを採用する。多数存在する家計を代表して、代表的家計の行動を記述しよう。代表的家計は無限期間生き、将来について完全予見で、毎期、私的財の消費、余暇(利用可能な時間のうち労働供給しない時間)から効用を得る。その毎期の効用を割引現在価値化した生涯効用を最大化するように、毎期の私的財の消費、余暇を決める。
企業は、労働(l)と資本(k)を投入して、利潤を最大化するように財を生産する。資本については、資本減耗があるものの新規の設備投資を行うことで翌期の資本を増やすことができる。
政府は、法人税を課税し、税収を家計に一括固定給付として支出する。後述する数値解析を行う便宜上、実際に課税している労働所得税、利子所得税、消費税も、この理論モデルに導入している。
毎期、家計の効用最大化条件と企業の利潤最大化条件を満たし、財市場、労働市場、資本市場等の需給が均衡する状況を考える。各期の状況から、この理論モデルにおける今期から来期にわたる移行過程が描写できる。さらに、消費、労働、資本が毎期一定となる定常状態についても描写できる。
租税の帰着については、Feldsteinの定義に従い、労働所得に帰着された租税負担の割合を、
![]()
とする定義を採用する。ここで、wは賃金率、rは利子率で、dwは(法人税率の変化を受けた)賃金率の変化、drは(法人税率の変化を受けた)利子率の変化を意味する。そこで、法人税率を限界的に引き上げたときに労働所得に帰着する租税負担Jはどのように変化するかを分析する。ただし、ここでは法人税率を引き上げたときの税収の変化は、同年度の家計への一括固定給付を変化させる形で対応すると仮定する。他の税率や政府支出や公債発行などには影響しない状況を想定している。
この理論モデルに基づき、日本経済のマクロ分析を行った先行研究で用いられた関数を特定化やパラメータの値を利用する。本稿の分析では四半期ベースとし、1期は1四半期とみなして数値解析を行った。いま1期目に法人税率を現行税率の1%相当分(すなわち0.3%ポイント)引き上げたとき、法人税が労働所得に帰着された度合Jは、図1のようになる。
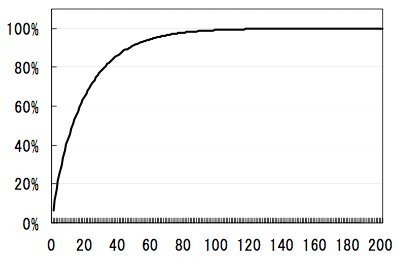
図1によると、本稿で採用したパラメータの値の下では、法人税の負担は、短期的(1期目)には6.2%が労働所得に帰着し、93.8%が資本所得に帰着し、1年程度(4期目)のうちに20%以下が労働所得に帰着し、80%以上が資本所得に帰着するが、時間が経つにつれて労働所得に帰着する割合が高まり、長期的には100%が労働所得に帰着することが示された。さらに、本稿では、資本分配率、割引率、資本減耗率などが、図1の分析と異なる値である場合の法人税の帰着も分析している。
これらは、法人税率を引き上げた場合についての分析であるが、法人税率を限界的に引き下げた場合も、ここで示されたものと同じ効果が得られることを確認した。
本稿で採用したパラメータの値の下では、法人税の負担は、短期的(1年目)には約10~20%が労働所得に帰着し、約80~90%が資本所得に帰着するが、時間が経つにつれて労働所得に帰着する割合が高まり、長期的には100%労働所得に帰着することが示された。また、資本分配率、割引率、資本減耗率などによって、法人税負担の帰着の時間的経過が影響を受けることも示された。

