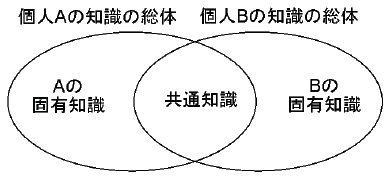| 執筆者 | Marcus BERLIANT (ワシントン大学)/藤田 昌久 (所長) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 少子高齢化と日本経済-経済成長・生産性・労働力・物価- |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
本論文は、知識創造活動に携わる人々の間における頭脳ないし知識の(水平的な)多様性を重視した、知識創造と伝播の新たなミクロ動学モデルを提案する。更に、そのモデルをHelpman・Romer型の内生的成長理論と融合することにより、R&Dにおける知識労働者の多様性と経済成長の間の相互的なダイナミズムを分析するとともに、日本経済の1990年代からの長期停滞と低成長の根本的な理由についても検討する。
前世紀の末から、世界の経済は従来の大量生産に基づく工業化社会から、広い意味でのイノベーションないし知識創造活動を中心的な活動とする、いわゆるBrain Power Societyないし知識創造社会に移行しつつあると思われる。この知識創造社会における中心的な資源は、さまざまな知識を持ち、新たな知識を学習し、それをもとに新たな知識を創造する能力を持つ、個々の頭脳そのものである。ただし、個々の頭脳は広い意味でのソフトウェアであり、同じソフトウェアからは相乗効果は生まれない。経済社会全体にとって重要なのは、多様な頭脳の相互交流から生まれる相乗効果を生かすことである。
多様な頭脳からどのように相乗効果が生まれるのか。その核心は、古くからの諺「三人寄れば文殊の知恵」にある。説明を簡略化するために、図1のように、個人Aと個人Bの「二人の知恵」を考えよう。まずAの知識の総体とBの知識の総体がある。AとBはある程度の「共通知識」を持っていないと有効にコミュニケーションができない。一方、各自がある程度の「固有知識」を持っていないと協力する意味がない。従って、知識創造の共同作業では、共通知識と各々の固有知識の適度なバランスが重要である。ただ、二人で長期間密な協力活動がなされると、共通知識の割合が増えすぎ、「三年寄ればただの知恵」に終わる。従って、大きな頭脳集団を有する一般の経済社会においては、共通知識の肥大化を避けるために、適当な期間ごとに、頭脳パートナーが相互に次々と入れ替わることが重要である。
以上の考えを、動学的な数理モデルとして一般化し、それをHelpman・Romer型の内生的成長理論と融合した。経済は、水平的に差別化された多様な財を消費者に供給する製造業部門と、新しい財の青写真(blue print)をパテントとして製造業部門に供給するR&D部門より成る。製造業における各企業はパテント付きの財の青写真をR&D部門より購入し、特定の財を同質の(普通の)労働者を用いて生産する。R&D部門においては、水平的に異なった知識の総体を持つ多数のR&D workerによって、新たな財の青写真が、単独で、あるいは、二人でパートナーを組んで生産される(単純化のために、ここではR&Dパートナーは二人の場合に限定される)。各々のR&D workerは新しい知識を、自身のR&D活動を通じて、また登録されたパテントの公開情報から自身の学習能力に応じて獲得し、知識の総体を拡大していく。
初期条件として、R&D workers全体の相互間における知識の多様性が比較的小さい状態を想定する。そうすると、各々のR&D workerが自分にとって最も知識生産性の高い相手とパートナーを一定期間組み、その後新しいパートナーを組み直すことを繰り返すことにより、R&D部門全体は長期的には自己組織化を通じて、社会全体の知識増加率が最も高い、理想的な状態に到達する可能性が大きいことが示された。
その理想的な状態においては、R&D workers全体は、比較的小さな最適な大きさの頭脳集団(研究所ないしは大学)に分化している。各々の頭脳集団の内部では密な相互交流が行われているが、集団間では緩い交流しか行われない。最適な頭脳集団の大きさは、「共通知識」により大きなウェイトを置く「改善型」のR&D活動の場合には、比較的小さい。一方、バイオやソフトウェアなどの、「固有知識」により大きなウェイトを置く「フロンティア開拓型」のR&D活動の場合には、最適な頭脳集団は非常に大きい。また、ITなどの発達により、パテント等の公開情報の伝播速度が速くなった場合には、最適な知識集団は、集団内部での共通知識の肥大化を避けるために、より大きくなる必要がある。
ただし、現実においては、それまで理想型に近かったR&Dシステム全体が、IT革命などの大きな技術変化に応じて、新たな理想型に移行することは容易ではない。これは、一度形成された各々の頭脳集団は、内部でそれぞれ固有の「共通知識」を蓄積していき、それがロックイン効果を及ぼし、R&D workerの組織間の移動を妨げ、R&Dシステム全体が硬直性を持つからである。
このR&Dシステムにおける負のロックイン効果が、改善型を主とした従来の日本のR&Dシステムが、IT革命や急速なグローバル化のもとで必要とされるフロンティア開拓型の新たなR&Dシステムへの移行を妨げているものと思われる。実際、Walsh and Nagaoka(2009)は、日米のパテントの発明者サーベイにより、日本における発明者の組織間(企業ないし大学間)のモビリティは、米国おけるよりも、遙かに低いことを示している。また、米国における発明者の30%近くは、外国生まれであるが、日本ではそれは皆無に近い。これは、21世紀に求められているフロンティア開拓型のイノベーション・システムに日本が移行していくためには、従来より遙かに固有知識重視の、多様性豊かで流動性の高い、経済社会システムの再構築が必要であることを示唆している。