近年、景気変動を分析するための新しい手法として、「景気循環会計(Business cycle accounting, BCA)」が開発された。筆者はこの手法で日本経済の1980年代~90年代のデータを分析し、90年代の長期不況の要因を探った。ここでは、研究結果(Kobayashi and Inaba, 2005)の一部を紹介する。
景気循環会計とは
景気変動をマクロ経済学的に分析する手法としては、Kydland and Prescott(1982)の研究を端緒とするReal business cycle models(RBC)が発展してきた。景気循環会計は、以下に説明するように、RBCと一種の双対関係にある方法論である。RBCの特徴は、消費者や企業の合理的な最適化行動を明示的にモデル化していることである。一国の経済は、消費者が効用を最大化し、企業が利潤を最大化するために競争する動学的一般均衡モデルとして記述される。消費者や企業の最適化行動の結果としてマクロ経済全体の消費や投資、物価変動などのマクロ変数が計算されることになる。この点は、マクロの消費や投資を、利子や所得のアドホックな関数と仮定していた従来のケインズ経済学的なモデルと違う最大の長所である。
現実の経済では、消費者や企業は政府の政策や将来の経済環境を予想して行動するので、大きな政策変更や環境変化があれば、ケインジアン・モデルで推計した消費関数の形状は変化してしまう(ルーカス批判)。従来のケインジアン・モデルでは、そのような変化をモデルで考慮できなかったが、消費者等の最適化行動をモデル化したRBCはその欠点を克服するものであった。
RBCの標準的な方法論は次のとおりである。景気変動を引き起こす原因と考えられる要素(設備投資の完成までに時間がかかること、資金の借り手と貸し手の間に情報の非対称性があることなど)を理論的に仮定して一般均衡モデルを構築し、それに現実的なパラメータの値を与えてコンピュータの数値計算で解析する。その結果計算された生産、消費、投資などの動きが、どれだけ現実の景気変動の動きに近いかを比較検討する。
RBCはあくまでコンピュータシミュレーションなので、計算結果が現実の経済データと一致することはなく、変数の動き方が似ていることや変数間の共分散などが現実のデータと似ていることが、モデルの良し悪しの判定条件となる。まず、「理論モデルを立て、そのシミュレーション結果が、どれだけ現実のデータに近いか」を見るのがRBCの方法論である。
これに対して、景気循環会計は、「現実のデータを完全に説明するためには、理論モデルには、どのような特徴(後述の『ゆがみ』)がなければならないか」を探る。つまり、RBCの発想を逆転させたのが景気循環会計であると言える。
この考え方は、同時期にChari, Kehoe, and McGrattan(2002)とMulligan(2002)によって発表された。以下では、主にChari, Kehoe, and McGrattan(2002)に沿って景気循環会計を説明する。
景気循環会計では、RBCと同様に、一国の経済を新古典派の動学的一般均衡モデルで近似できると仮定する。消費者や企業は、最適化行動の結果として、消費、投資、労働投入などを決めると仮定される。各変数を選択するにあたって消費者や企業が何のゆがみにも直面していないならば成り立つはずの関係式が、理論的にモデルから導出できる。たとえば、労働投入が効率的ならば、消費と余暇の限界代替率(消費者が、消費をどれだけ増やせるなら余暇を一単位追加的に犠牲にして働く気になるか、を示す比率)が労働の限界生産性(企業が、労働投入を一単位増やすと、どれだけ生産が増えるかを示す比率)と理論上等しくなるはずである。しかし、何らかの原因で労働投入が非効率になると、限界代替率と限界生産性は一致しなくなる。限界代替率と限界生産性の不一致の度合いを測ると、それが労働投入の「ゆがみ(wedge)」の大きさをあらわすことになる。
同じような方法で、設備投資や生産性についても、何のゆがみもないとすれば成り立つはずの関係式と、現実のデータをつきあわせることによって、設備投資や生産性の「ゆがみ」を計測することができる。
こうして計測された各分野の「ゆがみ」を、今度は一般均衡モデルに仮定して、シミュレーションを行うと、ちょうど現実の経済データを再現できることになる(現実の労働投入などのデータが、ちょうどモデルの関係式を満たすように、関係式に含まれる『ゆがみ』の値を決めたから)。つまり景気循環会計は、現実の経済変動をいくつかの「ゆがみ」の効果に分解するものであり、それらの「ゆがみ」の効果をすべて合計すると、現実のデータが完全に再現できる。現実の景気循環を説明する「会計」的手法、といわれる所以である。
さらに、こうして測定された各セクターの「ゆがみ」1つ1つについて、そのゆがみがあった場合となかった場合で、経済がどのように変化するかをモデル・シミュレーションで示すことができる。たとえば、投資のゆがみがある場合とない場合で、シミュレーションの結果があまり変化しないならば、投資のゆがみは景気動向にあまり影響していなかったと判断できる。このようにシミュレーションによって、どの「ゆがみ」が日本の長期不況を引き起こしたのか、ということを推定できるのである。
ただし、注意しなければならないことは、景気循環会計で各「ゆがみ」を計測したとしても、その「ゆがみ」が引き起こされた経済理論的なメカニズムは必ずしもわからないということである。「ゆがみ」を発生させたメカニズムは、別途、何らかの方法で推測あるいは特定しなければならない。以下では、日本経済のデータで景気循環会計を行った結果を示し、主要な「ゆがみ」の原因を推測する。
日本の長期不況の要因分析
日本経済について、シミュレーションの結果を示したのが次の図1である。不況を引き起こした可能性のある「ゆがみ」として、
・労働投入のゆがみ(Labor wedge)
・設備投資のゆがみ(Investment wedge)
・生産性の変化(Efficiency wedge)
・政府の財政支出の変化(Government wedge)
をまず計算し、それぞれのゆがみ、変化がどういう効果を国民総生産(GNP)に対して持っていたかをグラフで示したものである。
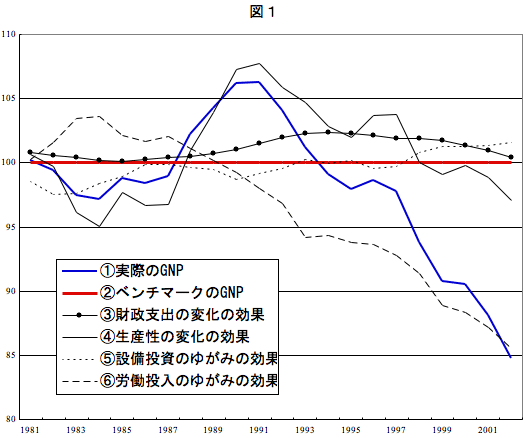
現実のGNPの動きを示したのが、太線(1)である。基準となる水平線(線(2))は、労働、投資、生産性、財政のゆがみ、変化が1984~89年の平均値に固定されていたとした場合の仮想的な国民総生産をあらわす。これは90年代以降の景気変動を見るときのベンチマークであり、すべての基準とするため水平線で示した。線(1)、(3)~(6)は、ベンチマークのGNPを100としたときの相対値を示している。
まず財政支出の変化が景気に与えた効果は、線(3)である。90年代、線(3)は基準線(2)よりも上にきているので、財政の変化は景気を押し上げる効果があったことになる。しかも、消費税増税のあった1997年でも財政の景気拡大効果は失われていない。消費税増税が景気悪化を招いたという説は、景気循環会計の結果と矛盾するといえるかもしれない。
生産性の変化による景気の変化は、線(4)で表される。現実の動き(線(1))と形状は似ているが、90年代末の金融危機までは基準線(2)の上にきている。このことは、生産性の悪化が経済を押し下げる効果が90年代末までは強くなかったことを示唆している。何らかの原因で生産性が悪化したことが長期不況の原因だったという見方は、現在かなり有力な説だが、景気循環会計の結果は、生産性の悪化が長期不況の決定的な要因ではなかったかもしれない、という可能性を示すものといえよう。
次に、設備投資のゆがみによる景気の変化は、線(5)である。これは、90年代にはだいたい基準線付近にあり、企業の投資は景気を悪化させた大きな要因とは言えないことがわかる。これも通念とは少し違った結果である。企業が不良債権問題で苦しみ過少投資になったのが不況の主因だ、というイメージがあるが、景気循環会計で見ると、必ずしもそうとは言えない。少なくとも、不良債権などの金融問題は、設備投資に悪影響を与えなかった可能性があるわけである。しかし一方で、90年代に企業の設備投資が大きく落ち込んだことは事実である。では何が設備投資の落ち込みの原因だったのだろうか。断定はできないが、労働投入のゆがみが悪化したことがその原因だった可能性があると考えられる。後述するように、担保制約と資産価格の下落が労働投入のゆがみを悪化させ、また設備投資も押し下げていたのではないか、と思われるのである。
最後に、線(6)は労働投入のゆがみが経済を押し下げる効果を示している。90年代初頭以降、労働のゆがみの効果は悪化の一途をたどっていたことが分かる。他のゆがみと比較すると、労働投入のゆがみが、長期不況の最大の要因であったと言えそうである。
なぜ労働投入は非効率になったのか
労働投入のゆがみが増大したこと(すなわち限界代替率と限界生産性の乖離が広がったこと)が長期不況の大きな要因であったことは景気循環会計から分かった。しかし、労働投入がより非効率になった原因としては、複数の異なる説明が考えられる。
1つの説明は、労働投入のゆがみは、日本経済の長期的な構造変化の結果として起きている、というものだ。そうだとすると、「ゆがみ」の変化は実は不況の発生と関係なく、不況の以前から続いていた、ということになる。たとえば、労働者の社会的地位の向上に伴って、労働者の賃金交渉力が趨勢的に高まってきたとすれば、労働投入の「ゆがみ」の拡大としてデータに表れるかもしれない。
そこで、長期的な労働投入のゆがみの推移を示したのが図2である。労働投入のゆがみは1984年から悪化しはじめていた(細線)。しかし、労働のゆがみがトレンド的に悪化しているように見えるのは、何らかの測定誤差による可能性もある。実際、生産関数の形を調整(※)して改めてゆがみを計測すると、太線のようになる。調整されたゆがみは、不況開始と同時に悪化が始まっている。つまり、不況より前に労働のゆがみが悪化していたという細線の結果については、測定誤差であった可能性も排除できないと思われる。
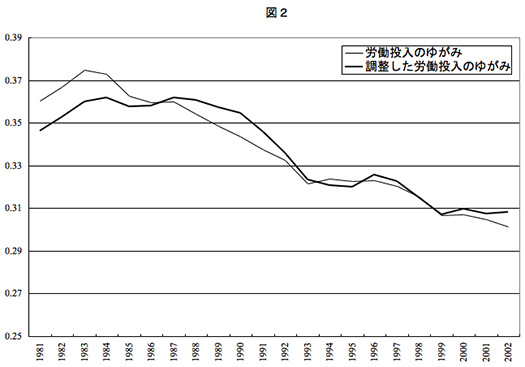
労働のゆがみの悪化が不況開始と同時に始まったのだとしても、非効率化の原因としてはいくつかのメカニズムが考えられる。
標準的な説明は、賃金の粘着性(あるいは下方硬直性)であろう。賃金が粘着的であるときに、金融引き締めなどのデフレショックが加わると、実質賃金が上昇し、労働投入が非効率になる。この説明は、たしかに90年代初頭の出来事とは整合的である。バブル末期にはかなり強い金融引き締めが行われた。しかし、この説明は、90年代後半のデータと矛盾するように思われる。労働のゆがみは90年代を通じて悪化し続け、2000年代に入ってもさらに悪化し続けている。一方、実質賃金は90年代半ばから低下し始めている。実質賃金の高まりが労働の「ゆがみ」を大きくしていたのなら、90年代後半も、実質賃金は上がり続けなければならなかったはずだ。
90年代後半も労働のゆがみが悪化し続けたことを説明する仮説として、現在、筆者が検討しているのは、「地価や株価の下落が、担保制約を経由して労働の『ゆがみ』を拡大しているのではないか」という考え方である。標準的な新古典派モデルでは、消費者が消費と投資を両方とも行うことを仮定している(企業は、消費者から資本を借り、労働力を買うだけである)。消費者にとって、消費と投資の合計をファイナンスするために借り入れが必要で、その借り入れには担保が必要だという「担保制約」を仮定する。すると、担保資産の価格が下がれば消費と投資が抑制され、結果的に労働投入も減ることが示される。つまり、担保制約のある経済で資産価格が下がり続けると、労働投入のゆがみが悪化するように見えるのである。
ちなみに、消費者は異時点間で消費をスムージングしようとするから、設備投資の方が、資産価格の下落によって、いっそう厳しく減少することになる。
日本では土地担保の借り入れが主要な資金調達手段であったことと、地価が90年代以降も一貫して下がり続けていることを考えあわせると、このような説明にはかなり説得力があるように思われる。
アメリカの大恐慌についての景気循環会計でも、1930年以降、労働投入のゆがみが急激に拡大したことが示されている。大恐慌も資産価格の大幅下落によって始まったことを考えると、日本との共通性を感じさせる。いずれにしても、労働投入のゆがみの悪化は、大恐慌型の不況が発生することと、何らかの重要な関連性があると考えられる。このメカニズムを明確に説明することが長期不況に関する経済理論の大きな課題といえる。


