はじめに
経済産業研究所の研究プロジェクトとして、企業が福祉に関与することの意義と、将来あるべき姿を探求してきたが、その研究成果を「企業福祉の制度改革」と題して、東洋経済新報社から出版した。本稿はその簡単な要約である。
企業がなぜ福祉に関与するようになったのか
企業が福祉に関与する方式には2つの種類がある。それら法定福利厚生費(社会保険料の企業主負担)、非法定福利厚生費(企業内福祉)の双方に関して、企業がどのような形で福祉に関与してきたか、なぜ福祉に取り組むようになったのか、19世紀末から20世紀初頭にかけてのいくつかの先進国の歴史をたどってみた。さらに現代において、国際比較の視点から、各国がどのような特色をもっているかを論じてみた。ここで、それらから得られた含意を簡単にまとめておこう。 第1に、産業革命以降多くの国で工業化が進んだが、一部の大企業の資本家はパターナリズムに立脚して、従業員の福祉に熱心であった。企業も福祉に関与すべきとの思想が一部に根づいていたことがわかる。これは後の時代になって、企業が法律によって強制的に福祉に関与するような制度に発展することの土壌になっていた。
第2に、工業化の進展は労働者を過酷な労働に追い込んだ。労働者の意識の高まりと労働組合の形成、そして社会主義思想の台頭によって、労働条件の向上や労働者の権利獲得をめぐって資本家との対決姿勢が高まった。労働側の要求に対して、国による温度差、産業による差、企業規模の差、等はあったが、企業側も福祉向上に一定の理解を示した。
第3に、企業側が福祉に取り組む動機はさまざまである。1つには、福祉の向上は労働者の勤労意欲を高めるのに役立つとする、いわば労務管理上の目的がある。2つには、本心をいえば、福祉のために企業負担を進んで拠出するものではないが、時の政府が法律で負担を求めてくるので、仕方なく受け入れるというものである。
第4に、第3の点に関連して、前者の動機は非法定福利厚生の解釈として有効であり、アメリカや日本の大企業による福祉資本主義につながる。後者の動機は法定福利厚生費への企業負担が、なぜ広まったかを説明するものであり、イギリスのベヴァリッジ報告が倫理的な基礎になっている。
第5に、非法定福利厚生と法定福利厚生は対象とする労働者が異なることに留意したい。すなわち、前者ではその企業に勤務する労働者のみにベネフィットが及ぶのに対して、後者では、財政負担を担うものの、そのベネフィットは匿名のその国の全労働者ないし全国民が受ける。企業の立場からすれば、前者への拠出は労務管理上役立つと判断するが、後者への拠出は渋々受け入れる側面がある。しかし後者であっても、企業が社会の構成員として公共政策に積極的に貢献する必要がある、という自覚さえあれば、あながち“渋々”とはいえない。そこには、「企業は社会の公器である」との理解が背後にあるとみなせる。
第6に、非法定福利厚生は企業の支払能力に依存するので、サービスを受ける労働者によってその格差が大きく異なる。日本はアメリカとともに、企業の規模に応じて企業内福祉に大きな差があることはよく知られている。この不公平を除去するには、非法定福利に頼るよりも法定福利に頼るほうが望ましい、という考え方はありうる。それよりさらに公平性を保つには、財源を国民から税収に求めて、福祉サービスはどの職業とか、どの企業に勤務しているとかの差がなく、すべての人が同質の福祉サービスを受けるのがよい、という考え方もありうる。
福祉の国際比較
ここで述べた6つの結論は、表1によって国際比較から次のようにまとめられる。北欧諸国の福祉水準は高く、日本、アメリカ、スイスは逆に低い。他の諸国は中レベルとみなせる。ただし、福祉のレベルは公共部門の提供するものだけを念頭においているので、日本が総合的に見て極端に低かったとは断定できない。日本とアメリカは家族(日本)と企業の非法定福利厚生(アメリカ)がそれを補完しているのである。
負担をどの方法で行なっているかに関しては、税が中心と社会保険料が中心の国があってさまざまである。社会保険料も企業と被保険者の負担割合は一様ではない。負担の方法は国によって大きく異なるといってよい。
企業の役割に注目すれば、企業の社会保険料の負担が大きい国は、デンマークを除いた北欧諸国とドイツ、フランス、イタリアの大陸ヨーロッパ、ということになる。それが逆に低いのは主要国のなかで日本、イギリス、アメリカである。ただし、アメリカは非法定福利厚生費が相当高いので、企業の役割はそう小さくない。
最後に、まとめの意味で、日本に関する結論を述べておこう。わが国の企業は法定福利としての保険料の事業主負担と、非法定福利厚生費は諸外国と比較して低い。ただし、非法定福利厚生費は大企業に限定すればそう低くはない。
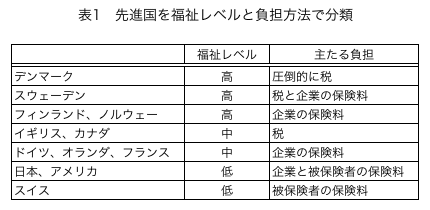
わが国の企業福祉の現状と課題
わが国では経営家族主義という解釈がなされることがあるように、企業(特に大企業)が企業福祉を行なってきた。例えば、社宅などの提供、そして企業年金制度、退職金制度で代表されるように、従業員の福祉充実を図ってきた。それは主として男子正規社員を対象にしていたという制約はあったが、少なくとも国の貧困な社会保障制度を補完する役割があった。しかも、それらが長期雇用と年功序列を基本とする安定した労使関係に貢献したことは確実であるし、日本企業の生産性向上にも寄与した。
大企業の男子正規社員というのは、全労働者の割合からすれば、ほんの一部にすぎず、女性の労働者、パートタイマー、そして中小企業で働く人の割合のほうが大きい。しかも、女性パートタイマーに代表されるように、この人たちの労働力としての役割は高まっている。大企業を含めて日本企業は、男子正社員以外の人をどう処遇するか迷っているのが現状である。もとより支払能力の低下により、労働力を低コストで得るためにその人たちを雇用している、といっても過言ではない。
しかし女性からすれば、自分も労働力として企業に貢献したいという希望が強く、しかもキャリア志向も高まっている。安易な労働力として女性を雇用するのは、企業にとっても女性にとってもマイナスの面が生じる。しかも、男女共同参画社会は時代の流れでもある。女性の活用は本人たちにも企業にとっても価値が高い。
女性には結婚・育児という壁がある。男性が育児に積極的に関与すべきであるが、わが国ではもう少し時間がかかる。理想は育児休暇制度の充実によって、女性も働きつづける方策を採用することである。それによって女性の労働力としての質を高めることができるし、企業にとってもプラスである。しかし、企業のみにファミリー・フレンドリー企業として、女性のための政策を押しつけるのであれば、企業は女性を雇用しなくなるおそれすらある。そういう企業のあることは、本書でも示された。
こういった問題を解決するためには、労働者と企業のみにまかせるのではなく、税制や社会保障制度を含めて、社会全体で取り組む必要がある。本書で明らかにされた女性の就業継続の問題を出発点にして、本格的な政策論議を期待したいものである。企業福祉は社宅や保養所、さらに退職金・企業年金の問題から、女性労働者をどう処遇するか、という問題に移りつつあり、しかも企業だけで処理できない時代になりつつあるからである。
中小企業で働く女性のことも、本書で扱っているが、いわゆるファミリー・フレンドリー企業は現在のところ、大企業に中心の話題であり、ある意味で企業規模間格差の再来である。
似たような問題は、退職金、企業年金にも発生している。確定給付型の企業年金を維持できなくなった現在、確定拠出型の企業年金の有用性を本書では明らかにしている。しかし、日本の国民は確定拠出型をうまく機能させるほどの意識なり方策を持っているかといえば、疑問は残る。しかも増加しつつあるパートタイマーは企業年金に加入できないのであり、それをどう処理するかも今後の課題である。企業年金に多くの女性が参加していないのが現状であり、男性ばかりの企業年金に頼るのでは、老後の女性にとって不安を残すだけである。
企業年金の発展は時代の要請であるが、蓄積した年金基金の運用をどうするか、といった点から出発して、コーポレート・ガバナンスの問題が重要になっている。アメリカの年金基金は企業への監視がうまくいっていて、コーポレート・ガバナンスが機能しているとされるが、わが国ではそれを今後どうすればよいのか。アメリカのコーポレート・ガバナンスはいわれているほど機能していないとの指摘も本書でなされたが、企業活性化のために望ましいコーポレート・ガバナンスを求める必要性は高い。
本書の冒頭で書かれた2つの章は、企業福祉の根源に戻って、どうあるべきかが論じられたものである。企業福祉から撤退してもよい、との主張もなされたが、その指摘は穏当ではないが、今後の議論のタタキ台として提案された。企業福祉を実践する社会保険代行機関の役割についても、選択・競争型と参加型の2つが提案されており、議論を呼ぶ話題の提供である。
女性を含め、そして労働時間を含めた働き方の多様性が求められる時代、企業が支払能力を失いつつあるわが国において、企業福祉の問題は今後大きな課題となるのは必至である。福祉の担い手として企業にその役割をどこまで求めるか、という課題においては、企業の活力を維持しかつできれば向上させる、また国民の福祉も高めるように努める、とする2つの命題を同時に解決しなければならない。容易にこの2つの命題を解決できるわけではないが、本書で得られた成果を出発点として議論が高まることと、望ましい政策措置が導入されることを期待したい。
補論
この補論は著者(橘木)の個人的意見が全面的に出たものであるし、「企業福祉の制度改革」の著者達との合意も得ていないので、別稿として独立に掲載したものである。
“企業は福祉から撤退してよい”、あるいは、“企業は福祉に関与しなくてよい”、が私の主張である。日本人の福祉レベルを上げる必要性は高いと私は判断しているが、その負担を企業に求めるものではない、というのがその根幹の主張である。
こう主張する理由をいくつか述べておこう。第1に、企業が福祉に貢献することによって、好ましい労使関係とか高い勤労意欲に期待する、といった時代でなくなりつつある。それは非法定福利厚生費においては特に著しい。
第2に、個人ないし労働者が受ける福祉サービス、例えば、年金、医療、介護といった分野では、直接のサービスの受益者は個人であるので、その負担を企業にも求めるのは、根拠がさほど明確ではない。 第3に、経済学的にいえば、社会保障給付の財源を社会保険料よりも税収に求める方が、いろいろな面から望ましい。例えば、経済成長率を高めたり、所得分配の平等を達成するには、私のいう「累進消費税」方式は、社会保険料方式よりもベターである。さらに、税方式であれば、現今問題になっている社会保険料の未納率の高さ、あるいは世代間の不公平の問題、女性に関する第三号被保険者の問題、等々を一挙に解決できる。税方式への転換は、企業と労働者の社会保険料負担をなしにする効果がある。
第4に、企業本来の目的はビジネスの繁栄と、雇用の確保である。これを達成することが、社会への最大の貢献とみなすので、企業が福祉に関してあれこれ苦悩するのであれば、福祉からの撤退があってよい。
第5に、福祉は日本国民それぞれと、公共部門との間の契約によって成立すべきものであって、中間に企業が介在しなくてもよい。この論理を貫徹しているのは、既に述べたデンマークである。デンマークほどの福祉のレベルの高さではなく、福祉のレベルは落ちるが税収が社会保障財源の中心という意味で、イギリスやカナダも私の主張に近い。
もとより私の主張には反対論が強いと予想されるが、こういう意見もあるぐらいの理解だけあれば十分である。


