序論
平成26年が始まりました。平成25年を振り返ると、富士山の世界遺産への登録、東京オリンピックの招致の決定といった心理を明るくする出来事がありました。このような一連の出来事は、日本のもつ価値を改めて認識する機会となったものと思います。平成26年においても、日本のもつ潜在的な競争力を「価値発見」を通じて顕在化させることにより、経済の活性化を図ることが有効な政策の1つであると思われます(注1)。本稿では、多くの方には、おそらく意外と思われる技術領域で、日本発の産業技術が国際的に通用するものとなっている事例を取り上げて、日本の価値発見の意義を平易に述べたいと思います。我が国発のコンピュータ言語Ruby (「ルビー」)が、近年、国際的な標準として採択・制定された事例を取り上げます。
技術の潮流
コンピュータの言語開発は、従来、英語圏が中心となって行われてきています。そのために、主要な言語の開発の中心はおおむね米国であると言って良い状況です。たとえばC言語はATTの研究所、JAVAは当時のサンマイクロシステムズといったいずれも米国の企業によって開発がなされています。英国の世界への最大の輸出品は「英語」(自然言語)であると言われることと重ねて考えれば、今日の米国の最大の輸出品は「コンピュータ言語」(人工言語)であると言って良いかもしれません。このような歴史的な経緯が、関係する技術情報の地域的な偏在を生み、米国企業や研究機関のコンピュータ技術領域での競争力の源泉の一要素となっているといって良いかと思われます。
また、C言語やJAVAといった、各種の情報システムの構築に利用されている言語は、暗黙のうちに英語文法や英単語の意味を前提として組み立てられています。このことは、プログラム言語の習得のうえで、非英語圏の学習者にとってはハードルの1つとなっていると考えられます。非英語圏の技術者にとっては、日本語のような母国語の文法知識にもとづいてプログラム可能な言語が策定されることが望ましいのですが、これまでの技術開発の蓄積を踏まえると、過去に作成され現在、実際に作動しているプログラムとの継承が図れなくなるおそれがあり、この選択はあまり現実的ではありません。
次善の発想として言語表記によらずに日本で開発されたコンピュータ言語で国際的に標準化されていたものがあれば、多少なりとも日本のこの技術領域における優位性が高まると期待できます。この問いに対しては、「そのようなものがあるのか?」といった疑問がまず思い浮かぶことと思いますが、幸いなことに日本人により開発が行われたコンピュータ言語としてRuby(「ルビー」)があります。今日、Rubyは、Webのシステム構築言語として普及が進んでいるコンピュータ言語です。Rubyは日本のJIS規格に2011年に制定されたのち、情報処理推進機構(IPA)が中心となって、国際標準化提案を進め、2012年にISO規格として制定されています[1][2]。昨年の12月には、一連の標準化作業の完了が公表されました[3]。また、教育面でも国内の大学で情報教育の教養レベル科目として教授されるなど裾野の広がりを見せています(注2)。
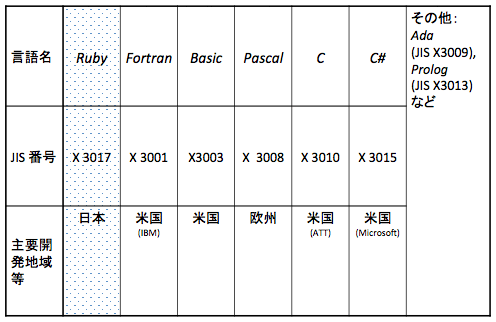
基盤的な技術の中でも、プログラミング言語は、当該プログラミング言語が利用されたシステムが採択されると、数年間はその言語が利用されつづけること、またその間に保守、アップデート業務のために、人的な需要が発生するなど、産業振興面での影響は大きいと期待できます。また、先端技術分野の技術を標準化する際には、技術標準の策定による技術の公開と、技術標準の策定を行わない技術の秘匿のバランスを考慮してビジネスモデルの構築を行う必要がありますが、プログラミング言語の場合には、言語仕様自体を公開することは、このような点を考慮する必要がありません。さらに、日本発である場合には、技術的な進展に伴う言語のバージョン更新において日本の産業界の要望が反映されやすいと期待できます。
結語
本稿では、日本の価値を発見し世界的に広めるとの視点から、意外とも思われる先端技術分野で日本人開発者の成果が、日本の主導で国際的な標準とされた事例を取り上げました。こういった、技術的な優位をもつ日本発の技術は、よく見てみると、まだまだそこかしこにあるのではないのでしょうか。取り上げたような事例は日本の産業および学術面での振興を図るうえで、有意義であると考察されます。昨年に続き本年においても、日本の社会・文化的な価値観や技術のもつ価値が積極的に発見されたり、再評価されることを通じて、社会、経済の活性化につながることを期待したいと思います。


