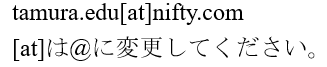1. はじめに
新年を迎えるに当たり、昨年から続いている世界的な紛争がどうなるかは、多くの人々にとって関心事であると思う。地域的な紛争が限定的なものであっても、経済活動において重要な物資や資源が当該地域に集中している場合、紛争当事国でなくても、サプライチェーンへの影響が生じる場合は、経済面に及ぼす影響は大きい。このような影響に対して、標準化がどのような効果を持つかについて概観したい。標準には、大別してデジュール標準とデファクト標準という2つの概念がある。両者が経済に与える意味は異なる。デジュール標準は、公的に定められる複数の関係者間で取り決められる物品の形状などの仕様に関する合意である。一方、デファクト標準は、市場競争の結果として形成される、言い換えればある時点で最も支配的な仕様である。経済への影響を考える際、両者の意味は異なってくる。経済安全保障における考慮要因としては、サプライチェーンの確保や、技術情報の流出管理といった点が挙げられる。
日本における標準化活動の状況に関する調査がある[1]。2019年から2021年までの5年間にわたり、主要指標を時系列でまとめたものである。この間に標準化活動の進展が観察されている。2019年から2021年は、新型コロナ感染症による外的なショックにより、社会生活におけるデジタル化が加速した時期と考えられる。
デジタル化は、アナログ情報である映像や音声を0と1に変換し、この二値化したデータを一定のルールに基づいて、符号化し、また復元するプロセスであるため、符号化と復号化の両手法の共通化が必須である。このことから今日におけるデジタル化は、社会実装において標準化と同義と解釈できる。このような標準化の進展が、経済安全保障の観点からどのような意味を持つのかについて考察したい。
2. 標準と標準化過程
(1)物流分野
標準化は物流の促進に大きな役割を果たしている。例えば、鉄道では国や地域によって線路幅が異なると、車両を変えないと国境を越えて走行することができない。列車が国境を越えて運行するためには、線路の規格を共通化するだけでなく、信号システムや車両の安全性評価の共通化が必要である。また、輸送に使用するコンテナのサイズや形状が一定であることは、積み替え作業を効率化し、鉄道でのコンテナ輸送を可能にしている。コンテナの形状が共通化されているため、海上輸送でもコンテナ船に積載することができ、陸路と海上を統合する輸送システムが実現している。このように、技術的な標準化は、効率的な経済活動において重要な役割を果たしている。コンテナの形状に関するルールはデジュール標準である[2]。
経済安全保障に直接的に影響を与える事例として、国際的な紛争によって輸送システムが遮断されたり、特定地域で算出される物資が輸出規制されたりする場合が挙げられる。技術の標準は、輸送システムの共通化において主要な役割を果たしており、代替的な輸送手段の確保の円滑化等を通じて、経済安全保障の強化に寄与している。
(2)製品分野
製品技術や生産方法の標準化は、代替品や代替的な生産手段の利用を可能にし、特定地域に依存するリスクを低減できるため、経済安全保障を高める有効な手段となる。製品の形状が規格化され、需要側がその規格の製品のみを利用する場合、標準に関する情報が公開されていれば、同じ規格の製品を生産して市場に参入することができるため、供給者が複数存在することが期待される。
しかし、製品が特定の企業からしか供給されない独占状態になると、技術の標準化が過度に進み、経済安全保障に大きな影響を与える可能性がある。これは企業間や国家間の両方に当てはまる。市場が独占状態にあり特定の供給元以外から代替品を調達することが困難である場合、供給の多様化が難しくなる。これはデファクト標準に該当する。
(3)知識情報
技術の標準は、知識としての情報的な意味を持つ。デジュール標準の制定過程では、関係者間での情報交換が行われ、知識の拡散が伴う[3]。ある参加者にとっては知識を獲得する機会となるが、同時に知識が流出するリスクもある。特に情報通信分野では、デジュール標準の制定が新しい技術の社会実装において必須であるため、標準の制定プロセスにおける知識流出に注意を払うことが重要である。いったん拡散した知識情報は回収できないため、経済安全保障の観点から、この点に十分留意し、とりわけ交渉過程における知識情報の流出に留意する必要がある[4]。
3. まとめ
標準の知識情報としての役割を、経済安全保障の観点から国際的な環境変化を踏まえて概観した。サプライチェーン確保の観点では、デジュール標準の制定は調達の多様性を確保し、経済安全保障の強化に寄与する。一方で、過度な市場独占(供給元独占)が進みデファクト標準となると、サプライチェーンの柔軟性を低下させる恐れがある。また、標準化プロセスにおける情報交換に注意を払うべきである点について言及した。標準策定過程の会合などデジュール標準の形成過程において、関連する技術情報の管理に注意を払う必要がある。
謝辞
本コラムに関する研究は、JSPS科研費(15K03718,19K01827,及び23K01529:研究代表者 田村 傑)の助成を受けて実施しています。