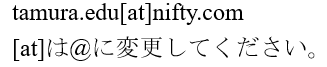1. はじめに
秋分を過ぎ、夜が長い秋から冬になると、街中ではイルミネーションによる飾りつけが楽しめる季節となる。光は社会生活の基本となる要素であり、装飾的な利用だけでなく、産業などの用途にも広く利用されている。本稿では、日常をとりまく事象に関する標準についての理解を深めることを目的として、3D空中表現を中心に光に関する標準を取り上げ、その特徴や今後の役割について概観する。
技術標準は、ルールメイキングの一つとして、新製品開発といったイノベーション政策のみならず、産業政策・通商政策においても重要なツールと考えられている。標準は、役割が多様であるがゆえにわかりづらい概念である。そのため、理解を助けるためには、機能面に着目したカテゴリー分類に基づく説明が有用である。本稿では、このカテゴリー分類に基づく説明を踏まえつつ、光に関する標準を取り上げることで、その特徴についての理解を深めたい。
2. 背景
標準を機能に基づいて分類するときには、製品、計測、基本用語といった視点で区別することができる[1]。製品標準は、ものの形状を規定する規格であり、例としては「ねじ」などの形状が挙げられる。計測規格は、製品の性能をどのような前提条件で計測するかを規定するものであり、その条件によって結果が大きく変わるため、計測方法を標準化する際には、まず「何を目的として計測するか」という合意が重要となる。
計測標準の役割がとりわけ重要となるのは、インクリメンタル(漸進的)なイノベーションよりも、ディスラプティブ(破壊的)なイノベーションの場合である。既存技術を基盤とする場合には、すでに性能比較の方法が確立されていることが多いが、新しい技術を用いる製品の場合は、性能評価の基準がなく、市場でのマーケティングが難しいためである。消費者保護の観点からは、製品が消費者の求める品質を有していることを示すことが重要であり、性能の計測方法を定める規格は大きな役割を果たす。また、異なる製品間で性能を比較するためには、同じ計測方法に基づく比較が必要であり、これは企業間の公正な競争を促す効果も期待できる。
基本用語の規格は、新しい技術概念がイノベーションによってもたらされた際に必要となる。新たな学術的発見にともない、同じ用語が多様な文脈で使われることがあるため、用語の用法や意味を統一することが重要である。 このように、標準は対象となる機能に着目して分類されることが多い。この分類方法は技術分野を横断しており、特定の技術分野の動向と組み合わせて理解することで、対象に関する標準の役割を把握しやすくなる。
3. 光に関する標準
光に関する標準は、光速度がさまざまな物理法則の基本定数であることを考えると、その多様な役割を理解できる。光は情報を伝達する媒体であり、電磁波のうち人間が視認できる領域のものを指す。
ハードウエアの分野では、ファイバーオプティクス、レーザー安全性、光ディスクなどの分野で製品標準が制定されている[2]。これらの関連ハードウエアに加えて、光の利用は今日ではエンターテインメントビジネスにおける装飾用途やコンテンツビジネスにも広がっている。このような領域における標準を含めて、色を伝えるための標準は製品デザインなどの分野における製造過程等で重要な役割を担う。
日本産業規格(JIS)では、赤・青・黄の光の三原色以外に、文学的表現などに利用されうる多様な色の呼び名を定めている[3]。このような色に関する標準は、工芸や芸術の領域でも用いられる。このように光に関する標準は形状・計測に加えて視覚的要素も含むため、その対象範囲は意外に広い。
4. 今後の期待
物体をどのように表示するかについては、2次元の白黒表示から2次元の多色表示へと進化するにつれて、製品やデザインへの応用範囲が広がってきた。情報通信技術の発展により大量のデータ処理が可能となったことで、多色による3次元表示に関する研究や標準策定も進んでいる[4-6]。
視聴用のゴーグルを必要とする方式と不要な方式があるが、ゴーグル不要型はより汎用(はんよう)的な利用が可能である。たとえば、芸術の分野では、日本の伝統芸術である能と3D空中表現を融合させた新しい表現方法の試みも進められている[7]。
2次元表現では困難だった没入感を実現することで、映像表現の多様化や新たなコンテンツ・メディア産業の創出につながることが期待される。また、新たな表示技術は、新たな仮説の探索や形成を通じて研究開発やイノベーションを促進する効果もあり、今後の研究への貢献も期待できる[8]。
5. 結語
光は、人間の視覚や認識に深く関わる存在である。製品製造に関する規格だけでなく、日常生活に影響を与える「色」に関する規格も制定されている。光に関する標準は、知識情報や芸術表現の社会実装という観点からも重要であり、芸術を含む理科教育、すなわちSTEAM教育の観点からも注視すべき分野である。特に、3次元立体表示のような新しい表現技術が社会に浸透するためには、さまざまなデータが多様な機器で立体的に表示できるようになることが必要となる。このためには、標準化の役割は大きい。光を利用する新たな表現技術は、製品設計のみならず、芸術表現や作品創造の面で先端領域を開拓し、社会変革を切り開く可能性がある。
謝辞
本コラムに関する研究は、JSPS科研費(23K01529:研究代表者 田村 傑)の助成を受けて実施しています。宇都宮大学 工学部 オプティクスセンター 山本 裕紹 卓越教授に、空中立体表示に関する国際標準化の動向について情報提供をいただきました。
連絡先