千年に一度と言われる未曾有の大震災を体験して、被災地以外の企業においても、多くの企業がサプライチェーンの構造を把握する重要性を再認識したであろう。平時においては、取引先の取引先、さらなる取引先を意識した経営戦略を立てることは少ないであろう。日本の産業の競争力は、取引先とのつながりの強さに依存すると考えられてきたが、このような競争力は、震災のように、つながりを断つ現象に対して、脆弱であると考えられる。より安定的な取引ネットワークを構築させるための長期的な対策を考えるべき時である。
震災被害の大きさ
被災地の企業においては、設備の崩壊などにより、物理的に生産活動を行えない企業が多いと考えられる。東京商工リサーチ(TSR)では、「東日本大震災」関連調査(注1)として、青森県、岩手県、宮城県、福島県の太平洋沿岸の44市区町村を被災地と定義し、震災被害の大きさとして、被災地の企業の数や売上規模、従業員規模を分析している。この分析によると、被災地の企業数は3万2341社、従業員総数は36万3796人であるとしている。しかし、震災被害の大きさを測定するには、被災地の企業のみでなく、被災地以外の企業への影響も考慮することが必要である。
たとえば、被災地以外の地域においても、仕入先の企業が被災地にある場合、その仕入先企業が生産活動を行えなくなれば、他の仕入先を見つける必要がある。仕入製品が特殊な技術を要するなど、仕入先企業を他企業に代替不可能な場合には、生産活動を行うことが出来ず、致命的な被害を受けることとなる。また、販売先の企業が被災地にある場合には、新たな販売先を開拓しなければならないだろう。
被災地の取引先を持つために、震災の被害を受ける企業は被災地以外にも多く存在すると考えられる。さらに、取引先の取引先が被災地にあるなど、企業自身が認識していないうちに、震災の被害を受けること可能性も考えられる。
サプライチェーンの構造
企業間の取引関係を通じて、地域を超えた震災被害の大きさを分析する上で重要な視点は、企業間の取引ネットワークの構造にある。ネットワーク構造の違いによって、被害を受ける企業の割合は大きく異なってくるからである。
たとえば、「世界中の誰もが6次のリンクでつながっている」と言われるように、社会学では、スモールワールドネットワークの構造がよく知られている。このような構造が、企業間の取引ネットワークに確認されるとすれば、被災地以外の地域においても、企業が認識しないうちに、サプライチェーンを通じ、震災の被害を受ける企業が非常に多く存在することを示唆している。
企業間の取引関係を把握するためには、企業レベルでの取引関係データが必要となる。TSRの大規模な取引関係データには、約80万社の企業について、約400万の取引関係を収録している。このデータを用いて、Saito, Watanabe and Iwamura (2007)では、企業間の取引関係のネットワークが、スケールフリーネットワークという構造を持ち、多くの取引関係のシェアを占める少数の企業「ハブ企業」が存在することを示し、Ohnishi, Takayasu and Takayasu (2010)では、スモールワールドネットワークの構造を持つことを示している。
被災地以外の企業への影響
企業間の取引ネットワークがスモールワールドの構造を持つことは、サプライチェーンを通じて、被災地以外の地域においても、震災の被害を受ける企業が非常に多く存在することを示唆している。では、それらの企業は、どのような地理的な広がりを持っているのだろうか。下図は、被災地企業(赤点)と被災地企業の取引先企業(青点)の地理的な広がりを示している。0次の企業は被災地企業、1次の企業は被災地企業の取引先企業である。
既存研究では、個々の企業から取引先企業までの距離は、半数が40km以内、9割が400km以内にあり、企業間の距離は非常に短いことが実証的に示されている(Nakajima, Saito and Uesugi (2012))が、下図では、被災地企業の取引先企業は地理的に広く分布していることが確認された。ただし、後述のように、企業の割合からみると、既存研究から示唆されるように、被災地企業の取引先企業の割合は、非常に少ないことが確認されている。
下表は、被災地企業、被災地企業の取引先企業、取引先の取引先企業(2次の企業)などの企業全体に占める割合を地域別に示している。前述のように、被災地企業の取引先企業の割合は非常に少なく、北海道地方で2.3%、関東地方で2.7%、中部地方で1.1%、中国・四国地方や九州地方で0.5%以下であるが、被災地企業の取引先の取引先企業まで含めると、北海道地方で60%、関東地方で58%、中部地方で53%、中国・四国地方や九州地方で40%以上となり、多くの企業が関係してくることが分かる。さらなる取引先の企業(3次の企業)まで含めると、すべての地域で9割近くなり、ほとんどの企業が何らかの関係を持つことが分かる。
以上の分析結果から、被災地以外の企業においても、企業自身が認識しないうちに、大多数の企業が取引関係から何らかの影響を受ける可能性があることが分かる。個々の企業の影響の大きさは、代替不可能な仕入先であるのか、販売の多くを1つの企業に依存しているのかなど、企業間のつながりの強さによって決まってくる。従来、日本の産業の競争力は、取引先とのつながりの強さに依存すると考えられてきたが、このような競争力は、震災のようなつながりを断つ現象に対して、脆弱であろう。
東海大地震も遠くない未来におこると考えられている。震災に対する脆弱性は、小さな世界である取引ネットワーク構造、取引先との強いつながりに依存している。より安定的な取引ネットワークを構築させるために、異なる地域に取引先を持つなど、リスクを分散させるための長期的な対策を考えるべきである。
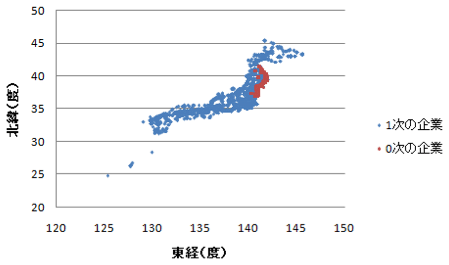
| 0次 | 1次まで | 2次まで | 3次まで | 4次まで | 5次まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 1.8% | 5.1% | 56.7% | 90.5% | 96.0% | 96.5% |
| 北海道 | 0.0% | 2.3% | 60.2% | 95.8% | 98.7% | 98.8% |
| 東北 | 16.6% | 33.6% | 82.0% | 96.7% | 98.4% | 98.5% |
| 関東 | 0.0% | 2.7% | 58.2% | 89.5% | 94.5% | 95.1% |
| 中部 | 0.0% | 1.1% | 53.1% | 89.1% | 95.7% | 96.4% |
| 中国・四国 | 0.0% | 0.5% | 47.2% | 90.1% | 96.7% | 97.2% |
| 九州 | 0.0% | 0.3% | 42.8% | 88.3% | 96.6% | 97.4% |


