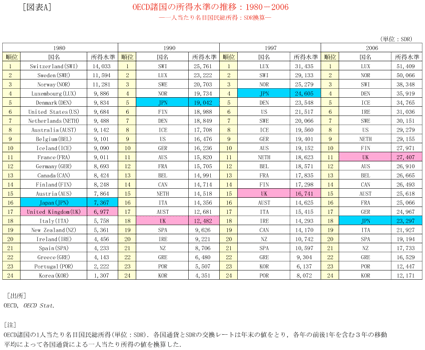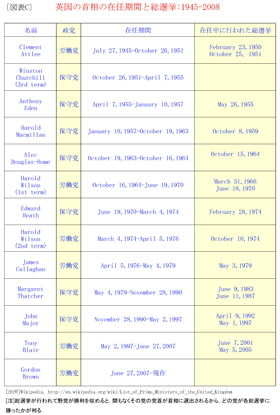OECD 諸国の「所得水準の推移」から驚かされたこと
前回の私の「経済問題:WHY?」のコラム(2007年12月18日付)から今回まで、かなり時間が経ってしまい、申し訳ない。それで前回の復習のようなことから始めさせて頂く。前回、私は、1993年~2005年の12年間にOECD 24カ国の「所得水準」(正確に言えば、国民一人当たりの名目国民所得または実質国民所得)がどのように変化したかを計算した二つの簡単な統計表[表A]、[表B]を示し、それらから読みとれることで、私が驚いたことを三つ挙げた。一つ目は1990年から2006年にかけて、アイルランド、ルクセンブルク、ノルウェイ、アイスランド、デンマーク、オランダ、フィンランド等、西欧・北欧の諸国、ことに「小国」(注1)が経済的に大いに栄えていることである。二つ目は英国の経済的躍進、あるいは繁栄。三つ目は、欧州大陸の三大国、すなわちドイツ、フランス、イタリアの経済的不振である。
本稿の[図表A]、[図表B]は、前回の[表A]、[表B]の両表を若干改訂し、再掲したものである。[図表A]は前回の[表A]の対象年次を、前の方は1980年、後の方は2006年まで延ばしたもので、為替レートで換算したOECD24カ国の国民一人当たりの名目国民所得の推移を示している。ただし各国通貨表示の値を為替レートで換算するのに、多くの場合米ドルが使われるが、為替レートの気まぐれな変動の影響を多少とも少なくするために、ここでは米ドルではなくSDR(米ドル・ユーロ・日本円・英ポンドの加重平均)を使い、かつ各年次の前後3年の為替レートの移動平均を求め、そのレートで換算した。また、[図表B]は前回の[表B]の改訂版であり、各国の「一人当たりの名目国民総所得」(SDR換算)と同じく各国の国民経済計算上の「一人当たり実質国民総所得」が、1980-1990年、1990-2006年の間にそれぞれ何倍になったかを示している。
「経済問題:WHY?」のコラムの第1回が昨年(2007年)12月18日にこのホームページに掲載されてから間もなく、12月26日に2006年の日本の国民経済計算が内閣府から発表され、国民一人当たりのGDPが前年のOECD加盟国中15位から18位に下がったこと、世界のGDPの中での日本のシェアが24年ぶりに10%を割ったことが報道された。そしてその後、その2006年分のOECD統計に基づいて、大田弘子経済財政担当相が2008年1月18日に国会の「経済演説」の中で、「日本はもはや『経済は一流』と呼ばれる状況にない」と述べ、日本の経済的後退が国会はじめ方々で取り上げられた。
私が気付いた関連の記事や論説は、『週刊東洋経済』(特集「北欧はここまでやる」)2008年1月12日号、岩本康志「『経済一流でない』の真実」『日本経済新聞』(同2月4日付)、大田経済相、「危機感バネに改革一段と」(同2月8日付)、『エコノミスト』2月26日号、特集「没落する日本」、鈴木淑夫『円と日本経済の実力』岩波ブックレット No.719, 2008年3月、等である。他方、英国について、私の上記RIETIのHPでの記事以前に、昨年夏『週刊東洋経済』(7月28日号)が「日本と英国:なぜイギリスはニッポンより豊かになったのか」という「特集」を掲載したことを知った(注2)。
「英国の経済的躍進」の統計
さて、今回から数回にわたる“経済問題:Why?”のテーマは、「英国の経済的躍進」である。再び前回の復習のようなことで恐縮だが、まず、「英国の経済的躍進」を、統計データから確認することから始めよう。英国は、[図表A]の名目所得水準(国民一人当たりの所得、SDR為替レートによる換算)の国際比較において、1980年の17位、あるいは1990年の18位から、2006年には11位に上がった([図表A]の第一列、第二列、第四列を参照)。駅伝やマラソンなどの言葉を使えば、1990-2006年の16年間に、英国は日本、欧州大陸の三大国(ドイツ、フランス、イタリア)、カナダ・オーストラリア・オーストリア・ベルギー等の諸国を“牛蒡抜き”にして、一躍、上位に進出した。
また[図表B]では、その第二列の、1990年-2006年の16年間の「一人当たり名目国民所得」の「増加率」と、同じく第四列の「一人当たり実質国民所得」の同期間の「増加率」で、英国は24カ国中いずれも第7位である。この[図表B]の第二列、第四列で、英国より上位にある国で、英国よりも人口の多い国は一つも無い。[図表A][図表B]から、1990年以降、英国が経済的に繁栄してきたことが、ハッキリ読み取れる。
どうしてそのようなことが英国で起こったのだろうか? また日本の所得水準は、今の18位から嘗ての4位(1997年)や5位に(1990年、以上、[図表A]を参照)、どうしたら戻ることが出来るだろうか?
この私の問いに対して、英国の所得水準の上昇はポンドの為替レートの動きによるところが大きいのではないか、とコメントした人が少なくなかった。しかし為替レートの変化は主な答ではあり得ない、と私は思う。何故かというと、英国は、[図表B]の第四列(「一人当たり実質国民所得の増加率」の、②1990-2006年の列、この数値は為替レートの変化からあまり影響を受けない)でも、OECD 24カ国中の第7位と大いに健闘しているからである。[図表B]の第四列で英国よりも上位にある六ヶ国のうち、韓国とギリシャは、実質所得の増加率では高かったが、その所得水準はOECDの中で最も低い、“latecomers”である([図表A]の第四列、2006年の両国の所得水準を参照:24カ国中、22位と24位である)。
英国民の「実質所得水準」は1990年-2006年の16年間に1.46倍になった、つまりほぼ5割増えたのである。日本の実質所得水準はその半分以下の21%しか増えていない。その16年間の実質所得水準の増加率が英国よりも高い国のうち([図表B]の第四列を参照)、上記のlate-comerの韓国を除くと、いずれも人口規模が小さい、いわば身軽な国であって、豪州(2007年の人口約2000万)以外は人口約1000万以下の国である。また2006年に、人口規模が英国と同程度以上の大国で「一人当たり名目国民所得」の水準が英国よりも高い国は、米国だけである([図表A]の第四列を参照)。
このような英国の「経済的躍進」、あるいは「繁栄」は如何にして達成されたのか?
日英の首相の在任期間の大差
「最近の英国の『経済的繁栄』は如何にして達成されたのか?」という問いへの答えを私が模索しはじめて、先ずビックリしたのは、最近の英国の首相在任期間の長さである。それは日本と比べた時に一驚に値する。英国では1979年5月の総選挙で労働党が敗れ、首相がそれまでの労働党のJ.キャラハン(James Callaghan)から保守党のM.サッチャー(Margaret Thatcher)に交代した(以下について、[図表C]を参照)。その1979年の総選挙から1992年4月の総選挙まで保守党が四連勝し、サッチャー首相の11年半、次いで同じく保守党のJ.メイジャー(John Major)首相の6年半と、保守党政権が18年続いた。1997年5月の総選挙で、22年半ぶりに労働党が勝利を収め、同党に政権が移ってT.ブレア(Anthony Blair)が首相の座に就いた。その1997年5月の総選挙から2005年5月の総選挙まで、労働党が3連勝した。ブレアは10年間首相を務めて2007年6月に、現首相G. ブラウン(Gordon Brown)に党首・首相の座を譲って引退し、1997年から現在まで11年以上、労働党政権が続いている(注3)。
1979年5月から2007年6月までの28年1カ月の間に、英国ではサッチャー、メイジャー、ブレアの、僅か3人の首相が国政の舵をとってきた。そして、この3人の首相の合計28年の在任期間中に、英国の経済社会は大きな変革を遂げ、繁栄に向かったのである。私は、英国経済が蘇り、大いに繁栄したことについて、マーガレット・サッチャーとトニー・ブレアの2人の偉大な宰相の貢献は非常に大きい、と感服している。
日本では、英国で3人の首相が政権を担当したのと同じ28年の間に、首相の地位に就いた人は何人だったか? この私の問いに対して、日本の政治にそれほど詳しくない人々の多くは、「多分、倍以上の7,8人か10人位ではないか」と答えた。正解は15人である。同じ28年間に日本の首相を務めた人は、英国の首相の人数の実に5倍に達する(注4)。言い換えれば、日本の首相の平均在任期間は英国の首相の平均在任期間の僅か五分の一に過ぎないのである。この日英の首相在任期間の大差、つまり日本では首相の在任期間が甚だ短く、首相が頻繁に交代してきたことは、日本の政治と経済が混迷を続けてきたことの重要な原因の一つであり、またその結果でもあるのではないか?
日英米の中央銀行総裁の在任期間にも大差がある
日英の首相の在任期間の大差だけではなく、中央銀行総裁についても、日本と英国・米国との間に在任期間の大きな差が認められる。最近のほとんどの日銀総裁の在任期間は5年あるいは5年未満であるが、英国の中央銀行である Bank of England の最近の総裁10人の平均在任期間はその2倍の10年である。また、他の主要国の中央銀行総裁に相当する米国のFRB(米連邦準備制度)議長の場合、暫く前に退任したAlan Greenspan は18年5カ月にわたって在任した。第二次大戦後に、任命されたFed議長のうち2人目のWilliam M. Martin(1951年に就任)は、Greenspan よりもさらに長く、18年10カ月在任した。これら2人を含めて、また僅か1年5カ月の在任で財務長官に転出したGeorge W. Millerも含めて、Greenspanまでの5人のFed議長(第9代から第13代まで)の平均在任期間はほぼ12年である(注4)。
英国・米国以外の先進諸国では、首相・中央銀行総裁の平均在任期間はどうなのだろうか。私はまだ調べていないが、民主主義の伝統の長い先進諸国…ということは旧ソ連圏を除く欧州とカナダ…では、日本のように首相在任の平均期間が短い例はあまりなさそうである。イタリアでは日本と同様にしばしば政情が不安定で、首相の在任期間は日本より僅かに長い程度である。しかしイタリアの中央銀行総裁については、私がOECD の「インフレなき成長」のための専門家研究グループ(通称 McCracken Group, 1975-1977)で同僚だった Guido Carli はイタリア中央銀行総裁を15年にわたって務め、その後3年間財務大臣を務めた。
なぜ日本の首相の在任期間は短いのか ─ 政治問題:WHY?
日本の首相が頻繁に交替し、在任期間が甚だ短いのは何故なのだろうか。“Why?”と問いたいことである。日本語の「政治学」に対応する英語の言葉(訳語)として、最近では“political science”が使われることが多いが(それ以外では、political studies あるいは Government だろうか)、政治学が“science”(social science)の一分野であるとすれば、一見簡単に説明できない現象に対して、実験または観察からの「帰納」により、出来るだけ単純でかつ尤もと思われる答えを探らなければならないだろう。
この、「政治問題:WHY?」の答は、私にはまだ良く分かっておらず、読者諸賢のご教示を頂きたい。この問いに「真っ当に」答えるためには、英国のみならず、民主主義の伝統の長い他の国々についても調べる必要があり、また日英比較に限定しても、選挙制度と選挙の実態についても詳しく知る必要がある。
ただ、日本の首相の頻繁な交替の背景として、二つのことが大いに関わりがあるように、私には思われる。一つは、日本社会(あるいは日本を含む儒教文化圏)に根強い「年功序列」の観念である。日本では「長幼序有り」の観念と慣行が根強くあるので、大きな組織のトップのポストについて、「次は、あるいは次の次には、自分に順番が廻ってきて、就任できるかもしれない」という期待が広がり易いのではないか。そして在職者の交替を期待する力、またその再任を阻止しようとする力が働き易いのではないか。
もう一つの背景として、日本の首相ポストの場合、日本の保守系政党の独特のシステムである政党内の「派閥」の存在が、日本の首相の在任期間が甚だ短いことに関係があるのではなかろうか。党内の「派閥」は他の先進諸国には例の無い、日本独特のシステムである、と私は思う。英国、米国にも、労働党左派とか、ネオコンといった政治家のグループがあるが、日本の派閥は、そのような、政治上の主義・主張の近い人々の集まりではない。自民党の「派閥」は「政策集団」であると説明されることがあるが、私にはそのような解釈は納得できない。自民党の「○○派」と「△△派」とは、政治上の主義・主張・信条、具体的な外交・防衛・経済社会政策に関して、どのような違いがあるのか、と外国人に訊かれたら、私はまったく答えることが出来ないし、○○派・△△派所属の党員自身も、ほとんどの場合、答えることが出来ないのではないか。
簡単に言えば、政治家を志した若者が政治の世界で出世してゆく過程で、ある「派閥」の「領袖」(親分、おやじ)に「世話になった」人々、あるいは「面倒を見てもらった」人々は、その「領袖」の派閥に所属することになるようである。そしてこの「面倒」の中にはしばしば金銭に関することも含まれる。日本では選挙に当選するためには、選挙時も普段の政治活動にも「カネ」がかかり、ことに「駆け出し」の時には政治資金が乏しい。
さらにいわゆる「革新政党」がすっかり弱体化してしまった最近では、一つの党の中に複数の「派閥」があるというに止まらず、自民党・民主党という大きな「政党」自体が政治上の主義・主張を同じくする(あるいは主義・主張が近い)政治家の集まりであるという、政党の本来の在り方から遠ざかってしまった感がある。というのは、民主党の小沢一郎党首はじめ同党の何人かのリーダーは、ともかくも「政権交代」が同党にとっての最重要な目標だということを繰り返し強調してきた。そうして最近の新党首の選出に当たって、新党首をリーダーとする民主党が政権に就けばどのような政策を行なうのかをあまり議論せずに、無投票で小沢氏を新党首に決めてしまったのである。「政策の議論よりも総裁・総理の交代を」というのは、自民党のお家芸だったのではなかろうか。
「派閥」とか「世話」とか「面倒」といった日本語は英語に翻訳することが難しい。それらの言葉がどういうことを意味するのかは、日本語で説明することさえ、たとえば高校生には、あるいは大学生でも、難しいのではなかろうか。しかし日本の政治家も、政治家に投票する一般の日本人も、それらの言葉が表している観念と行動原理に多かれ少なかれ支配されているのだから、それらのことの内容・実態を理解しないと、日本の政治は理解できないだろう。
日本の保守系の首相(総裁)は特定の派閥に所属しており、自らの所属する派閥といくつかの派閥は熱心に支持していても、他のいくつかの派閥は必ずしもそれほど熱心には支持していないことが多い。日本の保守党の首相は、このような複数の派閥の力関係の、それほど安定的ではない均衡の上に乗っかっているのである。政権政党の人気が低下すれば、首相所属の派閥、および首相に近しい「領袖」の派閥(したがって閣僚の配分その他で党内で優遇されてきた派閥)以外の諸派閥、ことに次の首相を送り出す可能性のある派閥からは、首相交代を望む声が高まってくる。そのような力関係のバランスが、首相支持の派閥に不利な方向に傾けば、首相は遅かれ早かれ退陣せざるを得ない。自民党の総裁・首相は、何時、党内の少数派になるか、「一寸先は闇」と言っても、それほど過言ではないのである。このような事情から、日本の首相の在任期間は短くならざるを得ないのではないか。
このようなことから、日本では国の政治のリーダーに相応しい人物を年齢の先後に関わらずに選び、そのような人物が長期間にわたって優れたリーダーシップを発揮するということが難しく、稀なのではなかろうか。
以上は「政治学」については素人である私のカジュアルなコメントに過ぎない。私が提起した「政治問題:WHY?」の質問に対して、読者諸賢、ことに“political science”に造詣の深い方々にご教示を賜りたい。
もともと、「英国の経済的繁栄」について記す心算で本稿を書き始めたのだが、先ず日英の首相在任期間に大差があることに驚かされ、しかも折しも日本の首相が頻繁に交代するという現実に直面したので、そのことに関連する記述が長くなってしまった。次回以降は、マーガレット・サッチャーが首相に就任してから、英国の経済社会を長年の停滞…「英国病」!…から蘇生に向かわせるためにとった“drastic”な諸政策について述べたい。また英国で政権が保守党から労働党に変わったあと、トニー・ブレアが「サッチャー改革」の成果を継承して、サッチャー以前に逆戻りさせることなく、自らは「センターの左の」民主社会主義者だと宣言して、教育・医療等の分野で民主社会主義者に相応しい政策を実施し、英国経済の繁栄をさらに前進させたことも述べたい。