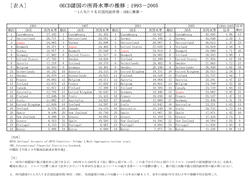OECD諸国の所得水準の国際比較
まず[表A]を見て頂きたい。この表は、1993年から2005年までの12年間について、OECD24カ国の「所得水準」を4年おきに為替レートで換算して国際的に比較した「所得水準の国際比較」の表である。「所得水準の国際比較」というときの、「所得」とは何かという問いは簡単には答えられないが、この表は、各国の国民一人当たりの1年間の所得、もう少し正確に言うと「一人当たりの名目国民総所得」を4年おきに市場為替レートで換算して比較したものである。この表は各国の「所得水準」、各国の平均的な一人の国民が、1年間に得る所得(名目値)の大きさの、上記12年にわたる推移を概観するために作成したものである。
この種の「国民一人当たりの所得」の国際比較には、共通の「価値基準」が必要である。国際比較のための価値基準の候補者としては、(1)米ドル、(2)SDR、 (3)購買力平価(purchasing power parity, PPP)の三つが考えられる。これらのうち、(3)の各国通貨のPPP に関する統計を私はあまり信用しない(まったく無意味だとは思わないが)。私が若かりし日に初めて国際的な academic journal に掲載してもらった論文は、円と米ドルの購買力平価を計算したものであった(Weltwirtschaftliches Archiv, 81-1, 1958, 渡部経彦氏と共著、英文)。その時のPPPの計算に大いに苦労し、多大な時間を費やした経験から、生活習慣や地理的条件等が異なる国々の間で意味のある PPP を求めることは不可能に近い、と私は考えてきた。そこで(1)か(2)かを価値基準として使うとことにすると、そのためには、各国通貨で表示された「所得水準」の数値を、市場為替レートにより米ドルの値、あるいはSDRの値に換算することになる。
SDRは、多くの人にとって耳慣れない言葉かと思うが、米ドル・ユーロ・日本円・英ポンドの四つの主要国際通貨の加重平均値であり、国際通貨基金(International Monetary Fund)が発表している。市場為替レートはさまざまな要因により気まぐれに変動するが、各国通貨の対米ドル・レートよりは、対SDRレートの方が気まぐれな変動の影響が幾分か少ないと考えられる。なお、[表A]では、やはり気まぐれな変動の影響を少なくするために、各年(年末)についてその年とその前後の年の、3年間の移動平均値を使った。
次に、[表B]は、1993-2005の12年間に、各国の所得水準が何倍になったかを示し、併せてその倍率の順位も示した。これについては、三通りの指標を示した。(1)と(2)は、各国の一人当たり国民所得を対SDR為替レート、対米ドル為替レートで換算し、SDRあるいは米ドルで表わした各国の一人当たり国民所得が12年間に何倍になったかを示したものである。この「倍率」の値は、当然、物価上昇分も含んでいる。米ドルの場合、[表B]の[注記]に書いたように、米国の消費者物価指数は12年間に約35%, GDPデフレーターは約28%上昇している。(1)と(2)の各国の所得水準の増加率にも、その様な物価上昇分が含まれている。
これに対して、[表B]の(3)は、各国毎の「一人当たり実質国民所得」の統計から、それが12年間にどれだけ上昇したかを求めたものであり、(1)と(2)に含まれる物価上昇分を含んでいない。また、(1)と(2)は市場為替レートの気まぐれな変動の影響を受けるが、(3)はそのような影響を直接には受けない(間接的には、輸入品の値上がり、値下がり等を通じて影響を受けるが)。
西欧・北欧小国の躍進
さて、このOECD諸国の所得水準の推移の統計表[表A]、[表B]を見て、私が驚かされたことが三つある。第一は、多くの西北欧州の諸国、ことに西欧・北欧の「小国」の経済的躍進である。すなわち[表B]の上位の国、アイルランド、アイスランド、ノルウェイ、フィンランドでは、上記の12年間に、SDRあるいは米ドルで測った「所得水準」が「倍増」、あるいは2倍以上に増加しており、「所得倍増」が達成されている。スペインとポルトガルでも、所得水準はほぼ倍増している。もともと世界の中でトップ・クラスの高所得国であったデンマーク、スウェーデン、ルクセンブルクでも、所得水準は7割方増加している。
「小国」という言葉は、時に若干の「軽視」ないし「侮り」のニュアンスを伴って用いられるが、ここではそのようなニュアンスは一切無い。それらの国は、上記の12年間のマクロ経済パフォーマンス(成長・雇用・物価安定等)が優れているだけでなく、社会福祉・年金・医療・教育については、概して「大きな政府」の国であり、国民の福祉・教育の水準が高い。そして労使関係・環境問題・国民の政治参加・各種の国際貢献等でも優れた実績のある諸国である。私はそれらの国の経済的「躍進」に拍手を惜しまない。
「所得倍増」というと、日本の池田勇人首相が1960年に発表した「所得倍増計画」が思い出される。それは1961年からの10年間に、実質国民所得を2倍にしようという計画だった。この計画の発表当時、経済学者・マスコミの論者(ことに左派)のほとんどは実現不可能の空論だと評した。実現可能と考えたのは、池田首相のブレインだった下村治氏以外では、内田忠夫氏(故人)と私くらいだったが、実績は10年もかからずに、7年で所得倍増が達成された。
中国についても、私が最初に訪中した1983年頃、中国の学者や要人に中国の経済発展の見通しをしばしば聞かれて、私は中国経済は当分の間、かなり高い成長率で発展するだろうと答えた。その理由は、今までの中国共産党の経済運営があまりにも悪く、中国人が本来持っているさまざまな能力があまり発揮されていなかったが、中国が従来の中央集権的計画経済・対外閉鎖主義・反市場主義から対外開放と市場志向の改革政策に転換するのに伴って、多くの面で国際水準への catch up が進むと予想するからだ、と率直に答えた。
この日本、中国の例でも、東アジアのFour Tigers(韓国・台湾・香港・シンガポール)や ASEAN のいくつかの国の場合でも、また最近のインドでも、貿易自由化(日本の場合には、技術輸入の自由化の影響も大きかった)、対内直接投資の自由化(最近の中国の場合等)、その他 closed economy に近い状態から more open economy への移行、また硬直的な中央集権的計画経済体制や各種の「割当制経済」から decentralized system への移行等、経済体制・対外経済政策の画期的な改革ないし変革に伴って、高い経済成長率が実現される場合はしばしば見かけられる。
しかし最近の西北欧の小国の場合、そのような画期的な改革が行われたとは、私は寡聞にして聞いていない。一体、どのような原因ないし背景から、多くの国で著しく高い経済成長率が達成されたのであろうか? その答えをご存じの方に教えて欲しい。それらの国の経験は日本にとって参考になるかもしれない。
英国の経済的躍進
私が[表A]、[表B]から驚かされたことの第二は、英国の経済的躍進である。英国も[表B]の上位を占めており、その所得水準(名目)は12年間に倍増した。私が1986年に英国に2カ月間滞在した当時、英国では他の欧州諸国に比べてマクロ経済パーフォーマンスが著しく悪く、その頃までの英国は慢性の「英国病」(British disease)患者だといわれていた。すなわち欧州大陸諸国に比べて失業率・インフレ率が高く、労働争議が多発し、成長率が低かった。そして当時世界最高、あるいは最高に近かった日本はもとより、ドイツ・フランス・オランダ・ベルギーの水準と比べて、英国の所得水準はかなり低く、その7~8割程度に過ぎなかった。英国の大学教員の年間所得は日本の教員達に比べて半分くらいだったように思う。
この長年の「英国病」に対して、マーガレット・サッチャーは首相に就任してから"drastic"な「改革」政策を進めたのだが、英国の知識人・大学教授達のほとんどは、それを酷評し、かつ苦情を言っていた。しかし今振り返ってみると、サッチャーの経済改革は大成功を収めた。政権が労働党に移り、トニー・ブレアが首相になってからも、サッチャー改革の大部分は引き継がれた。サッチャーの11年、メイジャーの7年、ブレアの10年の合計28年、ことにサッチャー首相が1978-79、1984-85年の炭鉱労働組合の2度の長期ストを一歩も譲歩することなく乗り越えてから、15-20年の間に、慢性の「英国病」の患者だった英国経済はすっかり蘇ったのである。インフレ率・失業率は劇的に低下し、経済成長率はほぼ一貫して大陸諸国よりも高かった。そして英国の所得水準は今やドイツ・フランスのみならず日本をも追い越す高水準に達している。
1980年代中頃の英国の大学人・知識人のサッチャー批判は、基本的に間違っていたのではないか? また日本では、サッチャーと米国のロナルド・レーガンと一纏めにして「新自由主義」というレッテルを貼り、小泉元首相はその亜流だと批判する論者が少なくなかった。そういう「分類学」ではサッチャー改革の大部分を継承した労働党のトニー・ブレアも「社会主義者」ではなく「自由主義者」になってしまうが、それはかなり見当違いではなかろうか?
欧州大陸の三大国、ことにドイツの低迷
西北欧の小国と英国に比べて、欧州大陸の三大国すなわちドイツ、フランス、イタリアの経済は、[表B]から見る限り、低迷気味である。ことにドイツ経済の停滞が著しい。[表B]において、日本はどのランキングでも美事に24カ国中ビリである! それは、日本経済にとって「失われた10年あるいは15年」といわれるバブル経済後の長引く不況の結果であり、われわれ日本人にとっては目新しいことではなく、驚くべきこととはいえないだろう。ところが、ドイツも[表B]のどの指標でも日本と肩を並べ、美事にOECD諸国中のブービーの位置に収まっている。ドイツと国境を接し、経済的にドイツの影響を強く受けるスイス・オーストリーが、ドイツ経済の低迷のお相伴をしているのは致し方ないのかもしれないが、ドイツとともに大陸欧州の大国であるフランス・イタリアも、経済的に振るわないのは何故なのだろうか。
ドイツ経済の低迷の原因は、1990年の東西ドイツの統合後の10年程については、統合のために生じた西ドイツ側にとってのさまざまな負担が重かったためである、と私は理解している。しかしその後の時期、つまり21世紀に入ってからは、本格的な「欧州経済統合」の影響が、ドイツのマクロ経済パーフォーマンスに深刻な影響をおよぼしているように思われる。このことについて、私は Hans-Werner Sinn("The Pathological Export Boom and the Bazaar Effect: How to Solve the German Puzzle," World Economy, September 2006)の議論に説得されている。その議論をパラフレーズすると、大凡次の通りである。
ベルリンの壁の崩壊に端を発して東西ドイツが統合され、その後中東欧の多くの国(バルト三国、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア)がEU(欧州連合)に加盟した。また、それ以上に多くの中東欧諸国がWTO(世界貿易機関)に加盟した。それによって、旧ソ連圏の中欧・東欧諸国とドイツとの間の貿易・投資・技術移転の障壁は大幅に低下した。しかしそれらの諸国とドイツ国内との賃金水準の差は依然として非常に大きく、それは短期間には縮小しない。そこでドイツの製造業企業は国内ではほとんど設備投資を行わず、生産能力の拡張を主として中東欧諸国への直接投資(企業買収、買収した工場での設備投資、新工場の建設等)によって行っているという。そのため、ドイツの国際収支において貿易収支は直接投資による資本収支の赤字を反映して大幅の黒字であるにもかかわらず、国内では雇用が低迷し、失業率は暫く前にはほとんど10%に達していた。Hans-Werner Sinnは、ドイツの国際的に著名な企業が近隣のいくつかの外国で生産された部品や半製品をドイツに集めて完成品に仕上げ、それを世界中に輸出している状態を、"Bazaar Economy"と呼んでいる。
このような、嘗て先ず米国で、次いで日本で、「国内製造業の空洞化」(hollowing-out)といわれた傾向は、現在の日本でも進行しつつある難しい問題であるが、ドイツの場合には、この傾向が日本よりもはるかに深刻となる条件がいくつかある。すなわち、
(1)ドイツはEUのメンバーであるから、貿易政策のさまざまな手段はすべてEUに預けてしまっている。ある種の品目の輸入が急増しても、基本的に(多少の例外はあるのかもしれないが)、ドイツ独自の貿易政策によって輸入を抑制することが出来ない。
(2)通貨統合により、ドイツでは今や「ユーロ」が正貨として使われており、失業率の上昇や景気後退に対してドイツ独自の金融政策によって対処することが出来ない。
(3)EUの加盟国となった中東欧諸国からドイツへの労働移動は、原則として自由になった。旅券さえあれば、"work permit"など無しに、ドイツへ自由に入国して働くことができる。中東欧諸国とドイツの間には、長年にわたる相互の人的交流により文化的、社会的親近性がある。その程度は日本と近隣のアジア諸国との間の親近性よりもはるかに高い。しかしそれらの諸国とドイツの間の現在の賃金差は依然として非常に大きい。ドイツとの国境線が長いチェコの賃金水準(hourly labour costs)はドイツの大凡6分の1、ポーランドの水準は8分の1に過ぎないという。
(4)ドイツと中東欧は地続きであるから、たとえば自動車の生産の場合、部品を積み替えなしに近隣諸国からドイツに輸送することが出来る。スポーツ・カーの「ポルシェ」は嘗ては西ドイツのシュトゥットガルトで組み立てられていたが、ドイツ統合後は旧東ドイツのライプツィヒで「生産」されたことになった。しかしそのエンジン以外はほとんどスロヴァキアの首都ブラチスラヴァの工場で組み立てられ、ライプツィヒで付け加えられるのは、エンジン以外は僅かに過ぎず、ポルシェの製造業での付加価値全体のうちドイツ国内の分は約3分の1に過ぎないという。
アイルランドやアイスランドを見倣うことは出来ないか?
アイスランド、アイルランド、フィンランドの人口は(以下、いずれも概数)、それぞれ、30万、424万、516万であり、日本の地方と比べると、日本で人口が最も少ない県の鳥取県が約60万、四国が410万、北海道が568万である。鳥取県、四国、北海道に、経済社会政策・教育等についてほぼ100%の独立性を与え、ただし外交・防衛等は引き続き中央の日本政府が権限・責任を持つこととしたとき、鳥取県なり、四国なり、北海道は、アイスランド、アイルランド、フィンランドと同様のことが出来ないだろうか?
日本の地方の人々は、地方の経済・社会・教育・文化等々が振るわないのは、中央政府のコントロール(支配?)が強すぎ、また中央の地方に対する支援が不十分だからだと考えがちであるように見えるが、中央も地方も発想を根本的に転換して、各地方は準独立国のように、それぞれ適当と考えられるサイズで「自治地域」となり、思い思いに「地方自治」を実行したら、上記の諸国のように、世界最高の所得水準を達成できないだろうか?
アイスランドは、水産資源や地熱・水力発電等の自然条件に恵まれているとはいえ、国土の一部が北極圏の中に入る極北・寒冷の地である。民族の発祥の地であるスカンジナヴィアからは遠く離れた辺境に、長年にわたって民主的な社会を発展させ、世界最高の豊かな国を創り上げたことは、驚異であるといえよう(注1)。
アイルランドは19世紀中葉に主食であったジャガイモの病虫害で飢饉に見舞われ、大量の移民が米国・カナダ・豪州・ニュージーランド等に出て行った。それは概して悲惨な祖国放棄の旅であった。そして苗字の頭に「Mac」や「O'」の付く名前や、それら以外でもKennedy, Reagan 等、当のアイルランド人やアングロサクソン系の人々にはすぐにアイルランド系と判る姓の子孫は、世界中で7500万(祖国の現在の人口の20倍近く)に達しているという。アイルランドはOECDの前身であるOEECが1948年に創設されたときからの加盟国であるが、当初、同国は所得水準が低く、トルコ・ギリシャ・ポルトガル等とともに「OEECの中の途上国」といわれていた。
また、私の記憶はあまり確かではないが、1980年代中頃のアイルランドの経済状態も甚だ芳しくないものであった。年率10%を超えるインフレが何年も続き、このインフレを抑えるために政府は厳しいディスインフレ政策をとらざるを得ず、その結果、失業率は数年にわたって15%を超えていた。政府の財政赤字の累積のために政府債務が累積し、経済全体としての対外債務もGNPの130%を超えていた。Rudiger Dornbusch は、このような状況ではアイルランドでは税負担は重くならざるを得ず、労働者にとっても、企業にとっても、アイルランドは生産活動を行うのに attractive な場所ではなく、企業はEC(欧州共同体)または EU(欧州連合)内の他の国に立地するだろうし、労働者は労働移動の自由化に伴って欧州の他国に emigrate するだろう、と、甚だ悲観的な見通しを述べていた("Credibility, Debt and Unemployment: Ireland's Failed Stabilization," NBER Working Paper, No. 2785, December 1988)。
そのように嘗ては非常に貧しかった国、また私の記憶ではインフレ・失業・不況に悩み、債券発行市場での格付けで、OECD諸国の中では最も低い方の下ったアイルランドが、どのようにして世界最高の所得水準の国になったのであろうか(注2)。
フィンランドは中世以来、スウェーデン、デンマーク、ロシアの支配下にあり、第一次世界大戦後に漸くロシア帝国から解放されて独立を勝ち得たが、もともと他のスカンジナヴィア諸国とは民族・言語が異なり、スカンジナヴィアの中では所得水準の低い国であった。第二次世界大戦の戦勝国は30カ国以上あったが、敗戦国は6カ国しかなく、フィンランドはその1つであった。そのためフィンランドはソ連に対してカレリア地峡のかなりの部分と北極海への出口を含む領土の割譲を余儀なくされ、かつかなり重い賠償を支払わなければならなかった。またソ連の圧力により、マーシャル・プランの受入国となることが出来なかった。フィンランドにとって、第二次大戦後のかなりの期間は、苦難の時代であったといって良いだろう。
これら、アイスランド、アイルランド、フィンランドのような、嘗ては決して経済的繁栄の条件に恵まれてはいなかった小国が、最近になって世界最高の所得水準に到達したのは、どのようにして可能だったのか、というのが私の今回の「WHY?」である。