住宅価格/世帯所得比と家賃/住宅価格比の水準から見て、中国の主要都市における住宅価格はすでにバブルの域に達していると推測される。しかし、2013年半ばから金融政策のスタンスが緩和から引き締めに転換したことをきっかけに、それまで上昇し続けた住宅価格は調整局面に入りつつある。住宅バブルが崩壊すれば、その影響は関連産業にとどまらず、マクロ経済全般にも及ぶだろう。
バブルの域に達している住宅価格
中国における住宅価格は、景気動向、ひいては金融政策のスタンスに大きく左右される。リーマン・ショック以降の金融緩和を受けて、北京や上海など、主要都市を中心に住宅価格が急騰した。これに対して、2010年以降、中国政府は、需要抑制策としては融資規制、購入制限、不動産関連税制の強化、供給拡大策としては保障性住宅の建設の加速化からなる一連の対策を発表・実施した。これらの政策が功を奏する形で、70大中都市の新築商品住宅販売価格の前年比上昇率は、一時マイナスで推移していたが、その後の金融緩和をきっかけに、2013年1月から再びプラスに転じ、ピークだった2013年12月には9.7%まで加速した(図1)。
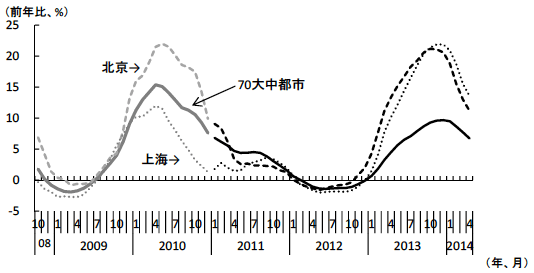
住宅価格/世帯所得比と家賃/住宅価格比の水準から判断すると、住宅価格がすでに均衡水準から大きく乖離しており、バブルの域に達していると推測される。まず、2013年の住宅価格/世帯所得比(世帯所得は年間値)は、北京が19.1倍、上海が18.1倍をはじめ、主要都市では、高くなっている(図2)。これらは、1980年代後半のバブル期の東京を上回る水準に達している。一方、2013年の家賃/住宅価格比(家賃は年換算)は、北京が2.0%、上海が2.4%など、預金金利(1年満期基準金利は3.0%、規制された上限は3.3%)を大幅に下回っている(表1)。このことは、投資家にとって、住宅価格の上昇によるキャピタル・ゲインが期待できなければ、家賃収入だけでは、収益率が極めて低いことを意味する。
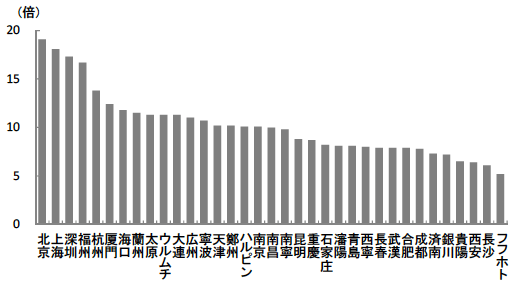
| (a)家賃 (年換算、元/㎡) | (b)住宅価格 (元/㎡) | 家賃/住宅価格比 ((a)/(b)、%) | |
|---|---|---|---|
| 北京 | 761.0 | 37,865 | 2.0 |
| 上海 | 702.5 | 29,622 | 2.4 |
| 深圳 | 631.2 | 26,494 | 2.4 |
| 厦門 | 435.5 | 21,869 | 2.0 |
| 三亜 | 489.4 | 19,334 | 2.5 |
| 温州 | 407.0 | 19,180 | 2.1 |
| 広州 | 494.3 | 18,400 | 2.7 |
| 杭州 | 479.2 | 18,229 | 2.6 |
| 南京 | 405.2 | 18,049 | 2.2 |
| 天津 | 381.5 | 15,977 | 2.4 |
| (出所)禧泰房産データ(http://data.cityhouse.cn/)より作成 | |||
調整局面に入りつつある住宅市場
住宅価格は、2014年に入ってから調整局面に入りつつある。4月には70大中都市の新築商品住宅販売価格の前年比の上昇率は、6.8%に鈍化している。前月比で見ても、住宅価格が上昇する都市の数が急速に減っている一方で、下落するまたは横ばいで推移する都市の数が増えている(図3)。
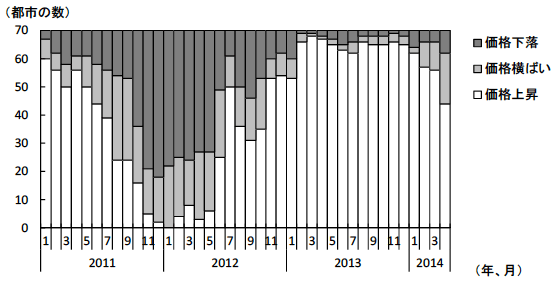
今回、住宅価格が調整に入ったきっかけは、金融政策のスタンスが緩和から再び引き締めに転換したことであると見られる。実際、2013年以降、不動産開発業者向けの資金供給の伸びは、社会融資総量の伸び(いずれも前年比)と同調して鈍化してきた(図4)。その上、金利の自由化に伴う金利の上昇と当局のシャドーバンキングへの引き締めも、資金コストの上昇につながっている。これを受けて、住宅に対する需要が減退する一方で、資金不足に陥っている一部の不動産開発業者が値引きして在庫の処分を急いでいる。
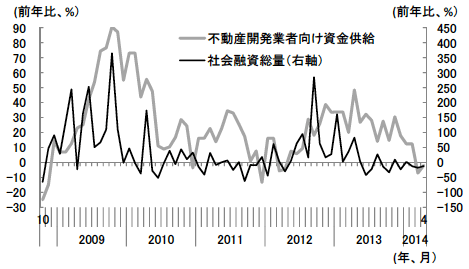
今後の住宅価格の動向を占うために、その先行指標となる住宅販売面積の動きに注目したい(図5)。リーマン・ショック以降、住宅販売面積の伸び率(前年比)は、2009年11月にピークを、2012年1・2月にボトムを、2013年1・2月に再びピークを打ったが、住宅販売価格の伸び率(前年比)も6ヵ月~1年後に転換点を迎えた。今年に入ってから、住宅販売面積の伸びがマイナスに落ち込んだことから推測すると、今後、住宅販売価格の伸びが一層鈍化し、マイナスになる可能性が高いと見られる。
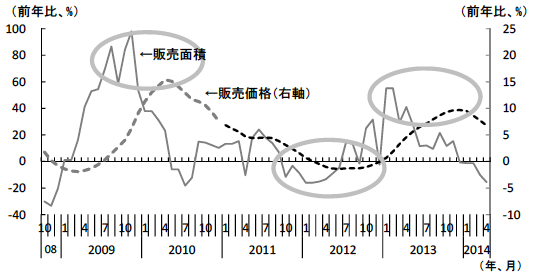
予想される住宅価格低下の影響
不動産は中国経済を牽引してきた重要な産業であるだけに、住宅価格の低下は、実体面だけでなく、金融面と財政面においても、中国経済に大きい影響を与えると予想される(表2)。
| 金額(億元) | 対GDP比(%) | |
|---|---|---|
| 不動産開発投資 | 86,013 | 15.1 |
| うち住宅 | 58,951 | 10.4 |
| 不動産販売額 | 81,429 | 14.3 |
| うち住宅 | 67,695 | 11.9 |
| 土地譲渡金 | 41,250 | 7.3 |
| 不動産関連税収 | 約20,000 | 約3.5 |
| 金融機関の不動産融資額 | 146,100 | 25.7 |
| うち個人向け住宅ローン | 98,000 | 17.2 |
| 参考 | ||
| GDP | 568,845 | - |
| 全国財政総収入(政府性基金収入を含む) | 181,382 | 31.9 |
| 金融機関の融資総額 | 719,000 | 126.4 |
| (出所)中国国家統計局、財政部、中国人民銀行のデータに基づき作成 | ||
まず、実体面では、2013年の不動産開発投資はGDPの15.1%に相当する8.6兆元に上っている。不動産市場が低迷すれば、不動産開発投資が従来ほど伸びなくなる。これは、直接GDP成長を抑えるだけでなく、鉄鋼、家電、家具などの関連産業における需要減を通じても、景気に水を差すことになる。
また、金融面では、2013年末現在、金融機関の不動産関連融資額は14.6兆元(融資総額71.9兆元の20.3%)に上る。理財商品や信託商品など、シャドーバンキング経由の分を含めると、不動産市場に流れる資金の規模がさらに大きくなる。住宅価格が下がれば、銀行の不動産向け融資の中から大量な不良債権が発生すると懸念されている。もっとも、近年、頭金比率の引き上げなど、住宅ローンへの制限が実施された結果、その可能性は低く、また、一部のシャドーバンキング商品が破綻しても、銀行への直接的影響も限られていると見られる。
さらに、財政の面では、2013年の地方政府の土地譲渡金収入は4.1兆元に達しており、約2兆元に上る不動産関連の税収を合わせると、全国の財政収入の約3分の1は土地に頼っていることになる。不動産価格が急落すれば、土地価格が低迷し、土地も売れなくなるため、政府の財政収入が大幅に落ち込む恐れがある。その結果、インフラ関連を中心に、公的投資も抑制されるだろう。
住宅バブルが崩壊した場合、中国も「失われた20年」を経験した1990年代以降の日本と同じ運命を辿ることが懸念されている。しかし、すでに成熟した先進国であった当時の日本と異なり、現在の中国はまだ発展途上であるため、「後発の優位性」を生かせば、6~7%という中程度の経済成長が当面維持されると予想される。特に、予想される都市化の進展は、不動産投資のみならず、経済成長を支える力にもなろう。このように、中国経済は、住宅バブルが崩壊すれば、短期的には景気の減速が避けられないが、長期低迷は免れるだろう。
2014年6月4日掲載


