2009年に出版した拙著『チャイナ・アズ・ナンバーワン』(東洋経済新報社)は、中国のGDP、貿易量、外貨準備、自動車・鉄鋼生産などの主要な経済指標を、米国と日本をはじめとする主要国と比較しながら、中国経済の実力を検証し、2026年にも中国のGDP規模が米国を抜いて世界一になるという予測を提示した。これに対して、当初から異論があったが、その後、中国経済の減速が顕著になるにつれて、「チャイナ・アズ・ナンバーワンは幻に終わるだろう」という論調が一層目立つようになった。しかし、中国は、成長率が引き続き主要国を大幅に上回っていることを反映して、世界経済におけるプレゼンスがむしろ一層高まっており、チャイナ・アズ・ナンバーワンの時代が着実に近づいてきている。中国のGDP規模が最終的に米国を上回るかどうかを基準にすれば、チャイナ・アズ・ナンバーワンが幻に終わるという可能性は極めて低いと言わざるをえない。
無用である過度な悲観論
中国経済の未来を巡って、悲観論を最も積極的に展開しているのは、経済産業省出身(元通商政策局北東アジア課長)で、現代中国研究家・コンサルタントの津上俊哉氏である。津上氏は、著書『中国台頭の終焉』(日本経済新聞出版社、2013年)において、今後の中国は、成長率5%程度の成長がせいぜいで、GDPで米国を抜いて世界一になる日は来ないと結論している。その根拠として、中国が直面している次のような短期、中期、そして長期の問題を挙げている。
まず、短期的問題として、4兆元に上る景気刺激策をはじめとするリーマン・ショックに対応した公的投資が設備の過剰をもたらし、このことは不良債権の増加につながりかねない。
また、中期的問題として、中国では農村部における余剰労働力が枯渇することを意味する「ルイスの転換点」の到来をきっかけに、賃金上昇圧力が高まっている。これを解決するためには、規制緩和と民営化を進めることを通じて、生産性を上げていかなければならないが、実際には、むしろ国有セクターが膨張して、民間企業が圧迫される「国進民退」が進んでいている。その上、「都市・農村二元構造」も農民の都市移動を妨げており、都市の人件費をいっそう高騰させる要因となっている。
さらに、長期的問題として、少子高齢化が急ピッチで進んでおり、中国は「未富先老」(豊かにならないうちに高齢化が進むこと)という試練を迎えているという。
確かにこれらは、中国経済の成長の制約要因になりつつあるが、これを以て中国の台頭がそろそろ終焉を迎え、また「チャイナ・アズ・ナンバーワン」も幻に終わると結論することはまだ早計である。なぜなら、中国は2013年の一人当たりGDPが6,747ドルと、米国(同53,101ドル)、日本(同38,491ドル)(いずれもIMF, World Economic Outlook Database, April 2014による、一部推計)などの先進国と比べて依然として低いため、産業の高度化や、海外からの技術移転の余地が大きいという後発の優位性が残っているからである(注)。
米中GDP逆転の時期
中国のGDP規模は、2008年には、4.52兆ドルと、米国の30.7%、日本の93.2%しかなかったが、2010年に日本を抜いて米国に次ぐ世界第二位となり、2013年には、日本の1.87倍、米国の54.6%に当たる9.18兆ドルに上昇している(図1)。その背景には、中国の経済成長率が、近年、低下しているとはいえ、依然として米国と日本など、主要国を大幅に上回っていることがある(図2)。これに加え、人民元のドルと円に対する上昇も、中国のGDP規模が相対的に拡大していることに寄与している。
― 日米との比較 ―
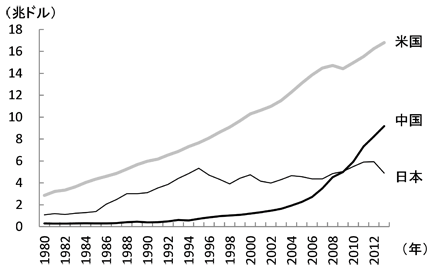
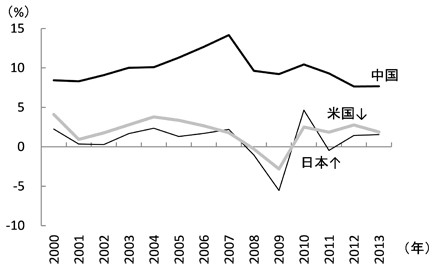
2013年の中国と米国のGDPをベースに、中国と米国の成長率と人民元の対ドルの為替レート(厳密にいうと、物価の変動を考慮した実質為替レート)の変化を併せて考慮し、楽観、標準、悲観という三つのシナリオに分けて試算すると、米中GDP逆転の時期は、楽観シナリオでは、2021年、標準シナリオでは2024年、最も遅い時期を示した悲観シナリオでも、2077年となる(図3)。
― 中国のGDPの米国のGDPに対する比率(試算) ―
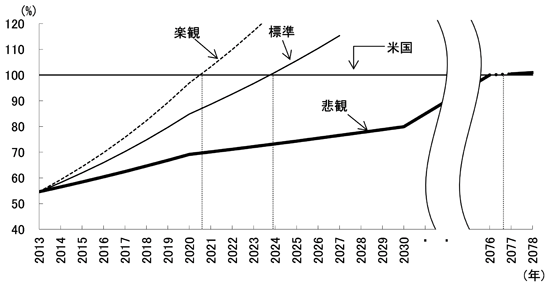
| 期間 | 楽観 | 標準 | 悲観 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GDP成長率 | 中国 | 2014-2020年 | 8% | 7% | 6% |
| 2021-2030年 | 6% | 5% | 4% | ||
| 2031年- | 5% | 4% | 3% | ||
| 米国 | 2014年- | 2.5% | |||
| 人民元の実質対ドルレート | 2014年- | 3% | 2% | 0% | |
| (出所)米国と中国の2013年の公式統計より試算 | |||||
揺るがない中国のグローバル経済大国としての地位
米中のGDP逆転を待たずに、中国による世界経済成長率への寄与度はすでに米国を大きく上回っており、2013年には世界全体(3.0%)の36.7%に当たる1.1%に上っている(図4)。ある国の世界経済成長率への寄与度は、その国の「成長率」と「世界GDP総額に占める割合(購買力平価ベース)」の積によって計算される。中国は、成長率が従来と比べて低下しているが、世界GDP総額に占める割合が逆に高まっているため、比較的高い寄与度が維持されているのである。
産業のレベルで見ても、2013年に中国の粗鋼生産量は、7.79億トンに達し、1996年以来首位の座を守っており、第二位の日本(1.11億トン)を大きく引き離している(表1)。また、2013年の中国の自動車の生産台数は2,212万台と、第二位の米国(1,105万台)の倍になっている(表2)。
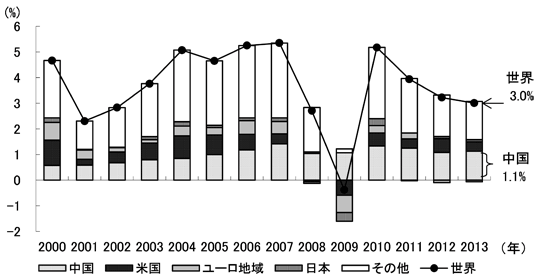
2013年中国の寄与度(1.1%)=(7.7%)×(14.7%)
2013年米国の寄与度(0.4%)=(1.9%)×(19.5%)
| 単位:億トン | ||
| 2008年 | 2013年 | |
|---|---|---|
| 中国 | 5.00 | 7.79 |
| 米国 | 0.91 | 0.87 |
| 日本 | 1.19 | 1.11 |
| (出所)世界鉄鋼協会(World Steel Association)より作成 | ||
| 単位:万台 | ||
| 2008年 | 2013年 | |
|---|---|---|
| 中国 | 935 | 2,212 |
| 米国 | 868 | 1,105 |
| 日本 | 1,156 | 963 |
| (出所)中国は中国汽車工業協会、日本と米国は日本自動車工業会「自動車統計月報」より作成 | ||
貿易面では、2013年に、中国の輸出規模は世界第一位、輸入規模は米国に次ぐ世界第二位を維持しており、輸出入の合計でみた貿易規模は初めて米国を抜いて世界一になった(表3)。
| 単位:10億ドル | ||||||
| 輸出 | 輸入 | 輸出入計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国 | 金額 | 国 | 金額 | 国 | 金額 |
| 1 | 中国 | 2,210 | 米国 | 2,331 | 中国 | 4,160 |
| 2 | 米国 | 1,579 | 中国 | 1,950 | 米国 | 3,910 |
| 3 | ドイツ | 1,453 | ドイツ | 1,187 | ドイツ | 2,640 |
| 4 | 日本 | 715 | 日本 | 833 | 日本 | 1,548 |
| 5 | オランダ | 664 | フランス | 681 | フランス | 1,261 |
| 6 | フランス | 580 | 英国 | 654 | オランダ | 1,254 |
| (注)なお、中国の1978年輸出入総額は206.4億ドルで世界第27位だった。 (出所)WTOデータより作成 | ||||||
金融面では、中国の対外純資産は年々増え続け、2013年末には1.97兆ドル(国家外匯管理局、「2013年国際収支報告」)に達し、日本の3.11兆ドル(財務省による一次推計)に次ぐ世界第二位の規模となっている。中でも外貨準備保有額は3.88兆ドルと、日本(1.27兆ドル)の約3倍に上る。予想される中国における資本取引の自由化の進展を合わせて考えると、従来の政府による外貨準備の運用に加え、民間による資金運用も盛んになると予想される。今後、中国は、実体経済の面のみならず、金融面においても、世界経済への影響力がますます大きくなるだろう。
2014年5月2日掲載


