中国では、2013年第3四半期に実質GDP成長率(経済成長率)は3四半期ぶりに上向いたが、それでも7.8%にとどまっている。一方、第3四半期のインフレ率(消費者物価指数の前年比)は第2四半期の2.4%を上回る2.8%(9月には3.1%)となり、2012年第2四半期以来の高水準となった。住宅価格の急騰も加わり、景気の過熱色は鮮明になってきた。「低成長下の景気過熱」という現状は、労働力の供給などに制約されて潜在成長率が従来と比べて大幅に低下していることを示唆している。これを背景に、当局は、金融政策をはじめ、マクロ経済政策のスタンスを緩和から引き締めに転換させると予想される。これを受けて、2014年の中国経済は減速するだろう。
前回の低迷期との相違点
リーマンショック以降(2008年第4四半期~2013年第3四半期)、中国の経済成長率の平均値は8.8%となっている。これを基準にすれば、中国経済は、2008年第4四半期から2009年第2四半期までの低迷期(平均経済成長率は7.5%)から、2009年第3四半期から2011年第4四半期までの好況期(同10.0%)を経て、2012年第1四半期以降、再び低迷期(同7.7%)に入っている(図1)。
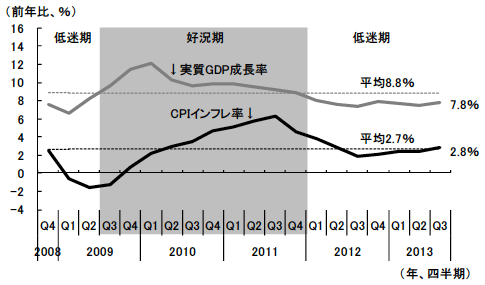
前回と比べて、今回の低迷期には次の特徴が見られる。
まず、景気過熱の兆候が見られる。両期間の経済成長率には大差がないのに、インフレ率は前回の平均が0.1%であるに対して、今回は2.6%と高くなっている。インフレ率にとどまらず、住宅価格も上昇している。2013年9月の70大中都市の新築商品住宅販売価格指数は、前年比8.7%上昇し、上海と北京に至っては、同20%以上急騰している(図2)。これは、住宅価格が下落した前回の状況と大きく異なっている。
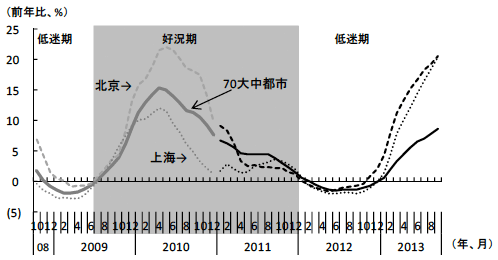
また、雇用問題が深刻化していない。前回は、リーマンショックを受けて、多くの出稼ぎ労働者が職を失い、都市部から農村部に戻らなければならなかった。これを反映して、都市部の求人倍率(求人数/求職者数)は2008年第4四半期には0.85まで低下した。しかし、今回の低迷期において、求人倍率は一貫して1を超えており、求人数が求職者数を上回っているという状態が続いている(図3)。
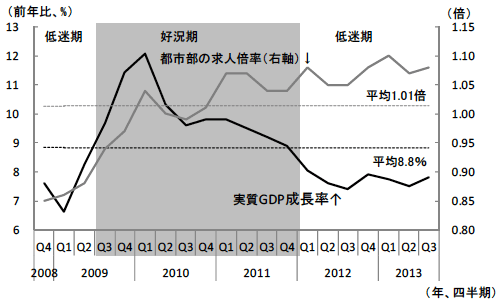
さらに、大規模な景気対策が行われていない。それゆえに、4兆元に上る内需拡大策が実施されたことを受けて中国経済がV字型回復を遂げた前回とは対照的に、今回は回復のペースが緩やかであり、低迷期が長引いている。
潜在成長率の低下を反映
これらの特徴には、共通した背景がある。すなわち、中国において、生産年齢人口の低下と農村部での余剰労働力の解消(いわゆる「ルイス転換点」の到来)を受けて、労働力が過剰から不足に転換した結果、潜在成長率が大幅に低下していることである。景気過熱の現状から判断して、中国の潜在成長率は、1979年から2012年の経済成長率の平均値である9.8%はもとより、リーマンショック以降の平均値である8.8%にも及ばず、すでに足元の実績値である7.8%を下回る7%程度まで下がっていると見られる。
現在の潜在成長率が従来と変わらないのであれば、7.8%の経済成長率は景気の低迷を意味する。その場合、雇用問題が深刻化し、インフレ率と住宅価格が低下し、政府も景気回復を目指すべく積極的に拡張政策に取り組むはずである。しかし、潜在成長率がすでに7%程度に低下しているとすれば、同じ7.8%という経済成長率はむしろ好景気を意味する。その場合、失業よりも、景気過熱が懸念され、政府のマクロ経済政策のスタンスも慎重にならざるを得ない。今の状況はまさにそれに当たる。
予想される金融引き締めへの転換
このように、経済成長率の実績値に加え、潜在成長率も、マクロ経済政策を策定する際の重要な参考指標となる。経済成長率の実績値が潜在成長率を下回れば、経済が冷え込み、その対策として緩和策が採られ、逆の場合、経済が過熱し、その対策として引き締め政策が採られる。無理して拡張的マクロ経済政策を以て潜在成長率を上回る高成長を追求すれば、バブルの膨脹を招いてしまう恐れがある。
中国では、金融当局は景気回復を促すべく、2011年12月、2012年2月と5月の三回にわたって預金準備率を引き下げたのに続き、2012年6月と7月の2回にわたって利下げを実施した。その際、経済成長率の実績値は潜在成長率を下回っていたという判断があっただろう。しかし、その後、経済成長率がほぼ横ばいで推移しているのに、景気の過熱色がますます強まる中で、当局も、潜在成長率の低下、ひいては引き締めの必要性を認識するようになった。すでに、インフレを抑えるために、当局は人民元の対ドル上昇を容認し始めている。インフレが今後さらに上昇すると予想されることから、人民元の対ドル上昇のペースが速まるだろう。また、預金準備率の引き上げと利上げも視野に入りつつある。インフレ対策の本格的実施は、景気減速のきっかけとなるだろう。
2013年11月6日掲載


