中国の経済成長率(実質GDP成長率)は、改革開放に転換した1978年から2012年にかけて、年平均9.8%に達していたが、ここにきて大幅に低下している。今年の第2四半期には7.5%と、昨年の第2四半期以降、5四半期連続して8%を下回っている。これに対して、中国を代表する経済学者の一人で、昨年まで世界銀行のチーフエコノミストを務めた北京大学の林毅夫教授は、成長率の低下があくまでも循環的な要因によるものであり、景気さえ回復すれば、8%成長が中長期にわたって持続可能であるという楽観論を展開しているが、議論の余地が残っているように思われる。
カギとなる後発優位性と比較優位の発揮
林毅夫教授によると、中国は後発優位性を上手く利用し、比較優位原則の下で政府がインフラ投資などの面において経済発展を積極的に支援すれば、今後も8%の経済成長率を維持できるだけの潜在能力を持っている(「林毅夫が質疑に答える:新構造経済学の要点」『FT中文ネット』2012年10月25日、「中国における経済成長の潜在力」『FT中文ネット』2013年8月28日)。その論拠は次の通りである。
まず、中国と先進国の間では技術面や産業面における格差がまだ大きいことから、技術革新による産業の高度化がこれからも経済の持続的高成長を支える力となる。すでに最先端の技術を持ち、産業の更なる高度化を自国の研究開発力に頼らなければならない先進国と違って、中国など途上国は、直接投資の受け入れなどを通じて、先進国から既存の産業と技術を導入することができる。これによって、研究開発コストなども低く抑えられるため、まさに一石二鳥と言える。これがいわゆる後発優位性である。
一人当たり国内総生産(GDP)から見ても、中国の後発優位性が大きいことがわかる。購買力平価を考慮した中国の一人当たりGDPは2008年には米国の21%にとどまり、ちょうど日本の1951年、シンガポールの1967年、韓国の1977年における米国の一人当たりGDPとの格差に相当する。日本、シンガポール及び韓国は、その後20年間という長期にわたり、経済成長率をそれぞれ年率9.2%、8.6%、7.6%の高水準に維持できた。この経験が当てはまれば、中国も2008年からの20年間において、年率8%の潜在成長率が見込まれる。
また、多くの国の経験が示しているように、自国の生産要素の賦存量を反映した比較優位に沿って発展戦略を採った国ほど経済が順調に発展している。生産要素の賦存量、ひいては比較優位は経済発展とともに変化するが、これを産業構造に正確に反映させるために、産業の高度化を目指すに当たり、政府は、産業政策による成長産業の選択や、インフラなどの公共投資の実施を通じて企業を支援しなければならない。
特に中国は、インフラ面の改善余地が大きい。これまでの経済刺激策は主に、高速鉄道、港と空港の建設を中心としてきたが、都市部の地下鉄建設や、汚水処理など環境保全に対する投資の余地がある。こうした分野に投資することは、経済や社会への波及効果も大きいと思われる。インフラ建設を推し進めるには政府の力が必要であるが、中国政府は財政状況が良好で、十分な投資能力を持っているという。
見落とされた成長の制約となる人口要因
しかし、林教授の分析では、成長の制約となる人口要因を十分考慮しておらず、それゆえに、中国経済の現在と今後の潜在成長率を過大評価している可能性が高いと思われる。
林教授は、現在、中国で見られる経済成長率の低下はあくまでも循環要因によるもので、潜在成長率の低下を反映したものではないと主張しているが、最近顕著になった「低成長下の労働力不足」という労働市場での異変から判断して、疑問を感じざるを得ない(図1)。具体的に、2010年までは、経済成長率が上昇するときに求人倍率(求人数/求職者数)も上昇し、逆に経済成長率が低下するときには求人倍率も低下するという相関関係が見られていたが、それ以降、経済成長率が低下しているにもかかわらず、求人倍率はむしろ上昇している。今年の第2四半期の経済成長率は、7.5%にとどまっているのに対して、求人倍率は1.07という高水準に達している。このことは、生産年齢人口の低下と農村部での余剰労働力の解消(いわゆる「ルイス転換点」の到来)を背景に、労働力が過剰から不足に転換した結果、潜在成長率が大幅に低下しており、実績である7.5%を下回っていることを示唆している。
―ルイス転換点の到来と潜在成長率の低下を示唆―
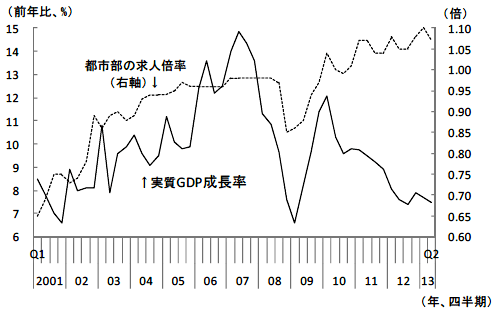
その上、林教授は、日中両国の発展段階の比較を踏まえて、中国も今後20年間、高成長が続く可能性が高いと主張しているが、両国の労働力供給の面において、状況が大きく異なっていることから、日本の経験をそのまま中国に当てはめることは必ずしも適切ではない。実際、15~59歳の生産年齢人口は、日本では1951年から1970年にかけて年率1.9%増えたのに対して、中国では2011年から2030年にかけて年率0.4%減少すると予想される(図2)。その一方で、当時の日本では扶養比率(非生産年齢人口/生産年齢人口)が下がり続けたこととは逆に、今後、中国の扶養比率は上昇し続けると予想される(図3)。このことは、経済成長に有利な人口のボーナスを享受していた当時の日本とは対照的に、これからの中国は経済成長に不利な人口のオーナス(重荷)を背負わなければならないことを意味する。特に、今後、中国において、扶養比率の上昇に伴う貯蓄率の低下が予想される。その結果、これまでの堅調な投資が維持できなくなり、林教授が提唱する投資主導型成長戦略の実現も難しくなる。
(1951-1970年の日本vs.2011-2030年の中国)
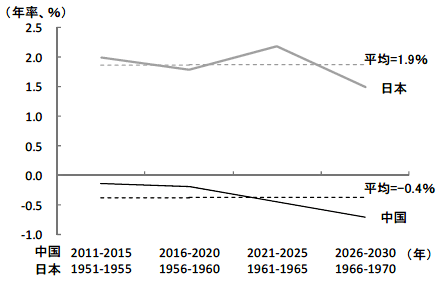
(1950-1970年の日本vs.2010-2030年の中国)
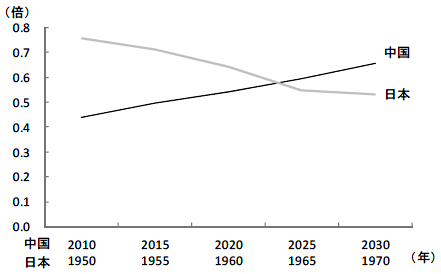
このような人口要因に加え、後発優位性も発展段階が先進国に近づけば近づくほど薄れていくことを合わせて考えれば、中国の潜在成長率は、現在の7%前後から、今後8%に戻るよりも、むしろ更に下がっていくと見るべきであろう。
2013年10月7日掲載


