中国が2005年7月に為替制度改革(人民元改革)の第一歩として管理変動制に移行した当時、人民元レートは均衡水準を大幅に下回ったと思われていた。しかし、その後、ドルに対して30%ほど上昇しており、それを背景に、中国の経常収支の黒字が大幅に縮小しているだけでなく、資本収支を合わせた国際収支の黒字もほぼ解消されている。当局が市場への介入を控える中で形成された現在の人民元レートは、すでに均衡水準に近づいていると思われる。
温家宝総理の見解
温家宝総理は2012年3月14日に、第11期全国人民代表大会(全人代)第5回会議終了後の記者会見で、人民元レートがすでに均衡水準に近づいている可能性があるという見解を示している。その根拠として、次の三点を挙げている。
- 2011年に中国の経常収支黒字の対GDP比はすでに3%という国際的に認められた合理的水準を下回る2.8%にまで下がっている。
- 2005年の為替制度改革以来、中国の実質実効為替レートはすでに30%上昇している(注)。
- 昨年9月以降、香港のノンデリバラブル・フォワード(NDF)市場で上下双方向の変動が始まっている。
確かに、1については、中国の経常収支黒字の対GDP比は、ピークに当たる2007年の10.1%と比べると、大幅に低下している。また、2については、2005年7月以来、人民元の実質実効為替レートは、対ドルレートとほぼ同じ30%程度上昇している(BISの統計による)。さらに、3について、将来の人民元レートの期待値の指標として広く使われるNDFレートと直物レートとの差(NDFプレミアム)がほぼ解消されている(図1)。
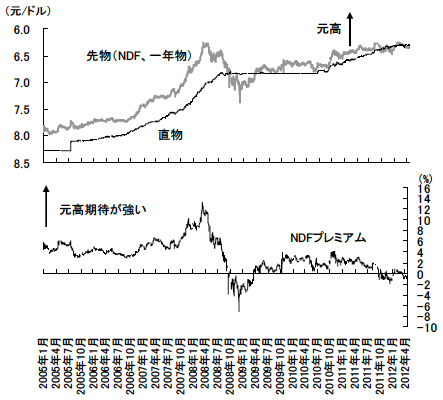
しかし、これを以て「人民元レートがすでに均衡水準に近づいている」と結論付けるには、まだ疑問が残る。まず、本来であれば、為替レートを決める要因として、経常収支に加え、資本収支も考慮しなければならない。また、「均衡水準」の定義が曖昧であるため、現在の人民元レートと均衡水準の差がなくなってきたかどうかは判断できない。さらに、現在のNDFレートは、人民元レートが市場よりも当局の裁量で決められるという理解の下で形成されている以上、市場の均衡値ではなく政府の政策スタンスへの予想を表しているにすぎない。
市場の需要と供給に基づく検討
ここでは、「均衡レート」を当局が介入しない完全変動制の下で、市場の需要と供給のみによって決められるレートであると定義し、現在のレートは、それに当たるかどうかを検討する。
完全変動制の下では、為替レートはもっぱら、市場の需要と供給によって決められる(図2)。外貨であるドルに対する需要は、経常取引としての輸入や資本取引としての資金の流出などによるもので、ドル高とともに減少する(右下がりの需要曲線)。一方、ドルの供給は経常取引としての輸出や資本取引としての資金の流入などによるもので、ドル高とともに拡大する(右上がりの供給曲線)。市場レートは需要と供給が一致する水準で均衡する。また、中央銀行は為替市場に介入しないため、仮に経常収支が黒字であっても、必ずそれと同額の資本収支の赤字に相殺され、外貨準備は増えない。
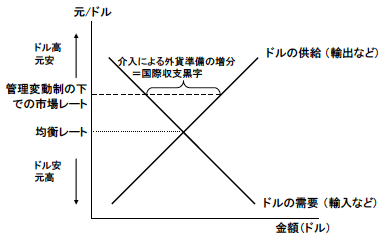
しかし、現在中国では、管理変動制を採用しており、当局が人民元レートを均衡水準より安いレベルに維持するために市場で過剰となったドルを介入という形で買い上げていることを反映して、経常収支と資本収支を合わせた国際収支が長期にわたって黒字になっており、外貨準備も増え続けてきた(図3)。特に、2008年9月のリーマン・ショック前後から約2年間にわたって人民元の対ドルレートが安定的に推移していた時期においても、外貨準備が増え続けていたことが示しているように、為替レートの安定はあくまでも当局の市場介入によって維持されたものである(図4)。しかし、2011年秋以降、中国の外貨準備はそれほど増えていないことから推測して、中国当局は介入を控えており、現在の人民元レートはすでに均衡水準に近付いていると見られる。
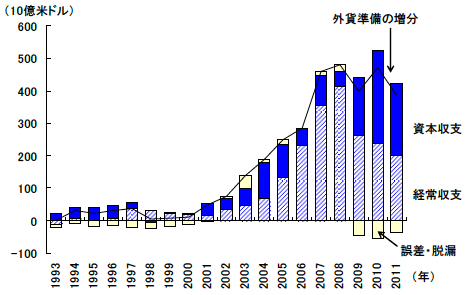
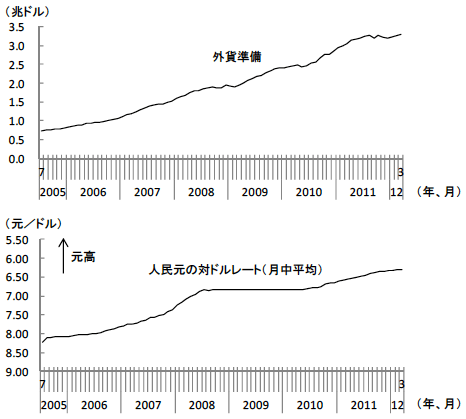
完全変動制へ移行する好機に
2005年7月以降、中国は人民元改革の一環として、固定相場制から変動相場制への移行を模索してきた。この過程において、為替の大幅な切り上げに伴う国際競争力の急激な低下を防ぐために、当局は市場介入を通じて、切り上げのペースを抑えてきた。人民元レートがすでに均衡水準に達したとすれば、当局が市場介入を控えても人民元レートが大幅に上昇する恐れがなくなることから、中国が「完全変動制」へ移行する時機はすでに熟したと言える。実際、2012年4月16日から、当局が決めている人民元レートの毎日の変動幅が従来の上下0.5%から上下1.0%に拡大され、これをきっかけに、人民元の「完全変動制」への移行は加速すると期待されている。
2012年5月2日掲載


