景気回復で再燃する労働力不足
中国では、景気回復とともに、昨年夏以降、労働者を募集してもなかなか集まらない「民工荒」(出稼ぎ労働者不足)という現象が顕著になっている。「民工荒」は、2004年頃から表面化し始めたが、リーマン・ショックを受けて、労働に対する需要が大幅に落ち込む中で、一時緩和された。しかし、2009年夏以降、都市部の求人倍率がほぼ危機前の水準に回復してきたように、労働の需給が再びタイトになってきている(図1)。
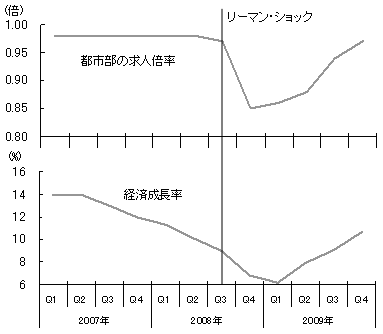
出稼ぎ労働者不足という現象は特に東部(沿海地域)において深刻である。中でも、深圳では、都市部の求人倍率は、景気がもっとも悪かった2009年第1四半期の0.94倍から2009年第4四半期には1.72倍に上昇しており、需給ギャップも10.3万人の供給超過から81.9万人の需要超過(求人数は194.4万人に対して、求職者数は112.5万人)に転じている(深圳人力資源公共就業服務網、「深圳市2009年第4四半期労働力市場需給状況」、http://jobsz.com/lsshr/MainAction.action?ActionType=content&id=229)。
労働力不足が起きた背景には、景気回復に加え、中部と西部(内陸部)における経済発展の加速、そして発展段階における完全雇用の達成を意味するルイス転換点の到来といった中国経済の構造変化がある。
中西部における経済発展の加速
まず、中西部において経済発展は加速しており、2007年以降、成長率は東部を上回るようになっている。特に、リーマン・ショック以来、海外市場への依存度が高い東部が輸出を中心に大きい打撃を受けているのに対して、中西部は2008年11月に発表された4兆元に上る景気対策の恩恵を受けているため、成長率の「西高東低」という傾向はいっそう顕著になってきた(図2)。
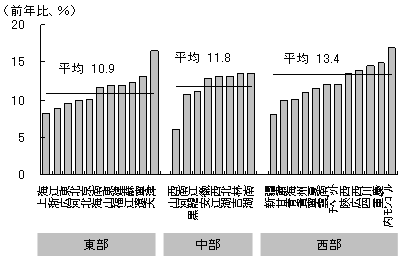
これを反映して、出稼ぎ労働者の流れは、従来の東部への一極集中から、中部と西部に分散する傾向が見られている。中国国家統計局の「2009年農民工監測調査報告」によると、2009年に、東部で働く出稼ぎ労働者数は前年比888万人(前年比8.9%)減り、9076万人となった(表1)。中でも、加工型の輸出企業が集中している珠江デルタでは、前年比22.5%も減少した。これに対して、中部と西部は、それぞれ、618万人(前年比33.2%)と775万人(35.8%)増加し、2477万人と2940万人となった。その上、2009年の各地域の賃金上昇率は、東部(5.2%)よりも、中部(5.9%)と西部(8.3%)の方が高くなっており、レベル(月額)で見ても東部の1442元に対して、中部は1350元、西部は1378元と、地域間の差が小さくなってきている。その結果、中西部の農民にとって、東部に出稼ぎに行くインセンティブが低下している。
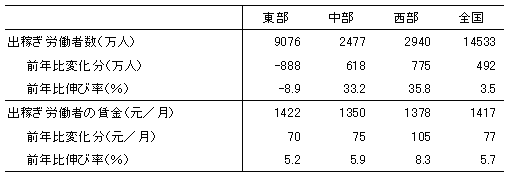
ルイス転換点の到来
一方、中国は発展段階における完全雇用の達成を意味するルイス転換点に近づいている(図3)。1980年から実施されるようになった一人っ子政策は、人口の年齢構造に大きい変化をもたらしている。当初は少子化が進むために生産年齢人口の割合は上昇したが、ここに来て高齢化が加速し始めており、2010年をピークに生産年齢人口の割合は低下すると予想される(図4)。その上、これまで1億5千万人に上ると言われてきた農村部での余剰労働力も解消されつつある。
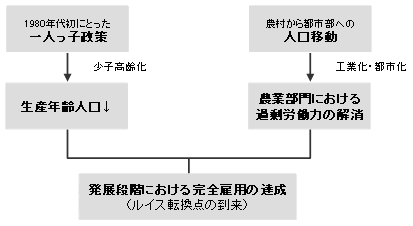
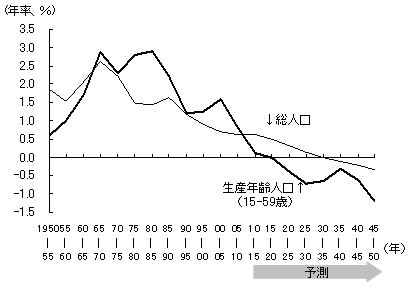
次の状況から判断して、ルイス転換点がすでに迫ってきていることは、間違いないようである。
まず、出稼ぎ労働者の不足が長期化し、当初東部に限られていた労働力の不足が、中西部にまで広がる傾向をみせている。その上、不足は技術者や熟練労働者ばかりに集中しているのではなく、非熟練労働者にも広まっている。
第二に、1998年まで実質賃金の伸びは一貫してGDP成長率を大幅に下回っていたが、その後、両者の関係が逆転するようになった(図5)。中でも、近年、出稼ぎ労働者の賃金上昇率が、正規の都市労働者のそれを上回っていると報告されている(蔡昉、「中国経済発展と転換点」、蔡昉編『中国の人口労働問題報告書No.8―ルイス転換点とその政策的挑戦』(第六章)、社会科学文献出版社、2007年)。
実質賃金の伸び率
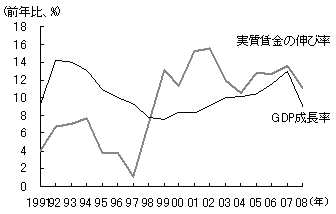
第三に、国務院発展研究センターの社会主義新農村建設推進課題チームが2005年に全国17省の2749村に行った調査によると、全国農村には約1億人の余剰労働力が依然残されているが、その多くは農業以外の産業への就業転換が難しい中高年労働力に当たり、農業以外の産業への就業転換が可能な青壮年労働力は転換を終えつつある(韓俊、崔伝義、範皚皚、「農村余剰労働力のミクロ調査」、蔡昉編、前掲書(第四章))。この調査において約四分の三の村は、「村内の出稼ぎに出ることができる青年労働力はすでに出尽くしている」と答えているという。
完全雇用の達成をきっかけに、政策の優先順位も雇用重視から生産性重視に変わっていくだろう。大量の雇用機会を創出しなければならないという制約から解放されれば、中国は、労働集約型産業から「卒業」し、より付加価値の高い分野に資源をシフトする形で、産業の高度化が加速するだろう。賃金と為替レートの上昇は、省力化投資や、新しいビジネス分野の開拓など、企業の経営戦略を通じて、それに向けた産業の再編を促すのである。最近、中国において労働集約型産業が不振に陥る一方で自動車や鉄鋼といった重工業が躍進を遂げているように、産業の高度化は着々と進んでいる(図6)。
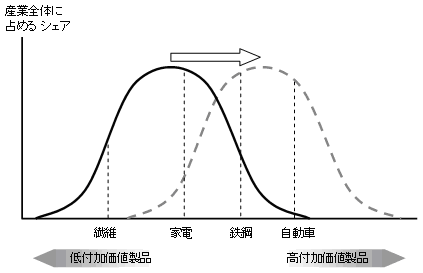
2010年4月28日掲載


