2009年12月にコペンハーゲンで開催される国連気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)では、京都議定書に続く枠組みなどが討議され、2050年までの温室効果ガス排出量削減目標と行動計画が提出される予定である(注1)。COP15を成功させ、環境破壊による人類の破滅を避けるために、最大の排出国となった中国の積極的貢献が期待されている。
中国は13億の人口を擁する大国であり、近年の経済の高成長を背景に、エネルギー消費量が急増しており、米国に次ぐ世界第二位のエネルギー消費国になっている。先進国に比べ、石炭をはじめとする化石燃料への依存度が高いことも加わり、中国の二酸化炭素(CO₂)排出量は2007年に60.3億トンに達し、初めて米国(57.7億トン)を抜いて世界一の規模となった(表1)。その一方で、中国の一人当たりエネルギー消費量とCO₂排出量は先進国に比べ、はるかに低い水準にとどまっている。これを考慮すると、今後、経済成長に伴い、エネルギー消費、ひいてはCO₂排出量はさらに増える可能性が高い。CO₂の大量排出は地球温暖化の原因とされるだけに、その影響は国内にとどまらず、世界全体にも及びかねないことから、中国は、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)などを通じて、国際社会と協力しながら、対策に取り組まなければならない。
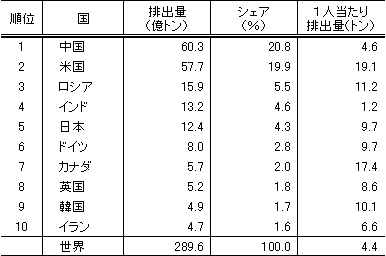
これまで、中国は、気候変動防止に関する国際協議の場において、協力的姿勢を見せながらも、「共通だが差異のある責任」という原則を盾に、あくまでも自発的取り組みを強調している(注2)。
すなわち、「先進国にせよ発展途上国にせよ、気候変動を軽減し、それに適応する対策を実施する責任があるが、各国の歴史的責任、発展レベル、発展段階、能力、貢献方法が異なるため、先進国はその歴史的な累計排出量と当面の一人当たりの排出量の高さに責任を負い、率先して排出量を削減し、それと同時に、発展途上国に資金を供与し、技術を移転する。発展途上国は経済発展と貧困撲滅の過程で、積極的な適応と軽減に関する対策を実施し、排出量をできる限り少なくし、共同で気候変動に対応するために貢献を果たす。」(国務院報道弁公室「中国の気候変動政策と行動」2008年10月)。
これを根拠に、中国は、発展途上国として、具体的な排出量削減目標を自らに課さず、公約もしていない。しかし、その一方で、台頭する経済大国として、また世界一の排出大国として、温暖化防止をはじめとする地球環境の改善という国際公共財の提供において、相応の責務を果たすことが求められている。こうした期待に応えるために、中国は排出量削減の数値目標を拘束力のある国際公約として掲げるべきであると胡鞍鋼・清華大学教授は提案している(胡鞍鋼「温暖化ガス排出削減で世界の主導国-低炭素経済が発展のカギ」、関志雄・朱建栄・日本経済研究センター・清華大学国情研究センター編『中国 成長の壁を越えて』、勁草書房、2009年10月)。
このような期待に応えて、中国政府はCOP15開催を前の2009年11月に、CO₂排出量を2020年までに、国内総生産(GDP)原単位(1単位のGDPを創出する際に排出するCO₂の量)で、2005年に比べ40-45%削減する数値目標を初めて発表した。今回の削減目標は、排出量そのものではなく、「原単位」が対象となっており、またあくまでも国内でのみ拘束力を持つ「自主的」なもので国際公約ではないことから、海外から不満の声が聞こえてくるが、これまでの中国のスタンスと比べれば、むしろ一歩前進であると評価すべきであろう。これにより、難航が予想されるポスト京都議定書の国際協調体制への各国の積極的関与が促されると期待される。
2009年12月25日掲載


