2002年6月に発表された通商白書では、グローバリゼーションの動きに参加する国家の間で経済水準の格差が収束し、戦後の東アジアにおいてもこのような傾向が見られるとしている。その波及経路として、貿易面での緊密化や投資の拡大が、域内の経済構造の高度化と地域間の水平分業を促進し、アジア各国間における所得格差を収束させる力として働いていることが強調されている。しかし、所得格差が収束するペースは非常に緩やかなものに留まっており、その上97-98年のアジア通貨危機の経験が示すように、その過程は必ずしも順調ではない。今のところ、域内貿易は、依然として各国の発展段階に沿った垂直分業が中心になっており、水平分業は域内格差の縮小の要因というよりも結果であると考えるべきである。
ここで所得格差の縮小に関し、日本、中国、NIEs、ASEAN4の10カ国・地域を対象に、1990年と2000年の東アジア地域全体のジニ係数を計算した。また参考のために、EU15カ国と中国の省別データを用い、同様の作業をした(図1)。これによると、東アジアのジニ係数は、90年の0.78から2000年には0.72へと若干改善してはいるものの、先進国が中心であるEU域内(2000年、0.10)はもとより、地域経済格差が大きいと言われている中国国内(同0.25)と比べてもはるかに大きい。
そもそも、90年代におけるアジア域内の所得格差の縮小は、後発組のアジア諸国の躍進よりも先発組の日本の経済停滞によるところが大きい。実際、アジア通貨危機の衝撃を受けて、ほとんどのアジアの国では成長率が80年代と比べて低下した。大幅な為替の切り下げも加わり、インドネシアやタイなど一部のASEANの国に至っては、90年代を通じて、日本との所得格差がむしろ広がっている。
しかし一方で、日本では90年代を通じて経済が停滞し、東アジアにおけるGDPのシェアが1990年の71.9%から2000年の65.1%まで低下してはいるものの、地域における経済超大国の地位は何ら変わらない。躍進のすさまじい中国と比べても、格差は縮小しているとはいえ、2000年でもGDP規模で4.4倍、一人当たりGDP規模では43.8倍と、依然として天と地の差が残っている。図2に示されるように、中国はあくまでも人口大国であり、高所得国ではない。
東アジア地域においては、同じ産業に分類される財の交換(即ち産業内貿易)が盛んになってきたことから、水平分業体制が整ってきたと言われている。しかし、依然として大きな経済格差を反映して、実質上、いまだに垂直分業が中心になっている。つまり、同じ産業に分類されるものに関し、最終製品にせよ、部品などの中間財にせよ、付加価値の高いもの(または工程)が日本やNIEsといった高所得国で、そして付加価値の低いものが中国を始めとする低所得国で生産されている。本当の水平分業体制の実現には、所得格差が解消し、他の国の所得が日本のレベルに収斂することが前提であると考えられ、まだまだ先の話であると考えられる。このように、東アジアにおいては、水平分業によって所得格差が解消するというよりも、格差が解消して初めて本格的な水平分業が実現可能であると理解すべきであろう。
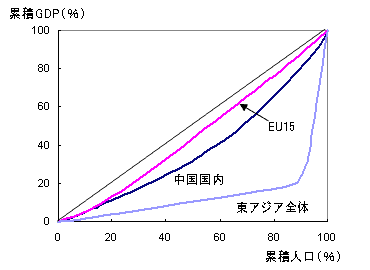
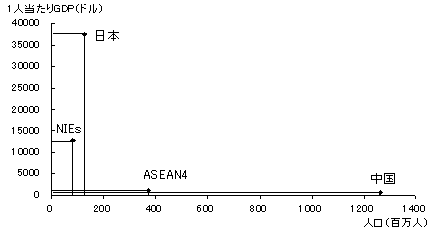
2002年7月12日掲載


