成長戦略の一環として、将来の日本の企業統治を巡る議論が高まっている。銀行危機の発生した1997年以来、日本企業の統治構造改革は、一貫して政策論議の中心の1つにあったが、今回の関心の高まりは、委員会設置会社の選択を可能とした2002年の会社法改正の前後に続く2度目の大きなピークといってよい。直接には社外取締役義務化に向けた法改正案をめぐる議論をきっかけに2011年秋に始まった今回の論議は、昨年6月、企業統治の強化が「日本再興戦略」の一環に位置づけられるとともに、より積極的な意義が与えられた。取締役会改革などの内部統治の改革は、機関投資家に投資先企業に対する責任ある対話を求める日本版スチュワードシップ・コード(注1)の公表などの外部統治の強化とパッケージで提示されることによって体系的となった。さらに、9月からは日本型コーポレートガバナンス・コードの検討が始まり、今後の統治構造に関する基本的な考え方を原則の形でまとめる取り組みが進められている。このレポートでは、今後の日本企業の統治改革の方向について考えてみたい。
統治構造の改革の課題
銀行危機以降、日本企業の株式所有構造は大きく変化した。株式相互持合いが解体し、それに代わって海外機関投資家の保有比率が急増した。東京証券取引所上場企業のうち、内外の機関投資家の保有比率の合計は96年の23%から2013年には48%に達し、これに個人の保有比率を加えたアウトサイダーの保有比率は、図1の通り60%に迫る。この間に上場企業は着実に増加し、この点は余り注目されていないが、英国・米国では非上場化の動きが進展していることと対照的である。他方、内外の機関投資家の保有比率は増加したが、その保有が機関間で分散しているのに対して、事業法人・銀行・保険会社などの保有は現在でも40%を占め、それぞれの主体は数%のブロックを保有している。つまり、日本企業は、上場のメリットを享受しつつ、安定的な株式所有構造を維持し、機関投資家の増加を受け入れている点で、機関投資家による保有が支配的な一方、上場企業の減少に直面する英・米とも、また上場企業が少なく、創業家族による集中的な保有が一般的な大陸欧州とも異なった進化を示している。
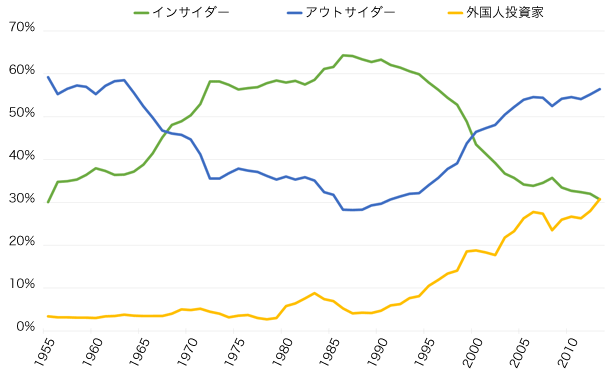
したがって、以上の特性をもつ日本の企業統治が抱える問題も英・米や大陸欧州と大きく異なる。大陸欧州の問題は、創業家と会社との間の利益相反問題にある。他方、リーマン危機後の英・米の株式会社における危機は、英国のケイ報告の指摘するように、短期志向の株主が敵対的買収を通じて、あるいは、過度のリスクテイクを強いることによって、債権者や従業員などの他のステークホルダーからレントを徴収するための機構に転じた点にある。それに対して、日本企業の問題は、逆に外部の株主の支配力がいぜん弱く、リスクをとらない保守的な経営が蔓延し、過大な現預金保有、低い株主還元政策が支配的となっている点にある。従って、今後の望ましい改革方向は、長期保有・従業員のコミットメントといった日本企業の特長を維持しつつ、とくに外部株主(投資家)の利益をより強く反映させる方向で、株主とステークホルダーの利益のリバランスを図る点に求められる。
スチュワードシップ・コードで何が変わるか
2014年2月に公表された日本版スチュワードシップ・コード(以下、コード)は、投資機関が投資先企業に対するモニターを強めることによって、株主重視の方向にリバランスを図る重要な契機となる。では、何が変わるのだろうか、また、その変化はどのような経路を通じて生じるのだろうか。
第1に、コードは、機関投資家に明確な投資方針の策定を求めた(原則1・7)。もっとも、投資顧問会社は、これまで運用方針・議決権行使方針・行使結果を公表してきたから、この原則の効果は特にアセットオーナー(年金基金)などに対して大きい。今回、GPIFをはじめとする公的・私的年金などのアセットオーナーがコードへの参加を表明したが、このことは、彼らが運用会社を選別する依託方針や、評価方針を明確にし、その運用会社のパフォーマンスを評価することにコミットしたことを意味する。こうしたコミットは、アセットオーナーの最終受益者(年金受給者、国民や企業の従業員)に対する説明責任を強める一方、今後、最終受益者がアセットオーナーの運用先選定に関してより積極的に監視を進める契機ともなる。こうした、いわゆるインベストメント・チェーンの形成を通じて、コードは、運用機関の対話の取り組みの強化を促す。
第2に、コードは投資運用会社に対して自ら直面する利益相反についての対処を求めた(原則2)。これまで国内の機関投資家は、投資顧問会社の場合にせよ保険会社・信託銀行にせよ、その銘柄選択・議決権行使には、親会社、グループ会社の影響を受ける可能性が指摘されてきたから、コードはこの点に対する明示的な対処を求めとことになる。もっとも、われわれの分析では(注2)、国内投資顧問会社の行動に強いバイアスは見られないから、今回のコードが大きなインパクトを持つのは、生命保険会社に対してと見られる。生命保険会社の投資行動や議決権行使は、他の取引(保険契約の拡大)を考慮する可能性が指摘され、これまでしばしば灰色の機関(Grey institutions) と呼ばれてきた。この点で、保険会社が本コードの受け入れを表明にしていることは歓迎され、今回のコードのもっとも大きな効果の1つということができる。実際、8月13日には、第一生命は生命保険各社に先駆けて議決権行使結果を公表することを決めた(実際に議決権行使結果が公表されたのは8月26日)。RIETIの小川亮RA(早稲田大学商学研究科)と進めた、簡単なイベントスタディによれば、この決定に対する市場の評価はポジティブである。同社が10大株主の1つを占める企業(178社/1802社)の8月13日から14日にかけてのCAR(累積異常収益率)は有意にポジティブ(0.27%)であり、この結果は、日本生命が10大株主の1つを占める企業の株価が全く反応を示していないこととは対照的である。コードは、これまで「物言わぬ株主」と理解されてきた生命保険会社が、企業統治により積極的に関与する契機となろう。
第3に、コードの原則3・4の求める企業と株式市場の積極的な対話は、今後、経営判断に徐々に影響を与えていくこととなろう。対話の対象となるのは、企業のオペレーショナルな意思決定ではなく、1)配当政策、自己株消却などの株主還元政策、2)財務政策(資本構成・資金調達策)、3)事業再組織化策、4)M&A戦略、5)買収防衛策の導入が中心となろう。これらの政策に関して、株主の支持を得ることがこれまで以上に重要となり、株主利益を損なう、上昇につながらない政策の継続は困難になる。もっとも、ただ企業側が、過度に株主の意向を考慮して、1)過大な配当、2)過度の負債調達、3)潜在的に(長期的に)優良な資産の売却、4)過大なM&A、5)必要な防衛手段の回避が起きる可能性がある。これが、いわゆる株式市場との対話の負の側面であり、非対称情報や、株主の短期的な視野の結果である。しかし、筆者の現時点での判断では、日本の場合、当面の問題は株式市場の企業経営に対する影響力の不足が問題であり、後者の近視眼の問題が深刻な企業は、機関投資家の保有比率は60%を超えたごく一部の企業であり、この問題への対処は将来に属する。
最後に、積極的な対話の促進というコードの実行は、投資家側には企業の固有の事情を理解することを促し、これまで形式的要件に依存しすぎた議決権行使を、より実質化することが期待できる。企業側は、投資家側が何を望んでいるかに関する認識を深める契機となる一方、今後、1)自社の企業価値に関するファンダメンタルな情報を十分に伝えるだけでなく、2)日本の事情に精通しない機関投資家が陥りやすい誤解を解く契機となることが期待される。企業の統治制度の特性は、ある程度まで海外機関投資家の銘柄選択の基準となっており、アングロサクソン型のスタンダード(社外取締役・ストックオプション)を評価する傾向がある。ただ、日本企業のすべてにとって、そうした制度を入れる必要はないし、導入することが有害である場合もある。企業は、自ら選択した企業統治の仕組みを、自社の事業特性などとの関係で、明示的に説明することがいっそう重要となる。
スチュワードシップ・コードの射程
コードによる機関投資家の受託者責任の強化は、以上の経路を通じて株主価値を引き上げる可能性がある。もっとも、これによって日本の上場企業の外部ガバナンスが即座に改善するわけではない。注目すべき点を確認しておこう。
第1に、機関投資家が企業統治に重要な意味を持つ企業が限られている点を確認しておく必要があろう。時価総額五分位別の機関投資家の保有比率の単純平均を示す図2を、先の図1と比較するとわかるように、東証の時価総額加重で得られる所有構造の変化の姿が妥当するのは、時価総額の大きい企業のみに限られる。海外機関投資家の投資対象は、MSCI(Morgan Stanley Capital International)インデックスに組み入れられた銘柄を中心に規模の大きい企業に限られ、現時点ではその下限は時価総額2000億円といわれる。したがって、コードによって対話が進展するのは、事実上、こうした時価総額上位350社程度にとどまる。
パネル1. 海外機関投資家の保有比率
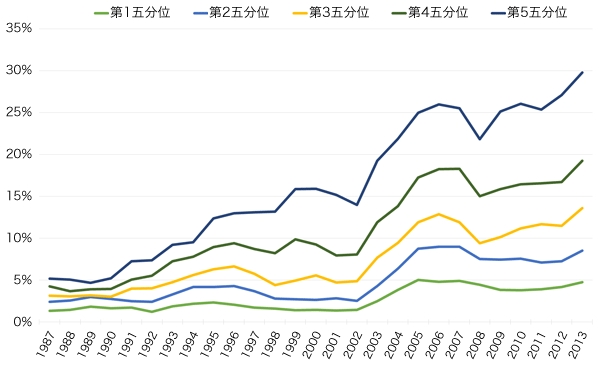
パネル2. 国内・海外機関投資家合計の保有比率
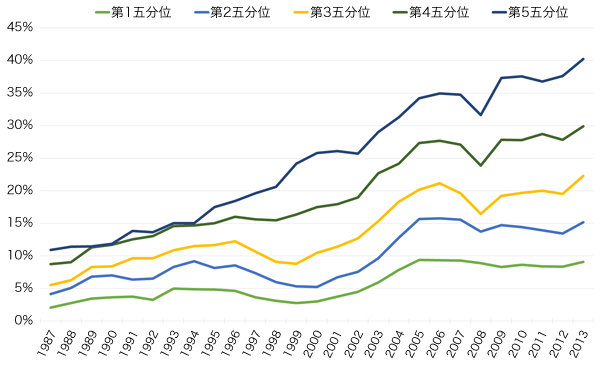
もちろん、比較的規模の小さい企業、非MSCI銘柄でも海外機関投資家の投資対象となれば株価は上昇するし、また、保有後の企業のパフォーマンスに対してポジティブな効果を持つことは確認されているが、ケース自体が限定的である。今後、機関投資家による投資先企業のモニターが日本の企業統治で重要性を高めていく上では、国内機関投資家を中心に、投資のユニバースの拡大、小型株ファンドが進むことが条件となろう。
長期コミットメントの促進
第2に、海外機関投資家の対象となる時価総額の大きな企業のみに限定しても、同コードは、対話を通じた機関投資家のモニターの強化という点では本質的な限界がある。本来、株主が投資対象企業の持続的成長に関与する仕組みを創り出すためには、株主の長期保有のコミットメントが不可欠である。しかし、投資顧問会社の基本的なビジネスモデルは、分散投資によるリスクの削減にあり、長期保有にはコミットしないことを特徴としている。平均保有期間が1年程度といわれるアクティブ運用を中心とする機関に、企業の中・長期の成長を考慮した対話を求めることは難しい。また、インデックファンドを運用する運用機関には対話に要するコストの支払いに限界があろう。さらに、国際分散投資の一環として日本市場に関心を持つ海外機関投資家も、経営政策の矯正をも含む、対話に強い関心を持つ可能性は低い。従って、コードの運用によって、対話が画期的な進展するといった過大な期待をかけることは禁物である。
従って、実際には、実質的な対話は徐々に進展すると見られ、その実現には、投資家側のコミットが不可欠である。その点では、対象企業の株式保有に長期にコミットする集中型投資ファンドが増加することが期待される。また、長期の株式保有にコミットする生命保険会社が「物言う株主」の側面を徐々に強めていくことも重要である。さらに、分散投資を進める内外投資家(投資顧問会社)が、投資対象企業の事業戦略・財務政策に再考を促そうとする場合に、共同して見解を発表する試みが有望である。現在、日本株を組成する外資系運用機関が共同して投資先との対話のための指針つくりを開始し、そのために投資家フォーラムを組織する計画が設定されている。今後のその活動に期待したい。
他方、外部株主の長期のコミットを促進するためには、種類株式などの新な仕組みの設計も重要な検討課題となる。この点でオックスフォード大学のメイヤー教授が『ファーム・コミットメント』(NTT出版)で提案する、保有期間についての登録制を導入し、長期に保有される株式に、普通株より大きな議決権を与える方法は検討に値する。これにより、企業の長期的利益に関心を持つ株主の投資先企業に対するモニターのインセンティブを引き上げる一方、発行企業は、長期に経営にコミットした株主を確保できる。
相互持合い規制
最後に、株式所有面での課題としては、相対的に規模の小さい企業の間で支配的な株式相互持合いの再検討が問題となろう。コードの狙いは、機関投資家の受託者責任の強化による企業価値の上昇である。しかし、相対的に規模の小さい企業の間では、機関投資家の保有比率は低く、株式相互持合いの比重は高い。さらに、筆者がこれまで試みた実証研究のいずれでも、持合い比率(銀行、生命保険の片持ちの合計)と、企業パフォーマンスの間には、有意な相関がある(注3)。この関係は、1)持合い関係にあると経営者が外部の圧力から遮断されることによって努力水準が下がる(いわゆるエントレンチメント効果)と、2)業績の低い企業の保有株式の売却を他の事業関係を考慮してためらう、という2つの側面があり、双方にとって合理的な選択となっているから、外部からの解消の促進策が必要であろう。
ただし、注意を要するのは、事業法人のブロック保有は、企業パフォーマンスについては、ポジティブな影響が確認されていることである。日本版コーポレートガバナンス・コードでも、持合いの規制が重要な論点となっているが、その際には、経営権の過度の保護を目的とする持合いと、実態的な経済関係に基づく事業法人間の持合いを慎重に区別し、適切な制度設計を試みることが今後の重要な課題となろう。
独立取締役の選任促進
近年の企業統治改革のもう1つの柱は、独立社外取締役の選任促進を中心とする取締役会改革である。今回成立した改正会社法では、いわゆるコンプライ・オア・エクスプレインの原則を導入し、独立社外取締役の選任について、選任しない場合、「相当の理由の説明」を求めた。このように独立性の高い機関の設置を促進することによって、いぜん内部者の利害が優位な日本企業の統治上の問題の解決を図ることが期待されている。
これまで、日本の企業の取締役会は、経営上の意思決定をその機能の中心としたマネジメント・ボードと特徴づけられる構造をとっており、この点は、1990年代末から監督と執行の組織的分離を謳った執行役員制が急速に普及した後も実は大きく変化していない。したがって、この構造を維持したまま、少数の独立取締役を選任しただけで根本的な変化が生ずるとみることは非現実的である。必要なことは、従来のマネジメント・ボードから経営の監督に特化したモニタリング・ボードと呼ぶべき仕組みに改革することである。従って、会社法改正後に進む社外取締役の導入が、単に外形的な整備にとどまるのか、以上の意味の実質的な変化を伴っていくかは今後の重要な注目点である。
もっとも、日本の企業がすべてモニタリング・ボードに移行する必要はないことは強調しておく必要がある。社外取締役に期待されている機能は、経営執行陣に対するアドバイスとモニターにある。また、この独立的な第三者によるモニターは、たんに少数株主だけでなく、従業員などのステークホルダーの利益を保護することが期待される。この役割は、従業員の企業へのコミットを競争力の源泉に置く日本企業では特に重要である。
一般に、独立取締役導入の合理性は、図3に要約した通りアドバイスを必要とする事業の複雑性(図の横軸方向)や、モニターを必要とする企業のエージェンシー問題の深刻度(縦軸方向)に依存する。事業ポートフォリオの多角化・グループ化が進むなど事業の複雑性の高い企業は外部のアドバイスの有用性は高い。他方、内部成長を中心とする企業(新興企業)ではモニターの必要性は低く、ここでは、現行のマネジメント・ボードで十分かもしれない。しかし、事業が成熟し、現預金の保有が多いか、買収防衛策を導入している企業ではモニターの必要性は高い(伝統的企業)。また、潜在的に従業員などのステークホルダーと外部投資家の利害対立が深刻な企業、つまり、人的資本の重要性が高く、外部資金への依存度が大きい、M&Aを通じた成長が合理的であるような企業群では、特にモニタリング・ボードへの移行の合理性が高いといえよう。
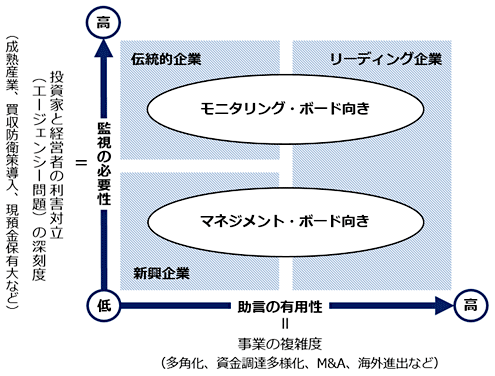
今後の取締役会改革の焦点
時価総額の大きい、先のMSCI組入銘柄であるリーディング企業では、独立社外取締役の導入は、2002年の会社法改正以降、徐々に進展しており、ほぼすべての企業で、すでに最低1人の選任は終えている。たとえば、昨年の2013年6月末時点で、時価総額上位200社のうち、独立取締役を1人も選任していない企業は、キヤノン、新日鉄住金、東レなど24社まで減少していたが、今年6月末にこのうち17社は1名以上を選任し、未導入の企業は7社となっている。
この意味で、日本のリーディンング企業では、1人以上の独立社外取締役を選任するという点に関してはすでに問題は解決しており、また、監査委員会設置会社に移行する理由も必ずしも大きくないと思わる。象徴的な変化は、トヨタ自動車の昨年の3名の社外取締役の選任である。これまで同社は、会社法改正によって委員会設置会社制の選択が可能となった2002年以降も、重要事項の意思決定にあたる取締役会メンバーには「現場の知識」が不可欠であるため、監督は社外監査役が過半数を占める監査役会が担うとして、あえて社外取締役は選任せず、また、取締役と執行役員との兼任も意識的に進めていた。しかし、海外展開が一段と進展し、また、米国でのリコール問題の経験を経て、トヨタは、監査役設置会社制を維持しながら外国人(元GM副社長)、金融機関(日本生命)から3人の社外取締役を迎えた。図3でいえば、マネジメント・ボードを採用する企業がさしあたりアドバイスの側面に重点を置いて社外取締役を選任したものと見られる。今後の注目点は、3人の社外取締役の選任とともに、監督の側面がどの程度強まっていくかである。
以上の例が示唆するように、リーディング企業での今後の課題は、第1に、新たな社外取締役の選任として並行して、新たなモニタリング・ボードの側面を強めるか、従来のマネジメント・ボードを維持するかを戦略的に選択することであろう。
また、第2に、複数の社外取締役の選任を前提として、自社の事業特性と、外部環境、事業上のポジショニングに応じて、外国人・女性取締役の選任などボードの多様性のどの程度実現するかである。私見によれば、海外売上比率が50%以上を超える企業では、外国人取締役の選任は不可欠であるとみられる。
中規模の企業/新興企業(企業家型企業)
以上のリーディング企業に対して、海外機関投資家の圧力が乏しい企業では、社外取締役の未導入企業が目立つ。図3の通り、理論的にすべての企業が社外取締役を導入する必要はない。また、実務的には、法学者・法務関係者の感触では、たとえば、新興企業が事業特性や自社の直面する利益相反の程度の側面から社外取締役を置かない理由を説明すれば選任しないことも可能という。もっとも、この場合には、監督は不可欠な機能であるから、重要事項の判断には現場の知識が不可欠などの挙証が必要であろう。
しかし、東証1・2部に上場している成熟企業では、財務政策、資本政策、事業再組織化、あるいは、買収に関連して、監督の観点から独立取締役の演じる潜在的役割は大きい。また、起業家に率いられる新興企業であっても、経営者の暴走回避にコミットする上で、社外取締役を選任する意義は大きい、外部取締役のアドバイスが、企業価値の向上に資する可能性は高い。社外取締役がこれまで日本企業で演じてきた役割に関しては、先般公表された「社外役員などに関するガイドライン」とともに公表された報告例が実務的に非常に有効であろう(注4)。
また、この企業群では、経過的に監査など委員会を積極的に利用することも1つの解決方法であるかもしれない。
取締役会改革に向けて
会社法改正にしても、東証の上場規則にしても、これまですべての企業に義務付けるという強行性を前提として構想されてきた。しかし、企業成長の促進につながる統治制度には、すべての企業に当てはまる、ワン・サイズ・フィッツ・オールの仕組みはないから、ベストプラクティスを提示し、それに従わない場合は、理由を説明するというコンプライ・オア・エクスプレインは強行法規より望ましいアイデアである。特に、多様化の進んだ日本企業の場合、選択の自由を保障することが不可欠である。
現在、会社法改正に続いて、日本版コーポレートガバナンス・コードの検討が始まった。同コードでは、既述の持合いに関する規制と並んで、取締役会構成(人数や独立性の定義)にどの程度踏み込むかが重要な論点となろうが、私見では、原則のみを提示することが望ましいように思われる。たとえば、すべての日本企業がモニタリング・ボードの方向に変えること望ましいという想定に立って、社外取締役の人数や、独立性の要件を余りに厳密に規定することには慎重であるべきであろう。この規制が、行き過ぎると、企業が規制忌避して非上場化する可能性もある。日本企業の多様な実態を考慮したコードの検討を期待したい。


