本稿は、「アベノミクス」による過度の円高の是正により、大幅な企業収益の改善、経営マインドの劇的な好転およびこれを基礎とする賃金の引き上げや設備投資の回復を実現しつつある我が国製造業が、「失われた20年」の間に如何なる負の遺産としての構造調整(国内の空洞化、競争力喪失など)に直面してきたかを分析し、同時により深化する「グローバル化」と「1ドル=100円強の為替水準定着」という新たな競争環境の下で、輸出力と非価格競争力を回復していくため何をなすべきかについて考察した論文(注1)の要約である。
本稿は、大きく3つのパートから構成されている。まず、第1のパート(1、4、6)においては、統計分析や企業への訪問調査等を通じて、貿易赤字拡大の背後にある構造問題として「行き過ぎた海外生産の拡大による国内空洞化」および「エレクトロニクス産業等での非価格競争力の喪失」が最も重要であることを示しつつ、今後は海外拠点の収益力向上による国内産業基盤(研究・開発・設計機能)維持の重要性や取引先大企業に依存しない新しい独立型中小企業の戦略的振興が重要であることを強調している。
また、第2のパート(2、5)では、「グローバル化」と「デジタル化」の荒波の中で劇的に競争力を喪失したエレクトニクス産業の敗北メカニズムを分析しつつ、高度な技術力を市場の競争力に直結させる企業レベルの知財戦略の重要性を主張している。最後に、第3のパート(3)では、2000年頃から本格化した企業統治改革がそもそも日本企業が寄って立つ社会的文化的文脈から余りに乖離した形で強行されたため、日本企業の競争力を減じた可能性に言及しつつ、今後の冷静かつ科学的な対処の重要性を主張している。
1 巨額の貿易赤字定着と産業の「空洞化&競争力喪失」の構造的連関
1996年以降の輸出入額、貿易収支および経常収支の推移を見ると、2008年のリーマンショック時と2011年の東日本大震災という2つのエポックメーキングな事件が生じた年に基本的なトレンドの変化が生じていることがわかる。即ち、2008年には、リーマンショックによる世界的景気停滞を反映し、輸入がそれ以前のトレンド上で拡大した一方で輸出が減少に転じ、貿易収支と経常収支の黒字幅が大幅に減少した。また、2011年には、東日本大震災による国内サプライチェーンの寸断などを背景に輸出が減少したのに対して、輸入が原発稼働停止による燃料輸入増を反映して更に増加したため、2010年に回復に転じる気配のあった貿易収支黒字と経常収支黒字が大幅に減少し、前者はついに赤字化した。
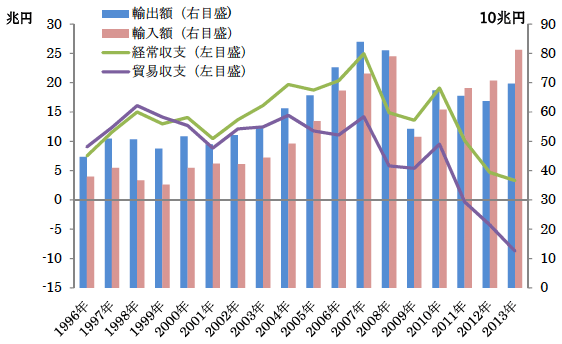
このように、2008年の需要面(世界)のショックと2011年の供給面(国内)のショックとを経て、我が国の貿易収支赤字が定着するに至ったが、その間を通じた基本的傾向は、「輸入の顕著な増加」と「輸出の伸び悩み」である。このうち前者については、原発運転停止と円安に伴う化石燃料輸入代金支払増の影響は確かに大きいが、2013年1~9月期の輸入額の対前年同期比伸び率を見ると、鉱物性燃料が8.3%であるのに対して一般機械が16.4%、電気機械が19.8%、および輸送用機械が15.6%となっており工業品輸入増の貢献の方が大きい。更に、電子部品の伸び率が35.7%、自動車部品のそれが20.2%となっており、2000年代以降本格化した下請けも含む『根こそぎ海外進出』の構造的寄与が示唆される。
他方、2割を超える円安進行により少なくとも国内産製品の価格競争力は著しく回復したはずにも関わらず輸出が伸び悩む現実は、非価格競争力の低下や空洞化による国内生産能力自体の縮小を示唆している。実際、「概ね2000年以降Jカーブ効果が現れにくい構造になっている」こと(注2)や「過去20年間に、法人企業の内部留保拡大にほぼ見合う規模で長期株式所有が増大している」ことなどを見ると、やはり行きすぎた企業の海外進出がもたらした国内生産能力の空洞化の影響と考えるのが妥当である。また、実際の市場プレゼンスを見ると国内の空洞化と同時に、電機産業を中心に製造業の非価格競争力も低下し、世界市場の爆発的成長の中で市場シェアを劇的に失った影響(注3)も無視できない。
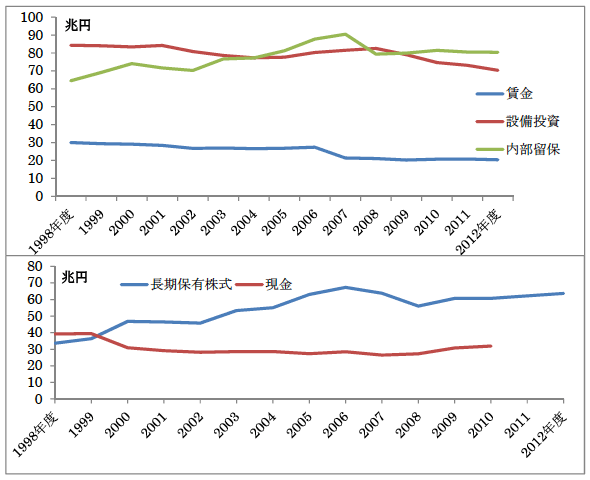
2 「デジタル化」と「グローバル化」による競争力喪失
1980年代に世界を圧倒した日本のエレクトロニクス産業がその後の「失われた20年」の間に、先進的技術水準で依然として優位を維持しながら市場競争に勝てなくなったことは、近年かなり広く認識されている。その背景を分析する論考は少なくないが、小川[2014] は、2000年前後に本格化した「グローバル化」と「デジタル化」を軸概念として、対アジア企業に対する敗北のメカニズムと、欧米メーカーの独占的競争力を整合的に説明する点で秀逸である。彼によれば、製品の技術構造がハードウエア・リッチなものからソフトウエア・リッチなものに深化することで、従来の「工場内摺り合わせ」や「現場の暗黙知」が果たした品質管理上の役割が基幹部品や製造設備への組み込みソフトに代替されたことがもたらした「最先端の技術が瞬時に国境を越えてグローバルに移転する市場の出現」が圧倒的な製造技術優位を誇った日本企業の競争力を劇的に低下させたとする。
これに対する勝ち組欧米企業の戦略を見ると、意外なことに各社の圧倒的強みとなるコア技術領域に係る特許取得は少なく、ほぼ社内に囲い込んでいる。他方、契約でのインターフェース情報の開示や基幹コンポーネントのインターフェース情報の全面的開示により、激しい競争によるコストの大幅減と世界市場の急激な拡大を実現している。他方、製品や部品の設計・開発・生産に特化したアジア企業は、クロスライセンス戦略により研究開発コストを最小化するとともに、償却期間などを自由に選択できる柔軟な法人税制の支援も得つつ、「機動的な大規模生産設備投資により高い市場シェアを目指す」戦略により、低利益率でも売り上げを最大化することで市場競争に勝利した。
両者の間に挟まれた日本企業は、多額の研究開発投資と夥しい数の特許を生み出したものの、それをビジネスでの勝利に結びつける具体的な戦略不在のまま、当初の圧倒的な技術力に基づく独占状態が短期間に崩壊し、しかも近年になるほど市場シェアの劇的喪失に至るまでのリードタイムが短縮し、今や研究開発投資分の回収も難しく、ビジネスそれ自体を維持できなくなりつつある。
3 コーポレート・ガバナンスの歪みによる「良い経営」の萎縮
2000年前後を転換点として、1) 株主代表訴訟制度の改革(訴訟提起の容易化)、2) 内部統制制度の強制導入(企業統治における性悪説への転換)、3) 株式持ち合いの解消(機関投資家の役割増大)、および 4) 役員制度改革(執行役の分離と委員会会社の創設)などによる企業統治改革が一気に進められた。これらの諸改革は、いずれも英米型の会社観に基づき、多様なステークホルダーのうち株主のみの利益を最大化するべく構想されたが、「伝統的な企業観や企業統治原理とは相容れ難いものを性急に、かつ強制的に取り入れたため日本企業の競争力が徒に毀損された」とする見方がある。
たとえば、株主代表訴訟改革により訴訟リスクを意識した取締役は、「経営判断の原則」を遵守する必要に迫られ、監視とルール違反への厳罰によるコンプライアンスを強化したが、これは「X理論に基づく管理」の導入を意味し、従業員のパフォーマンスは低下した(注4)。また、多くの経営者が合理的だと思う決定に拘わった結果、市場競争に当然伴うリスクも取れなくなった。更に、持ち合い解消に伴う上場子会社の100%子会社化は、日本企業がリスクを取ってベンチャー的新規事業を進める上での優れた伝統的手段を奪った。他方、機関投資家の役割拡大や執行役員制度の導入も会社への長期コミットを基礎とする内部監視機能を低下させ、短期の利益計上や過大な配当を求める近視眼的な株主圧力を高めた。
勿論、バブル崩壊後のバランスシートの極度の拡大や株主利益を余りにも軽視した企業経営慣行など、日本企業側にもこれらの改革が求められた実態と問題はあった。しかし、これら一連の改革の基本にある英米型の会社観と制度の発想は、日本で伝統的に機能し、高度成長期に広く定着した『従業員や取引先も含む多様なステークホルダーが主体的に関与する長期連帯主義による経営やガバナンス』とは余りに距離があり、やはり短期的な効果の一方で、中長期的な弊害も無視し得ないものがあったのではないか。
4 今後の対応1:国内産業拠点の維持と海外拠点の収益力向上
アベノミクスが企図するデフレ脱却を実現するとともに、中長期的に民需主導の成長軌道への復帰を実現していくため、輸出力と技術革新力の回復に繋がる国内産業基盤の競争力再構築は、経済政策上の喫緊の課題である。しかし、過去の円高期に一旦海外に移転した設備投資はサンクコストになりがちであり、容易に国内に再転換できない。加えて、サプライヤーも含む海外進出の蓄積による海外での集積形成が更なる海外投資を誘引する効果も小さくない。更に、日本経済が直面するISバランスの限界(企業部門のみ貯蓄過剰だが海外生産能力に化体)を踏まえると、マクロ的には可能な限り空洞化スピードを遅らせつつ、巨額貿易赤字による国富の散逸を防ぐとともに、人口減少時代にも中長期的にサステイナブルな国内産業基盤を早期に構想し、構築していくことが肝要である。
この場合、国内に維持されるべき産業基盤とは、まず現在日本企業が競争力を維持し、今後もその見込みの高い産業分野を考えるべきである。業種的に見れば、自動車、自動車部品、産業機械、建設機械、および精密機械などの『摺り合わせまたは術蓄積が意味を持つ非デジタル産業分野』である。また、「市場規模で100億円程度のニッチ分野は技術蓄積のある日本企業の競争力維持が容易」であり、当該分野も重要である。他方、機能面で見ると、研究開発部門、製品開発・設計部門、およびマザー工場(世界の自社拠点向けの生産技術開発指導部門)が重要であり、特に根こそぎ海外進出を防ぎ、技術力ある中小企業が競争力を維持しつつ国内事業基盤を維持していく上で、需要創造と技術情報移転の源泉となる大企業の開発・設計部門が国内に残ることは、優れて肝要である。
また、このような諸重点分野・部門を競争力ある国内産業基盤として維持していくためには、これら諸部門自身が必ずしもプロフィットセンターではないことも踏まえ、企業全体の戦略として、これら国内拠点を維持・強化するための資金の稼ぎ場として、海外拠点の役割はその重要を増す。同一社内の国内拠点に比べれば利益率が高いものの同業の欧米企業よりは低いといわれる海外子会社の収益率を高め、そこから国内への送金増を図ることが今後益々必要となる。因みに、今回のASEAN現地調査を通じて、輸送用機械や電気機械を中心に現地で多拠点を展開する主要日系企業が海外に蓄積した自社事業資産の収益力を高めるため、地域経営の強化、生産以外の現地化の強化などに積極的に取り組んでいることが明らかとなっている。
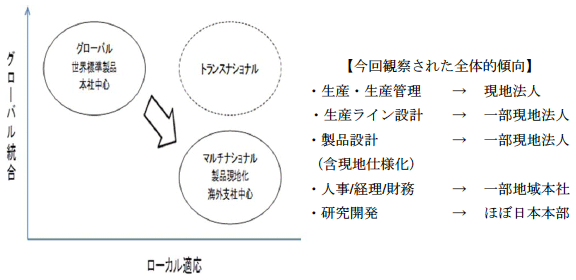
5 今後の対応2:「ソフトウエア・リッチ型産業」分野における競争力再構築
また、日本企業が劇的に競争力を喪失したエレクトロニクス産業を中心に、「ソフトウエア・リッチ型産業」分野での競争力を再構築することも必要不可欠である。何故なら、エレクトロニクス産業は依然として技術革新が著しく、市場の成長力も高い産業分野であり、この分野で競争優位を維持することが国内産業基盤を「量的に」維持する上で意味が大きいからである。また、従来「摺り合わせ型」ゆえに日本企業が優位を持つとされた自動車、事務機械、産業機械、機能材料、石油化学などの産業でも急激にソフトウエア・リッチ型への転換が生じている現実があり、これらの産業分野でも競争優位を失うことは、国全体としての技術水準や技術革新力を維持していく上で深刻な影響が生じる可能性もある。
このためには、やはり欧米企業の戦略に学び、各社が自らの固有の強みを活かした新しい戦略を構築し、大胆な戦略転換を行うことが緊要である。この場合、小川[2014] が具体策として主唱する『毒まんじゅうモデル』戦略は、必ずしも欧米勝ち組企業の専売特許ではなく、三菱化学など日本企業でも効果的に実践されている。技術力の向上は当然として、より大切なのは、当該技術力を活用して「自らが儲けるビジネスモデルと知財戦略」を各企業が独自に考案し、実践することである。勿論、そのためには当該戦略を構想する能力を有する人材の育成・確保は勿論のこと、それを企業レベルの重要課題として組織的実践に体化できる「経営者の眼力や能力」も不可欠となる。
そういう意味では、政府レベルでも「厳格な知的財産の保護」はともかく、「多額の研究開発投資」および「多数の特許取得」が企業と産業の成長に直結すると単純に想定する既存の「知的財産政策」や「技術開発政策」についても再考が望まれる。何故なら、既に見たように、「デジタル化」が進む産業分野においては、少数の特許を使ったクロスライセンスにより容易に技術が移転し、またはコピーされ、また、そもそも特許取得それ自体が当該技術情報の公開情報化を加速する結果をもたらしているからである。また、産業競争力の観点からは、特にIT産業を中心に、特許権のみならず、著作権や意匠の領域においても米欧企業の勝ちパターンを戦略的視点から慎重に検討することが望まれる。
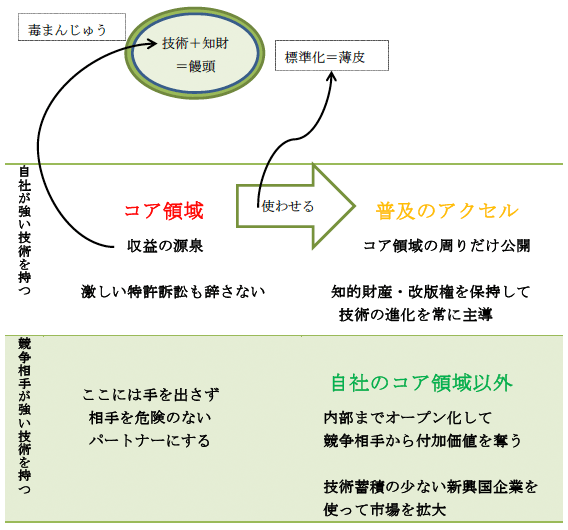
6 今後の対応3:「新しい独立型中小企業」群の戦略的振興
2000年代以降の期間に、我が国の製造業の競争力低下と国内空洞化の深化により、円高是正後も輸出量そのものが増えにくい産業構造となったが、この間を通じて最も競争力を維持しているといわれる自動車産業においても、これまでの「グローバル化」トレンドに加えて、「部品共通化」や「モジュール化」トレンドによるサプライチェーンの構造的変化が生じつつある。かかる構造変化が進展すれば、国内の大企業製造拠点から取引先である中小企業への部品発注量や技術情報の流通機会は確実に減少し、これまでの単純な「下請型事業モデル」では、いくら良い加工・製造技術を有していても企業としての存続が徐々に困難となっていくと予想される。
では、どうすべきか。今回筆者が行った「成功している海外非進出中小企業」への訪問調査によれば、その共通の特徴として、1) 独自の技術又は技能を武器に国内で生き残ることを明示的な経営戦略目標としていること、2) 生き残るための必死の努力が強い競争力を生み、これを基盤に一昨年来の円高修正局面で高収益を享受していること、3) 大企業とのデザイン・イン活動等を通じて提案型営業を行っていること、4) 自社製品の高性能と低価格を欧米企業に訴求するべく、海外技術営業スタッフの充実を図り、新たなビジネス発掘に努めていること、5) 会社と従業員間の強い一体感や優れたチームワークを維持し、伝統的に日本企業の強さの根源であった「長期連帯主義による経営」を行っていること、が明らかとなった。
これを踏まえ、今後の有望な生き残りパターンとしては、「独自の加工技術・技能を競争力の基盤とし、取引先企業に積極的な提案を行うデザイン・イン企業化のモデル」と「独自の製品技術を自らの競争力の基盤とし、自ら海外営業も行うメーカー化のモデル」とに集約されると考えられる。因みに、優れた加工技術とコスト競争力を有する部品供給中小企業群の存在は、特に摺り合わせ型産業分野で外資系企業の設計・製造拠点を日本国内に誘引し、維持すること促す「強力なインフラ」として機能することも注目すべきである。


