企業不祥事とガバナンス
昨年以来、大王製紙、オリンパス、AIJ投資顧問など企業の不祥事がメディアの関心を集め、コーポレート・ガバナンスや公的規制の強化が論じられている。
社外取締役の拡充やその独立性の向上は、企業統治改革の柱としてしばしば議論の俎上にのぼるが、企業統治に関連する諸制度を検討する際は、不祥事の抑止だけでなく企業業績や日本経済全体への効果を考える必要がある。
社外取締役の導入や増員が企業の経営成果を高めるかどうかについては、内外で極めて多くの研究が行われており、社外取締役の任命が企業価値に及ぼす効果、社外取締役の人数と利益率の関係等が分析されている(Hermalin and Weisbach (2003), Adams et al. (2010)は代表的なサーベイ論文。齋藤 (2011)は日本企業を対象とした分析の好例)。それらの結果を大胆に要約すれば、最適な社外取締役の人数や独立性の程度は企業特性によって異なり、社外取締役を増やすことが企業にとって望ましいかどうかは一概にいえない。たとえば、Coles et al. (2008)は、研究開発集約的な企業は企業特殊的知識の重要性が高いため、総じて社外取締役の比率が低く、社内取締役の割合が多いほど企業価値が高くなることを示している。Linck et al. (2008)は、成長機会の高い企業、研究開発支出の多い企業、株価収益率の変動度が高い企業は取締役の人数が少なく独立性が低いのに対して、伝統的大企業は取締役の人数が多く独立性が高い傾向があると指摘している。これらは、企業特性によって望ましい取締役会の構成に違いがあることを示している。
社外取締役と生産性の関係
「企業活動基本調査」(経済産業省)は、平成22年調査から社内・社外取締役の人数、社外取締役のうち関係会社役職員の数を新たに調査項目とした。その結果によると、取締役構成の平均値は、社内取締役が81.2%、社外取締役が18.8%となっている。社外取締役の内訳は、関係会社が57.6%と過半を占めている。
同調査のデータを用いて、社外取締役の人数・属性と生産性の間の関係を観察したところ、企業規模・業種等の違いを考慮した上で、社外取締役の数が多いほど生産性が高いという統計的に有意な関係が観察される。量的には、社外取締役の数が1人多いとTFP(全要素生産性)、労働生産性のいずれで見ても2%強高いという関係である。もちろん、この分析はクロスセクションでの単純な相関関係に過ぎず、現実には社外取締役の任命自体が内生変数なので、生産性から社外取締役という逆の因果関係も排除できない。企業業績が悪化した時に社外取締役の任命が行われる傾向があるとすれば、この数字は過小評価の可能性もある。一方、社外取締役を属性別に分析すると、関係会社の社外取締役が1人多いと生産性は4%程度高いという関係なのに対して、その他の社外取締役の場合には生産性との関係は必ずしも明瞭ではない(下図参照)。
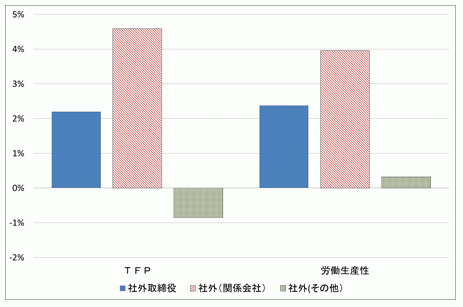
海外の経験からの教訓
以上の結果は、(1)平均的には日本企業の社外取締役が過小であり、企業が自主的に社外取締役の増員を図ることは望ましい場合が多い可能性、(2)社外取締役の属性としては、当該企業の業務に関する知見を持つ者が適切である可能性を示唆している。社外取締役の機能強化は不祥事を契機に論じられることが多いため、法律家等できるだけ独立性の高い純粋の外部の者が望ましいと思われがちだが、企業の生産性という観点からは必ずしもそう単純ではない。
米国では、エンロン社事件等を背景に2002年にSarbanes-Oxley(SOX)法および関連する証券取引所の制度改正によって、上場企業に対して独立取締役からなる監査委員会の設置を義務化する等の規制が導入された。しかし、その後のいくつかの実証研究は、SOX法が様々な副作用を持ったことを示している。たとえば、Ahmed et al. (2010)は、SOX法により企業当たり年間600万~3900万ドルのコスト増加が生じ、収益性に負の影響を持ったとの結果を報告している。Linck et al. (2009)は、SOX法が取締役数の増加と独立性の増大をもたらし、比較的規模の小さい企業において取締役報酬のコストが大きく増加したことを示している。Duchin et al. (2010)は、SOX法に伴う社外取締役の有効性は当該企業に関する情報取得コストの多寡に依存し、そのコストが高い場合には外部取締役の増員が経営成果を悪化させることを示している。さらに、Fracassi and Tate (2012)は、SOX法の結果、独立の取締役が急増したが、多くはCEOとスポーツクラブ、慈善活動などさまざまな個人的つながりを持っており、法的な独立性と実質的な独立性には乖離があることを指摘している。
社外取締役に限定された分析ではないが、最近、Ahern and Dittmar (2012)は、ノルウエーで2003年に取締役の40%を女性にすることを義務付けた法律を対象とした分析を行い、経営経験の乏しい女性取締役が急増した結果、企業価値が大幅に低下したことを示し、各企業にとって最適な取締役構成と異なる割り当てを強制することの弊害を実証している。
不祥事を契機にコンプライアンスの強化が叫ばれ、公的な規制が強化されることも少なくないが、コンプライアンス強化はコストも伴う。生産性という視点からは、企業の異質性を考慮に入れた対応が必要である。


