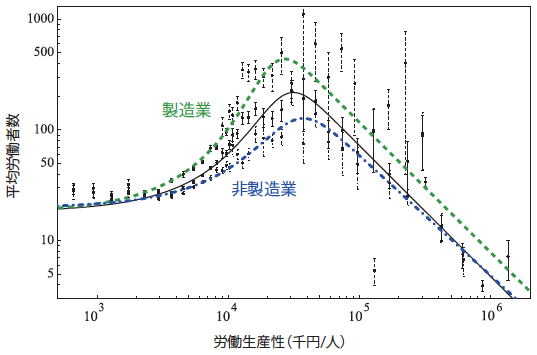| 執筆者 |
青山 秀明 (ファカルティフェロー) 家富 洋 (東京大学) 吉川 洋 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 中小企業のダイナミクス・環境エネルギー・成長 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
新しい産業政策プログラム (第三期:2011~2015年度)
「中小企業のダイナミクス・環境エネルギー・成長」プロジェクト
本論文では、企業の労働生産性と、その企業で働く労働者数の関連について、実証的および理論的研究の成果を発表した。データベースは、中小企業信用リスク(CRD)データベースと日経NEEDSを統合したものであり、大企業から中小企業まで広いカテゴリーをカバーしている。付加価値を日銀方式(加算法)で計算し、それを労働者数で割って得られる量を「労働生産性」とした。
図は1企業あたりの平均労働者数と労働生産性の関連を調べたものである。実データは誤差幅を含んだ縦棒で表してある。このような振舞いを説明する理論として、「1企業あたりに就労できる労働者数」について制限を設け、その制限のもとで確率的に分布する労働者を考えた。これによって得られる理論値が図の曲線である。その特徴として2点上げられる。第1点は労働生産性が低い企業について、労働生産性が上がると共に平均労働者数も増加する現象がみられることであり、これは、統計物理的な平衡分布において、温度が負である場合にみられる現象のアナロジーとしてとらえることが可能である。第2点は、より高い労働生産性の領域では、労働生産性が高いほど、それにほぼ逆比例して就業可能な労働者数が減少することが判明した。すなわち、高い労働生産性を達成しているのは、中小企業が中心である。
これから次のような政策課題が浮かび上がる。
高生産性企業の中心は大企業ではなく、むしろ中小企業である。なぜ大企業へと成長しないのかという問題について、こうした中小企業が成長すればより多くの労働者が高生産性部門にシフトすることが本研究から判明したことから、高い生産性を誇る中小企業を育成するための政策を推進することが重要であると示唆される。そのためには高労働生産性の中小企業への重点的支援、雇用環境の改善(就職情報提供、労働者の待遇改善等)、が必要であろう。本プロジェクトでは、高生産性の中小企業の成長を制約する要因が何であるかを解明することを、今後の研究課題としたい。