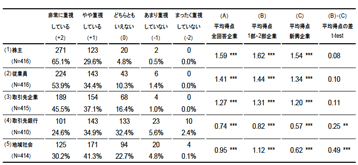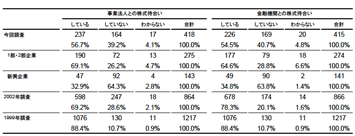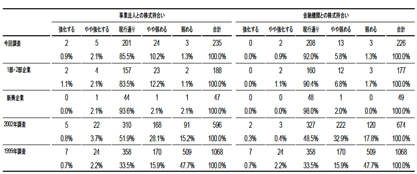経済産業研究所では、「企業統治分析のフロンティア:日本企業の競争力回復に向けて」プロジェクトの研究の一環として、2012年5月から8月にかけて日本企業のコーポレート・ガバナンスに関する包括的なアンケート調査を実施した(注1)。本コラムでは、これから6回に渡って、この「日本企業のコーポレート・ガバナンスに関するアンケート」調査(以下、本調査という)の主要な回答結果とその含意を報告する(注2)。第1回は、『神話か現実か:ステークホルダー型モデルと株式持合いの現在』と題して、本調査とYoshimori (1995) の調査を比較し、従来日本企業の特徴とされるステークホルダー型モデルの「いま」を明らかにする。
株主重視 vs. ステークホルダー重視
企業の経営目的、あるいは、「会社は誰のものか」という認識の点で、日本企業と欧米企業、特に英米企業は大きく異なると理解されてきた。図1は、これまで国内外の文献で広く引用されてきた Yoshimori (1995) の「あなたの国の大企業は株主の利益とステークホルダー全体の利益のどちらを優先して経営されていると考えますか」という質問に対する回答結果である(注3)。Yoshimori (1995) のアンケート調査は、1990年10月から12月にかけて実施されており、その回答者は東証1部に上場している製造業に属する企業の中間管理職層である。
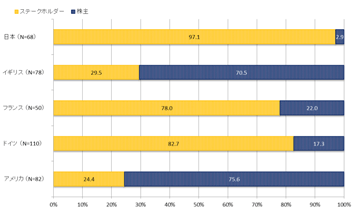
[ 図を拡大 ]
ほとんどすべての日本企業は、"株主の利益"よりも"ステークホルダー全体の利益"と回答している。フランスとドイツにおいては約2割、イギリスとアメリカにおいては約7割が"株主の利益"と回答しているのに対して、日本においてこの比率は3%にも満たない。しかし、Yoshimori (1995) の調査以降、日本企業のコーポレート・ガバナンスは大きく変化した。最大の変化の1つは、事業法人・金融機関間の株式相互持合い構造の解体と、海外機関投資家を中心とする機関投資家の保有比率の上昇であり、この所有構造の変化を背景として、わが国でも敵対的買収案件がみられるようになった。過去十数年に渡って、研究者・政策立案者・実務家・マスメディアの間では、英米型(株主重視型)コーポレート・ガバナンスの導入の是非が大きな注目を集めてきた。では、こうした変化は、実際に日本企業の従来のステークホルダー重視の経営姿勢に変化をもたらしたのだろうか。
表1は、本調査の「現在、どのステークホルダーの利益を重視していますか」という質問項目に対する回答結果である。企業には"非常に重視している"から"まったく重視していない"までの5段階で回答(評価)してもらっているが、特筆すべきは、株主を"非常に重視している"と回答した企業が271社(65.1%)にのぼり、"やや重視している"と回答した企業123社(29.6%)を合わせても、その他のステークホルダーを上回る結果が得られたことである。また、"非常に重視している"に2点、"やや重視している"に1点、"どちらともいえない"に0点、"あまり重視していない"に-1点、"まったく重視していない"に-2点を付して平均得点を求めた場合にも、(2)従業員の1.41点、(3)取引先企業の1.27点、(4)取引先銀行の0.74点、(5)地域社会の0.95点に対して、(1)株主は1.59点であり、その他のステークホルダーを上回る結果が得られた。さらに、全国証券取引所1部・2部上場企業とJASDAQなどの新興市場上場企業にサンプルを分割しても、(1)株主、(2)従業員、(3)取引先企業の平均得点に統計的に有意な差がないことが確認できる。以上の結果は、日本企業の経営姿勢が従業員などのステークホルダーに加えて、株主を重視し始めていることを明確に示している。
配当と雇用のどちらを重視するのか
日本企業は以前と比べて明らかに株主重視の姿勢を示し始めているが、では、どの程度株主を重視しているのであるか。この点に接近する1つの有効な設問は、企業が財務危機に直面した際に、配当維持と雇用維持のいずれかを選択するのかという問いである。本調査では、Yoshimori (1995) の「CEOが配当の維持と雇用の維持の決断を迫られたとき、あなたの国ではどちらが優先されると考えますか」という質問に倣って、「企業は業績悪化時に、配当と雇用のどちらを優先すべきと考えますか」という質問項目を設けた。
回答結果の比較は図2に示されている。最上段の今回調査の結果(ここでは、Yoshimori (1995) との比較可能性を考慮して1部・2部企業の回答のみを取り上げる)をみると、ちょうど9割の企業が"雇用"、残りの1割が"配当"と回答している。2段目以降の Yoshimori (1995) の回答結果と比較しても、当時の欧米4カ国よりも"雇用"と回答する企業が断然に多いことが確認できる。図掲はしていないが、新興企業において"雇用"と回答した企業の割合は87.9%である。つまり、株主重視の姿勢を示し始めた後でも、株主の利害と従業員の利害が決定的に対立した場合には雇用を優先するという日本企業の姿勢について本質的な変化は生じていない。この結果は、先の株主重視の意識の上昇が、従業員重視と代替的に進んだのではなく、並行して生じたことを示唆している。
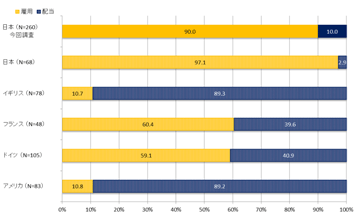
[ 図を拡大 ]
株式所有構造の現在と将来
現時点の株式持合い
日本企業の企業統治構造における様式化された特徴の1つは、事業法人間、あるいは、事業法人と金融機関間の相互の株式保有関係にあった。これが経営者に対する資本市場からの短期的な圧力を遮断し、従業員重視の経営姿勢を所有構造面から支えていた。しかし、1997年の銀行危機以降、こうした株式相互持合い・安定保有は急速に縮小した(宮島・新田 [2011])。本調査では、この10年間に急速な変化を経験した事業法人との株式持合いと金融機関との株式持合いについて、それぞれ同一の質問項目を設けて、従来日本企業の特徴とされる株式持合いの現状と今後の方針を明らかにした。
表2には、現在の事業法人と金融機関との株式持合いについての回答結果がまとめられている。企業間の持合いを実施している企業は56.7%、金融機関との持合いを実施している企業は54.5%である。成熟企業(1部・2部企業)と新興企業にサンプルを分割すると、成熟企業では、"している"("していない")と回答した企業の割合は、事業法人については69.1%(26.2%)、金融機関については64.6%(28.8%)である。他方、新興企業においては、事業法人、金融機関のいずれとの間の株式持合いについても6割以上が"していない"と回答している。
さらに、成熟企業の結果と2002年調査を比較すると、事業法人との持合いにほとんど変化がないのに対して、金融機関との持合いは78.3%から64.6%へと14%近く低下している。つまり、この10年間で金融機関との持合い解消が進展したのに対して、依然、事業法人との株式持合いは安定的である。
以上の結果は、近年の株式所有構造に関する実証研究(宮島・新田 [2011])とも一致しており、成熟企業では金融機関との持合いが低下する一方、事業法人間の持合いは維持され、全体として依然持合いが重要な役割を演じている。それに対して、新興企業では事業法人・金融機関との持合いの役割は小さいと理解してよいだろう。意識的に株式持合いを維持している企業は、概ね、1部・2部企業ではその6割程度、新興企業ではその3割程度という結果は、かつての法人優位、あるいは、株式相互持合いによって特徴づけられた日本の上場企業の所有構造が大きく多様化したことを、企業の意識面からも裏付けている。
今後の株式持合い
表3には、事業法人と金融機関との間の株式持合いについての今後の方針に関する回答結果がまとめられている。事業法人との株式持合いについて、全回答企業では、"現行通り"と回答した企業の割合は、85.5%(92.0%)を示した。成熟企業と新興企業を区分すると、"現行通り"という企業の比率は新興企業のほうがやや高く、93.6%(98.0%)である。
この結果に関して、次の2点を指摘しておこう。第1は、1999年調査、2002年調査と比べると、将来方針が大きく変化したことである。90年代末、および2000年代初頭には、"弱める"と"やや弱める"を合計すると半数を超え、この過去の調査で示された"弱める"という将来方針はその後の持合いの解消と対応していた。したがって、"現行通り"という今回の調査結果は、今後株式所有構造が安定する蓋然性が高いことを示唆している。
第2に、調査時点の機関投資家保有比率の高い上場企業でも、逆に、安定保有比率の高い企業でも、この"現行通り"という今後の所有構造に対する姿勢に有意な差がないことである。"弱める"と"やや弱める"に0を、"現行通り"に1を、"強化する"と"やや強化する"に2を与える変数を被説明変数として、現時点の機関投資家保有比率(あるいは、外国人投資家保有比率)と安定保有比率(あるいは、持合い比率)、その他のファンダメンタルな要因を説明変数とする回帰分析(多項ロジット・モデル)でも、機関投資家保有比率の高い企業が持合いを強化するという関係や、逆に、安定保有比率の高い企業が持合いを解消するという姿勢を示す傾向は確認できない。
以上の結果は、銀行危機以降に進展した「持合い解消」がほぼ峠を越えたこと、逆に、2005年以降に注目された「持合い復活」も一時的な現象にとどまったことを示唆している。わが国の上場企業の自己選択による新たな株式保有関係の形成はほぼ終了した。かつての法人優位、あるいは、株式相互持合いによって特徴づけられた日本企業の所有構造はいまや大きく多様化し、しかも、現時点では、企業は所有構造の大きな変化を望んでいない。この姿勢は、機関投資家保有比率が上昇した企業でも、逆に持合い比率の高い企業でも同様であり、今後もしばらくは、この大きく多様化した構造が維持されると推測されよう。
付録:アンケート調査の概要
本調査は「日本企業のコーポレート・ガバナンスに関するアンケート」という題目で、全国証券取引所に上場しているすべての企業に質問票を郵送した。実施時期は、2012年5月から8月である。質問票は以下の6項目から構成されている。1)企業の概要について(枝問数4)、2)経営上の基本方針について(同5)、3)株式持合いについて(同10)、4)敵対的買収・その他株主対応について(同14)、5)経営層の状況について(同8)、6)従業員の状況・人事方針について(同8)である。質問票の有効回答数は419社であり、有効回答率は11.7%(質問票郵送先は3582社)であった。
回答企業の公開市場の分布については、付録表1にまとめられている。1部・2部企業と新興企業に区分すると、前者が65.9%、後者が34.1%であり、調査票送付先企業(全上場企業)の比率である67.3%、32.7%とほぼ一致していることが確認できる。ただし、今回調査の回答企業が概ね実際の全上場企業を代表しているとみなすことができるものの、前回調査との比較では、新興企業からの回答率が高い点には注意を要する。新興市場が整備されて間もなかった1999年調査と2002年調査では、新興企業(店頭登録を含む)からの回答は、それぞれ95社(7.9%)、62社(7.1%)にとどまっていたから、本調査は、この2000年代の新興市場の整備を反映した回答状況といえる。
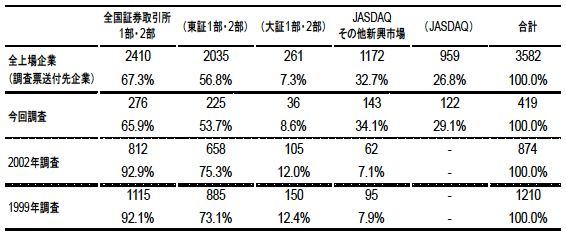
つぎに、付録表2から回答企業の業種の分布を確認する。製造業175社(比率41.8%)、非製造業244社(比率58.2%)と、非製造業に属する企業からの回答が製造業に属する企業からの回答を上回る。1部・2部企業と新興企業を区分して、それぞれを調査票送付先企業の業種分布と比較すると、1部・2部企業については実際の東証1・2部の業種分布と概ね一致しているが、新興企業については実際の業種分布よりも、非製造業に属する企業からの回答の比率がやや高いという偏りがある。また、今回調査の1部・2部企業と前回調査を比較すると、製造業と非製造業の構成比が逆転しているものの、その他に大きな変化はない。表掲はしていないが、1部・2部企業で最大の業種は、製造業では機械(24社)、非製造業では小売業(26社)であり、新興企業で最大の業種は、製造業では電気機器(8社)、非製造業では情報通信業(28社)で、サービス業(24社)がそれに次いでいる。以上、公開市場の分布と同様に、今回調査の回答企業の業種分布は実際の業種分布と大きな乖離はなく、新興市場における主要な業種が情報通信業やサービス業であるという一般的な認識とも合致している。
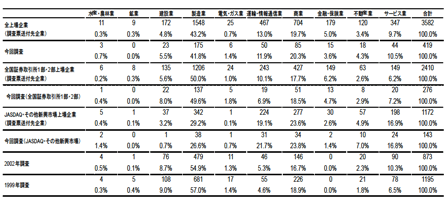
[ 図を拡大 ]