2004年の年金制度改正から2年近く経過し、年金を巡る世論の盛り上がりも一段落ついたかのように思われるが、各種世論調査を眺めると国民の年金制度への関心は高い水準にあり、未だ重要な政策課題であると認識されているといえる。経済産業研究所では、さらなる公的年金制度の持続可能性向上のための課題を研究するプロジェクトを立ち上げており、ここではその中間成果を一部紹介する。
年金制度の原理原則
メディア的な受けはあまり芳しくなかった2004年改正であるが、過去の年金制度改正と比べれば非常に重要度の高い改正であったといえる。特に、保険料水準の上限を定めることで、これまで引き上げられ続けることが予想されていた、家計および企業の保険料負担に歯止めをかけると共に、マクロ経済スライド制の導入により、年金給付総額を保険料収入と国庫負担の枠内で賄える範囲内に自動的に抑制するしくみができたことは、大きな前進であった。国内での評価に比べ、諸外国や国際機関における2004年改正に対する評価が比較的高かったのは、これらの改正内容が盛り込まれていたからであるといえよう。
勿論、これでわが国の公的年金制度に取りくむべき課題がなくなったわけではない。特に、経済情勢や出生率の変動に対応するために改正を重ねてきたことで、制度の原理原則が解りにくくなっている点は、解決すべき重要な課題である。わが国の公的年金制度は制度枠組みを変化させながら現在まで維持されてきたが、その間、給付と負担の原理原則も大きく変化した。設立当初の厚生年金は積立方式の報酬比例年金であったから、給付と負担は1対1で対応していた。しかし、インフレと経済混乱で積立方式が崩壊した後の新厚生年金法に基づく厚生年金は、定額部分をもつ二階建て制度であり、保険料率は定率であることから、制度内に所得再分配機能を持たせた年金制度として新発足したものといえる。国民年金に関しては、設立当初は夫婦2人分で標準的厚生年金加入男性と同等の給付を得られるように設計されていたが、就業構造の変化と給付と負担の著しいアンバランスが基で単独での制度維持が困難となったため、老後の生活の基本的部分をカバーする基礎年金制度へと、意義と給付設計が変更された。基礎年金導入後は、第三号被保険者制度の誕生もあり、公的年金制度内での所得再分配はよりいっそう複雑化した。
このように年金制度内で所得再分配が認められるのは、年金制度が社会保険方式に基づいて運用されていること、そして社会保険方式は、保険原理を基本としつつも所得再分配の観点から、扶助原理を部分的に取り込んで運用されるものである、と一般的に理解されているからである。保険原理のみに従えば、保険技術に基づく所得再分配(リスク分散)以外の再分配は本来許容されない。しかし、無所得・低所得の被保険者に対して扶助原理を働かせることで生活保障を行う、というのが社会保険方式の原則であるといわれる。
しかし、原則は比較的明瞭でも、実際に行われている所得再分配が明瞭ではないところにわが国の年金制度の難しさが存在する。特に、基礎年金制度導入後は、制度間・制度内、世代間・世代内の再分配が非常にわかりにくくなってしまっている。これに関連して、内閣府が平成15年に行った『公的年金制度に関する世論調査』によれば、「公的年金制度の負担と給付の関係は、働いている時に納めた保険料の実績に応じた額の年金が給付されるなど負担と給付の関係が明確なしくみであった方がよい」と思うかという設問に対し、81.1%が「そう思う」と回答しており、「そう思わない」とする者の割合7.9%を大きく上回っている。払った保険料がどの程度自分たちが受け取る給付に反映され、どの程度扶助的に使われているのが見えにくい点が、国民が抱く年金制度不信の原因のひとつになっているものと思われる。
原理原則を明確にした改正案
現実の年金制度がもつ原理原則の不明瞭さが年金制度不信の一因であるとすれば、これらを払拭するには、保険原理と扶助原理の長所を併せ持ち(即ち社会保険の原則)、かつそれぞれの原理が年金制度の構成要素に対応していることが国民に理解しやすい、年金制度の選択肢について検討する必要があろう。この目的のために検討すべき選択肢として、次の2つが考えられる。
【基礎年金全額国庫負担化】
現在の基礎年金部分の給付を扶助原理に基づく国民全体に対する最低生活保障であるものと位置づけ、その給付にかかる財源を政府の一般財源、ないし目的税による徴収に求める。
【国民年金・厚生年金統合一元化】
現行の定額給付の国民年金と二階建ての厚生年金を、報酬比例年金を基本とする新年金制度に統合し、また報酬比例年金だけでは低給付に陥る受給者には、扶助原理に基づいて国庫負担による最低保障年金を支給する。
これらの改正案を定量的に評価するために、筆者らの研究グループは新たな年金財政モデル(以下、RIETIモデル)を開発した。RIETIモデルは、枠組みそのものは保険数理の原則に従っており、したがってデータや精度は劣るものの厚生労働省の財政再計算と枠組みを共有しており、また重要性の低い項目について計算の手間を省きつつ、公表された情報のみでは計算不可能なことまで試算できるようにプログラムされている。また、厚生労働省の平成16年財政再計算の基準推計と同じ想定の下では、非常に近い推計結果を得られていることも確かめられている。以下では、上記の公的年金制度改革案を、RIETIモデルを用いて定量的に評価する。ただし、経済想定は平成16年財政再計算の基準ケースと同じであるものと仮定し、新制度への移行年次は2010年とした。
基礎年金全額国庫負担化案
基礎年金を全額国庫負担にした場合のケースを考える。この場合、これまで基礎年金勘定に拠出を行っていた厚生年金の給付設計をどのように変更するかが問題になる。ここでは2004年改正以降の厚生年金の給付水準(給付乗率)を維持しつつ、それに見合う保険料水準へ変更する場合を考える。基礎年金勘定への拠出がなくなるのであるから、その分だけ現行の保険料水準(14.288%)を緩めることができるはずである。保険料率は段階保険料率ではなく2100年までの平準保険料率を算出した。また、端点条件として2100年度の積立残高が平成16年財政再計算の基準ケースと同額になるように設定し、この条件を満たすようにマクロ経済スライドを効かせるものとした。
その結果は次の通りになった。すなわち、保険料率の水準は現行の14.288%よりも大幅に低くすることが可能であり、遺族年金・障害年金制度を制度内に保持したままで11.938%、遺族年金のみを分離して別立ての財源で賄うとすれば8.688%、遺族・障害年金両方を分離して別立ての財源で賄ってこれらを給付し、厚生年金は老齢年金だけの構造に改めるとすれば8.442%にまで引き下げることができる。現行基準では、通常の就労者の所定労働時間もしくは所定労働日数の4分の3未満の場合、厚生年金への加入が義務付けられておらず、保険料率の引き上げは正規就業者の雇用コストを押し上げ、企業が保険料を負担することのないパートタイマーの雇用を促すことになるが、これにより保険料率を引き下げることができれば、企業の正規雇用者の採用を促す効果が期待できる。
また、注目すべきは遺族年金を分離した場合の保険料率の下げ幅が非常に大きい点である。基礎年金を国庫負担化することで、所得再分配機能をもつ一階部分と、給付と拠出が1対1対応をもつ報酬比例の二階部分を明確に分離することができるが、このような給付と拠出の1対1対応をもつ年金制度には遺族・障害年金はなじみにくいという側面がある。近年、日本でも評判の高いスウェーデンのNDC制度では遺族・障害年金は制度から分離されている。遺族年金という生命保険的な機能を年金保険制度内でどこまで維持すべきかという点は、わが国とスウェーデンの女性就業率および賃金格差の違いを鑑みれば多大な困難が予測されるが、今後もっと議論されてよい論点である。
次に、基礎年金部分の全額国庫負担化が行われた場合の必要額の試算結果を示す。現行制度では基礎年金給付にかかる支出は、国民年金勘定、厚生年金勘定、共済年金勘定からの拠出と国庫負担(2009年度以降は2分の1)で賄われている。ここでは、2010年以降について既に国庫負担で賄われることになっている2分の1は予定通り一般財源でカバーし、各年金勘定の保険料収入から拠出されている分(即ち基礎年金給付総額の2分の1)を年金目的消費税を財源として賄った場合の必要消費税率を試算した。
必要な消費税率については、制度変更当初は4%未満の消費税率で賄うことができるが(図1)、2030年以降、必要な消費税率は増加し、2050年ごろには6%以上を課す必要がある(現在既に課せられている消費税率は据え置いているため、現行の5%消費税に対する追加的税率であることに注意)。2030年以降消費税率が急速な伸びを示すのは、団塊ジュニアの世代が労働市場から退出し、扶養比率がさらに高まり始めると共に、国庫負担化によって未納・未加入問題が解消し、納付率が100%になるのと同様の状況となるため、基礎年金を満額受給する世代が増えていく効果が影響しているものと思われる。
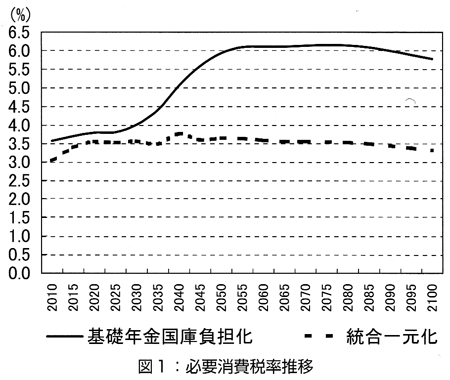
厚生年金・国民年金統合一元化案
ここでは、厚生年金と国民年金の統合一元化案を検討する(年金の一元化という用語には様々な意味が含まれるため、以下では統合新年金と呼ぶ)。統合新年金の基本形は、完全所得比例型の年金制度とする。保険料率については、現行の厚生年金の引き上げスケジュールと同じ保険料率が適応されるものとするが、現行の第一号被保険者(国民年金)・第三号被保険者は、所得がない場合には保険料を納める必要はない。一方、完全所得比例型受給額の計算方式は、現行の厚生年金の報酬比例部分同様、所得水準と加入期間に比例するものとする(遺族・障害は分離)。このような制度のもとでは、給付と拠出が1対1で対応し、所得(保険料拠出)が2倍であれば2倍の年金を受け取ることになる。
前記のように計算した所得比例年金受給額が、現行の基礎年金の水準に満たない場合には、所得比例年金とは別途、最低保障年金を受給できるものとする。最低保障年金として受け取る受給金額は、現行の基礎年金の水準と所得比例年金受給額との差額であるものとする。即ち、最低保障年金を受け取る場合には、一律に現行の基礎年金の水準の年金額が保障されているものとする。また最低保障年金給付にかかる財源は保険料ではなく、全額国庫負担によるものとする。また、統合新年金制度の初期の積立金は、2009年末の厚生年金と国民年金の積立金(厚生労働省予測)を合算したものとする。一方、端点条件として2100年度末の積立金は2100年の支出と同額になるものとする。
厚生年金被保険者・受給者(通算老齢年金含む)に関しては、2010年に新制度に全員が移行するものとする。一方、国民年金被保険者は、1970年生まれ以降が2009年度以前の履歴を切り捨て新制度に移行するものとし、それ以外は旧制度のままとする。旧制度にかかる収支に関しても、統合新年金の収支に含めている。旧制度の受給額にかかる国庫負担は、現行制度(2009年以降)と同様2分の1とし、最低保障年金にかかる国庫負担と合算している。
試算結果については、給付乗率は11.522(対総報酬、現行5.481)と遺族・障害年金を制度から分離しているため、総じて高い水準を持つことができる。さらに、最低保障年金と移行期の国民年金給付の2分の1を賄うための国庫負担金については、基礎年金国庫負担化に比べ最大でも3.8%程度の消費税負担で賄えると試算された(図1)。これは、基礎年金国庫負担化案が高額所得者にも基礎年金を給付するのに対し、統合一元化案では国庫負担による給付を低額所得者のみに限り、所得再分配効果を可能な限り低く抑えることから生じる違いである。
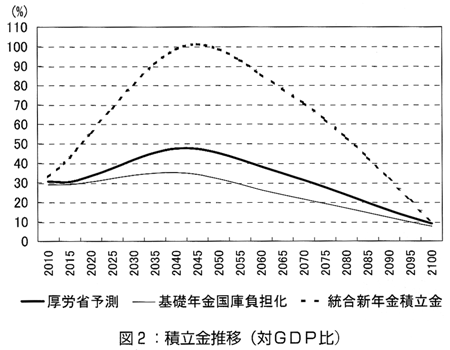
ただし、統合新年金の積立金の推移(対GDP比)をみると(図2)、国民年金加入者にも所得比例年金をベースとする統合新年金へ移行を行うことにより、経済内に占める年金制度の割合は大きく上昇し、最大でGDPに匹敵する積立金が積み上がることになる。これは現行制度で予測される積立残高の約2倍の水準であり、年金制度が資本市場に与える影響は、相当に大きなものになることが予想される。これだけ積立金が増大するのは、保険料率を2004年改正のスケジュールに合わせたことの結果である。平成16年財政再計算の特徴の1つは、保険料率を早めに引き上げることにより2045年ごろまで積立金をなるべく積み上げておいて、残り半世紀をこの積立金を取り崩すことで乗り切る点にあるが(有限均衡方式)、仮に、国民年金制度を厚生年金制度に吸収する形で統合すれば、新制度もこの性質をそのまま引き継ぐことになる。急速に高齢化が進むわが国において、世代間で負担をなるべく平準化しようとすれば、保険料率を早めに引き上げ固定する必要があるが、そのために積み上がる積立金の規模は相当なものになることが予想される。とすれば、GDPに匹敵する規模の積立金を、どのようなポートフォリオを組み管理・運用すればよいのかということが重要な論点となろう。
以上、年金制度の原理原則を明確にした制度改正案を試算し、その場合の課題について考察した。ただし本稿では、被用者年金のうち共済年金に関しては、データの制約から分析に反映させることができなかった。ここ数年、急速に共済年金に関する情報公開が進んできており、利用可能なデータも広がりつつあることから、モデル内に共済年金制度を導入することが今後の課題と考えている。


