3月25、26日、南アフリカ(2025年G20議長国)のプレトリア大学で開催された国際会議"Convening on Carbon Pricing, CBAM and Green Transition"に主催者から(RIETI経由で)招待を受けて参加した。
主催者は、African Tax Institute、J-PAL(貧困撲滅研究目的の世界の大学のネットワーク)、Climate Action Platform Africaで、ゲイツ財団が会議開催のスポンサーであった。中心的に企画、実行に当たったのはMIT、ハーバード、UCLA等の教授たちであり、その目的はいかに炭素価格制度を広めるかというものであった。
この会議には世界各地から約40名の専門家(政府、国際機関、産業界、大学、シンクタンク等)が集まり、チャタムハウス・ルールのもとで議論が行われた。
参加者の所属国は、南アフリカ、モザンビーク、ケニア、ナイジェリア、ウガンダ、シェラレオネ、エジプト、モロッコ、トルコ、ベルギー、オランダ、米国、ブラジル、インド、タイ、マレーシア、インドネシア、豪州等非常に多彩であり、日本から参加したのは筆者一人であった。 肝心のEU当局は当初の参加者リストにはあったが、結局参加していなかった。
まず、CBAM(炭素国境調整メカニズム)の現在位置を紹介しよう。
CBAMは、2021年に欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長によって発表されたFit for 55政策パッケージ(GHG排出の2030年55%削減を目指すための数々の措置)に含まれたもので、EU-ETS(排出量取引制度)を補完する措置として、EUへの輸入品に対して当該品目のEU内炭素価格とその輸出国での炭素価格の差分を輸入者が支払わなければならないという制度である。俗に炭素関税とも呼ばれる。
これは、EU-ETS対象分野の産業のカーボンリーケージ(EU域外への生産移転)を防止するためのもので、鉄鋼、セメント、アルミニウム、肥料、電気、水素が対象とされた。
その実施は、2023年10月から移行期間として、輸入者は当該品目の炭素含有量を報告する義務を負い、2026年1月からは本格施行として、実際の差額負担賦課が始まる。
また、英国がCBAMを2027年から導入することを発表している。これはEU以外では初めてである。米国でも以前議会でCBAM導入の法案(Clean Competition Act)が提出されたり、バイデン政権時代にCBAM導入の検討がなされたが、現在のトランプ政権ではその見通しはない。
EUのCBAMは、制度の発表以来(もしくはそれ以前の検討段階から)世界のEU貿易相手国に大きな衝撃を与え、その制度の是非をめぐって大きな政策論争を巻き起こした。
各国ともその自国への影響を分析しつつ、対応措置が検討されている。中にはその貿易制限的な性格をめぐってWTO提訴を示唆する国もある(EU側はCBAMはGATTルールを遵守していると主張している)。
EU-CBAMについては、日欧産業協力センターとして政策セミナーやポリシーインサイト(政策レポート)で取り上げており、また筆者もコラムを投稿しているので、それらを参照ありたい。
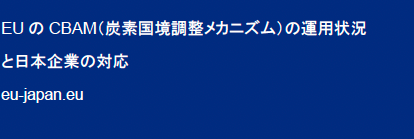
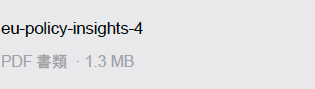
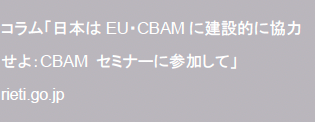
以下、今回の会議の議論に参加した上での筆者のテークアウェイ、所感を述べることとしたい。
第一に、CBAMというイノベーティブな政策を打ち出したEUの構想力、実行力、そしてそのインパクトの大きさに改めて感心させられる。
今回集まった専門家の顔ぶれを見ても、その所属国のカバレッジ、専門分野の範囲(気候政策、貿易政策、財政政策、開発政策、経済学、国際政治学等)の広さに驚かされる。それだけCBAMは、政策ベンチャーとして世界の多くの国々の関係者に対して学際的なインプリケーションをもたらしているということである。
今回の議論を聴いていても、さまざまな角度からの参加者の意見に対して、かつて関連政策立案の立場に身を置いた者として知的刺激を感じざるを得なかった。
CBAMというボールを投じて世界に波紋を拡げたEUの影響力の強さを改めて認識した次第である。まさに「ブリュッセル効果」の面目躍如といったところであろう。
第二に、CBAMへの反応には温度差があることが確認された。
今回は場所柄アフリカ諸国関係者が多く参加していたが、彼らは概してCBAMに対して警戒的・批判的である。
彼らの主張を要約すると、①EUによる一方的措置であり多国間主義に反する、②環境保護の名の下の保護貿易主義である、③パリ協定での「共通だが差異のある責任」(CBDR)の原則やJust Transition(公正な移行)の考え方に反する、といった論拠である。
特に筆者にとって新鮮だったのは、今回財政政策関係者が多く参加していたためか、EUが途上国製品に対して課税するのは税収を通して富の逆移転だとの主張である。
ただ、この点はEUの狙い通りに働く可能性もある。すなわち、EUに税収を取られるぐらいなら、逆に輸出側で課税をして輸出側の税収にしようとの案も国によって検討されているようであるが、これはEUが狙っている炭素価格制度の世界的な普及につながる可能性があるからである。
アフリカ諸国としてはEUに対する不満を持ちながらも、独自の炭素価格制度の導入に向けて検討が進められていることも紹介されていた。
他方、インド、東南アジア、豪州、ブラジルの参加者からは、CBAMの自国の対EU輸出への影響を測りつつも、CBAMを機に、自国の炭素価格制度を構築、実施しつつあることが紹介された。日本もそのようなグループに入るであろう。
これは、概してアジア諸国からEUへのCBAM対象分野の輸出が大きくなく、従ってその影響も大きくないという事情を反映していることもあろう。
CBAMのアジア太平洋諸国への影響については、RIETIの有村俊秀ファカルティフェローとモルタ・アリン氏の分析が参考になる。
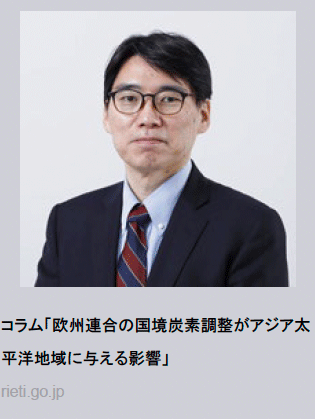
なお、会議の中で紹介されていたが、世界銀行はCBAM Exposure Indexという指標を開発した。これは、ある国のCBAM対象品目の炭素強度とその対EU輸出からその国へのCBAMの影響度を見るという指標である。
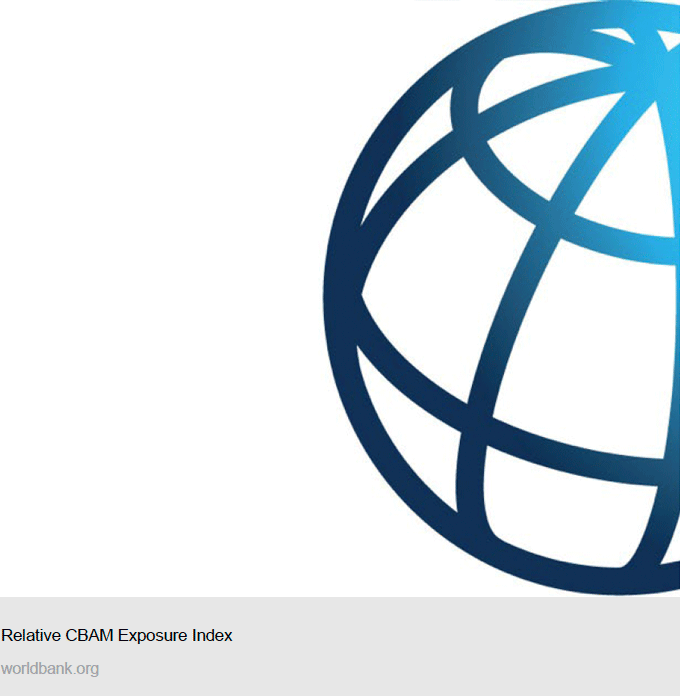
また、EU-CBAM制度の問題点として、直接炭素価格(キャップ&トレード型のETSか炭素税)しかカウントしない点をあげ、間接的炭素価格(脱炭素化投資支援金等)も含めるべきとの主張もあったが、それは(どこまで含めるかの)パンドラの箱を開けることになるとの反論もなされていた。
また、制度の別の問題点として、MRV(計測、報告、証明)のための管理的負担・コストが多大で、欧州のコンサルタントのビジネスを増やすだけではないかとの指摘もあった。これに対して、最近報告義務者を90%削減し多くの小規模輸入業者は義務から除外されることになった欧州委員会による簡素化策が紹介され、また2026に予定されるCBAM制度のレビューにおいてさらなる簡素化策に期待しようとの指摘もあった。
第三に、日本としてはEUに建設的に協力して、世界的な炭素価格の普及、炭素市場の形成に努めるべきである。
炭素価格は、経済学的にみて最も有効な排出削減政策ツールであることが認められている。であるからこそ、世界銀行もWTOも世界的な炭素価格を目指すべきだとしている。今回の会議の狙いもそこにあった。世界的な炭素価格を目指す際に前例としてグローバル税制合意を参考にすべきとの指摘もあった。
世界銀行によると、炭素価格(排出量取引、炭素税)を導入している、あるいは導入を検討している国々は世界の排出量の24%を占めている。
2024年の炭素価格の現状と動向
大排出出国で炭素価格制度を導入していないのは米国、ロシア、サウジアラビアぐらいのものである(米国でもカリフォルニアなどの州は排出量取引を導入している)。この状況から、G20ではなくG17が中心になって進めるべきだとの主張もあった。
日本でもGX戦略により、2026年からのGX-ETS、2028年からの化石燃料賦課金(実質的な炭素税)の導入が決まっている。
アジア太平洋地域でも、中国、韓国、タイ、マレーシア、インドネシア、豪州、インド等で何らかの炭素価格制度の導入が決まっているか検討中である。
このきっかけを作ったのは明らかにEUのCBAMである。今回参加したある学者によれば、CBAMは炭素価格という囚人のジレンマ状況に対する解決策であるということである。
日本とEUは2021年に初めてグリーン・アライアンスを形成し、気候政策の対話に努めている。この中でCBAMについても協議が行われている。
2023年11月に欧州委員会のトーマス気候行動総局長が来日して日本政府と協議を行った際に日欧産業協力センターとして冒頭紹介したセミナーを開催した次第である。その際にはEU側から日本に対してCBAMへのサポートの要請がなされていた。日本はEUにとって信頼に足る同志国であり、EUとして味方を多くしたいとの気持ちの表れであった。
日本として当面まず目指すべきは、日本のGX政策がEU-ETSと同等で十分な制度であること(adequacy)を確認して、日本からの対象製品の輸出に対してCBAMが賦課されないようにすることである。これには、EUのGDPR(一般データ保護規則)導入の際の十分性の確認の前例が参考になろう。
その上で、日本はEUとともに、そのような確認作業の実績をもとにアジア太平洋諸国、さらには世界に向けて炭素価格制度の普及、そのルール(MRV等)の相互運用可能性の確保を目指すべきである。
言い換えれば、EUの言うCBAMが目指すlevel playing fieldを世界に拡げるべきであり、フラットな世界を目指すべきである。そして取引コスト・管理コストの最小化を目指すべきである。
今回の議論を通して感じたのは、EUとアフリカ諸国の間にはなお相互信頼の足りない関係があるということである。
それに比べて日本とEUには相互信頼関係があり、また、日本はアジア太平洋諸国の信頼を得ている。今回も、日本が主導するアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)への賞賛の声が聞かれた。また、筆者が紹介した日本のGX戦略の導入、実行のプロセス(20兆円の政府資金を産業界の脱炭素化に投じて150兆円の官民投資を促しつつ、炭素価格制度を導入するという「アメとムチ」の政策)は多くの参加者の関心を集めていた。
日本はこのような立場を生かして、世界のルールづくりをEUとともに主導すべきである。幸い筆者のこの主張に同調する立場を示す識者もいた。
このプロセスでは、AZECの取り組みを活用し連動すべきである。
また、併せて、パリ協定6条(排出削減量を国際的に移転する市場メカニズムが規定されている)も含めた炭素クレディット市場の形成をも生かすべきである。
つまり、日本国内でアメとムチによりGX戦略を進めるプロセスと連動するように、アジア太平洋地域で脱炭素投資を促す官民の資金の流れを確保するというアメとともに、炭素価格制度の導入・実施というムチを働かせるべきである。
このような形で日本がアジア太平洋地域から始めて世界的な炭素価格の導入・普及にリーダーシップを発揮することはEUの望むところであり、日EUグリーン・アライアンスの代表的なユースケースとなるであろう。
これこそが、筆者が標榜する「ブリュッセル・東京効果」の模範事例になるであろう。
(上記は筆者の個人的見解であり、所属する組織の公式見解を代表するものではないことをお断りしたい。)


