一昨年末の政権交代により政権運営の安定性は格段に増した。つまり、政治状況は「決められない政治」から「決められる政治」へと好転した。当時の全国紙は、安定した政治基盤が築かれたことで政府・与党は懸案の政策に取り組むことができるようになったとして、政治の安定性の回復を高く評価した。
ところで、経済産業研究所が2011年末から2012年2月にかけておこなった約3400社の企業へのアンケート調査では、それらのうち33%の企業が経営に重大な影響を及ぼす要素として政府や政策の安定性を選んでいる(注1)。この結果は、政治の不安定性が企業の生産計画や設備投資計画の策定に影響することを通じて実体経済と関わり合いを持ち得ることを示している。
そのことを踏まえ、なかには次のような疑問、すなわち昨年の政治の安定性の回復はいったい実体経済にどう影響するか? が湧いて来た読者が少なくないかもしれない。しかし、残念ながらその点に着目して定量的な評価をおこなったレポートはあまり見当たらず、したがって読者がその疑問を解決するのはそう簡単ではないかもしれない。
このコラムでは、そのことに関心を持つ読者の一助となる材料を提供するという動機から、新たに試作された政権運営の不安定性指数を用いておこなったシンプルなデータ分析から得られた、暫定的だが興味深い研究結果を紹介する。
政治の不安定性をいかに測るか?
政治の不安定性が実体経済に及ぼす影響を定量的に評価するときに付きまとう問題は、政治の不安定性をどのようにして測るかである。既存の実証研究では政府要人の暗殺者数や政権交代の頻度といった変数が政治の不安定性指標として利用されてきた。しかし、現在の日本においてそのような事例は皆無か、あったとしてもごくわずかであり、したがってそれらの変数は政治の不安定性指標としてふさわしくないかもしれない。
また、代替的な変数の候補として議会における議席数が挙げられる。議会における与党の議席数が野党のそれを大きく上回るとき、政権運営は安定的であるとみることも可能だと思われる。しかし、2012年に起こっていた現象が1つの好例として挙げられるように、与党が相当な数の議席を保有していても政権運営に窮する事態が発生し得る。この場合、政治の安定性は低いととらえるほうが自然である。したがって、議会における議席数は政治の不安定性指標として適当ではない。
前述された弱点を補い政治の不安定性指標として利用可能と考えられる有力な変数の1つは、新聞社、テレビ局そして通信社が毎月実施する世論調査のなかで報告される政党支持率である。図1は1993年1月から2014年1月までの期間における政権運営の不安定性指数(以下ではiPM指数と呼ぶ)を示している。
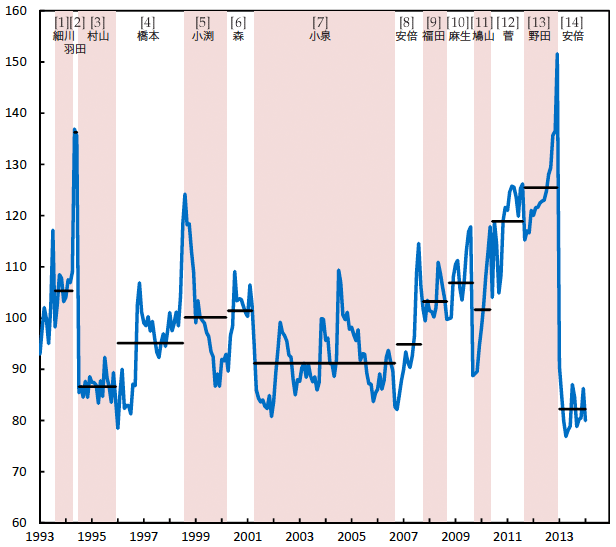
この指数は、時事通信社、NHK、NNN、ANN、JNN、FNN、朝日新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社そして読売新聞社より公表される政党支持率のデータを加工処理したのち、そうして得られた10系列を加重和(ウェイトは一定)して導出されている。支持率でみた与野党の伯仲度合いが高いと指数の値が大きくなる。与野党が伯仲する状況下では、政府・与党は野党の激しい攻勢に晒されるため円滑な政権運営をしにくくなる。指数の上昇は政府・与党が政権運営に行き詰まる、すなわち政治の不安定性が高まっていると解釈することができる。
図を見ると、iPM指数は過去20年のあいだ上下変動を繰り返しながら推移している。先月の指数は80であり、歴史的にみて低い水準にある。歴代内閣で比較してみると、現在の内閣は細川内閣以降で政治の安定性がもっとも高い状況下にある。
より詳しく見ると、指数が前月比で30ポイント以上も激しく動いたときが3度あり、それは1994年7月、2009年9月そして2013年1月である。いずれのときもその直前では政府・与党の政権運営がかなり苦しくなり、政局は不安定であった。そのあと政権交代が起こり、政治の安定性が取り戻されている。
また、指数は2007年から上昇トレンドを示しており、政治の不安定性が持続的に高まっている。同年7月の参議院議員選挙で自民党が惨敗し、与党が参議院で議席の過半数を失った結果、国会では衆参のねじれ現象が発生した。当時、ねじれの発生が政治の不安定化を招くことは不可避と危惧されたが、指数はその点を如実に表している。
政治の不安定性と実体経済との関係
前節ではiPM指数が政治の不安定性をまがりなりにも示していることがわかった。ここでの大きな関心事は、その指数と実体経済変数とのあいだに関係があるかどうかである。図2は内閣別データを用いてiPM指数と実体経済変数の散布図を描いている。実体経済変数には雇用者数伸び率と経済成長率を使用している。
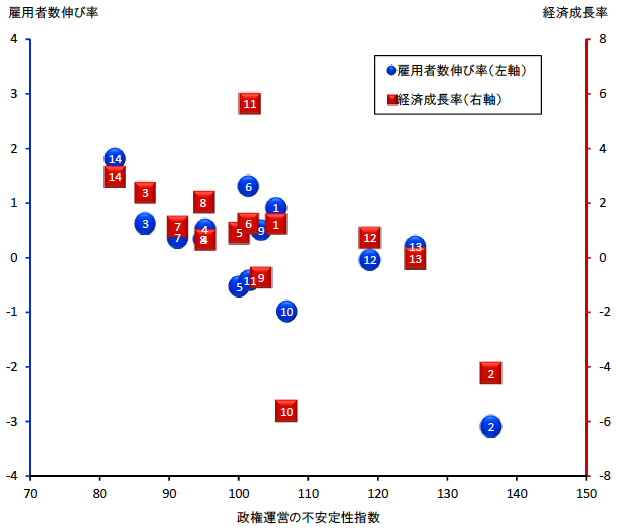
図からはiPM指数が低い、つまり政治の安定性が高いとき雇用者数伸び率や経済成長率も高いことが見て取れる。政治の不安定性と実体経済のパフォーマンスとのあいだには負の相関がある。この事実は、政治の不安定性が企業行動の意思決定に影響することを通じて実体経済と関わり合いを持ち得るという、前述のアンケート調査の結果を裏付けているように見える。
しかし、その負の相関は、雇用者数の伸び悩みや経済成長率の低迷といった実体経済の不調が政府・与党への不支持を醸成し、結果的にiPM指数が高まったことを示している可能性がある。その可能性を検証するために用いられる方法の1つは、時間間隔がより短い四半期データの利用である。図3はiPM指数と実体経済変数の時差相関係数を示している。なお、実体経済変数にはトレンド除去された雇用者数と実質GDPのデータを使用している。
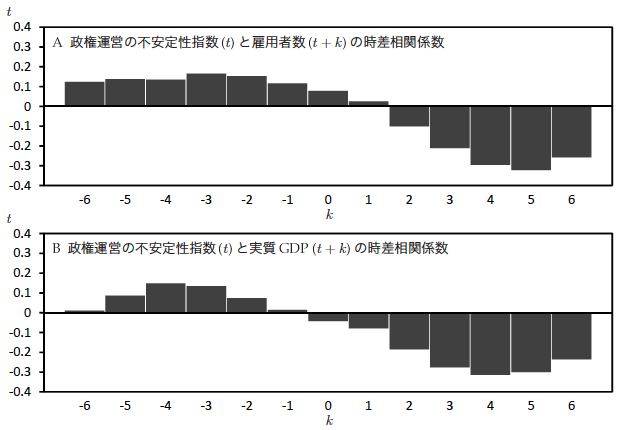
パネルAはiPM指数と雇用者数との時差相関係数を示している。ある時点のiPM指数はそれより4-5四半期先の雇用者数と相関が高い。政治の不安定性が雇用者数の伸び悩みに起因しているとすれば、ある時点でのiPM指数はそれより前の時点の雇用者数と負の相関があるはずである。しかし、図からそのことは確認されない。実質GDPについても同様である(パネルB)。
政治の不安定性が実体経済へ及ぼす影響の定量的な評価
前節では、ある時点の実体経済変数はその時点より前のiPM指数に依存していることを確認した。それでは、政治の不安定性の予期されなかった変化(ショック)は体経済にどう影響するか? そのことを調べるために、図4は、iPM指数、実体経済変数、短期金利そして株価の4変数からなる多変量自己回帰(VAR)モデルを推計し、その得られた結果をもとに政治の不安定性ショック(iPM指数の10ポイント上昇に相当する規模)が発生したときの実体経済変数のインパルス応答関数を描いている。実体経済変数として雇用者数と実体経済活動指数を使用している(注2)。
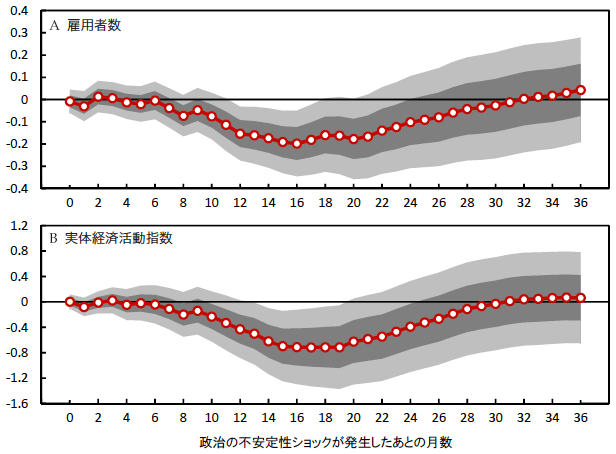
パネルAを見ると、ショックの発生により雇用者数は徐々にトレンドから乖離して減少していき、16カ月後に0.2%のピークに達したあとトレンドへ戻っていく。マイナス効果はショックが発生したあと1年から1年半のあいだで統計的に有意である。パネルBを見ると、ショックはその発生から13-19カ月後に実体経済活動指数に対して有意な負の影響を及ぼし、17カ月後においてその影響が最大(0.7%)となる。
モデルより識別された政治の不安定性ショックにもとづき算出した結果によると、一昨年末の政権交代に伴う政治の安定性の回復は雇用者数を今年上半期に0.9%増加させたり、実体経済活動指数を今年の第2-3四半期において3.1%増大させたりするインパクトがあった。4月に実施される消費税率の引き上げは実体経済にマイナスの影響を及ぼすかもしれない。しかし、政治の安定性の回復がもたらすプラスの影響が実体経済の落ち込みを多少なりとも和らげると見られる。

