ソロー・パラドックスと無形資産
ソロー・パラドックスという言葉をご存じだろうか。ノーベル経済学賞を受賞したRobert Solow (MIT教授)が87年に"We can see the computer age everywhere but in the productivity statistics"と述べ、米国において80年代に急速にIT化が進んだにもかかわらず、なぜ生産性上昇が統計数字に表れないのかと問いかけた「謎」のことである。90年代後半になってようやく米国の生産性は上昇を示したが、多くの経済学者がこの経済事象の解明にチャレンジし、その結果、IT投資が無形資産(Intangibles)の一種である組織資本や人的資本の蓄積と結びついたときにタイムラグをもって生産性や企業のパフォーマンスが向上することが明らかにされた。たとえばErick Brynjolfsson (MIT教授)は、企業の大規模IT化プロジェクトにおいて、組織資本(業務プロセスの再設計・再構成)や人的資本(ユーザー教育)への資金投下は全体のコストの8割(ハード投資額の約9倍)を占めており、そのような配分を行った企業は3~7年以上の期間を経て効果を上げていることを実証分析し、組織・人的資本の重要性と投入されるべきコストの大きさについて指摘している。そして、07年の米国大統領報告において「企業は、IT投資を補完する無形資産の蓄積を行ったときだけ生産性を実質的に上昇させることができる」と記され、学界のみならず一般にもその認識が定着されるに至っている。
無形資産(組織資本・人的資本)の定量的把握
わが国の物的なIT投資は、最近ようやくドイツやフランス並みの水準に達しているが、経済全体の生産性上昇率は伸び悩んでいる。(http://www.euklems.net/)。米国での議論を考慮すると、日本でも組織資本や人的資本の蓄積が不足している可能性がある。Fukao et al (2008)において、Corrado, Hulten and Sichel (2005,2006)の手法に従った推計により日本はコンピューター等情報化資産投資やR&D投資など革新的資産投資に関しては欧米を上回るが、組織資本や人的資本を含む経済的競争能力投資では大きく下回っていることが明らかにされており、少なくともマクロレベルで無形資産投資が不足している可能性が示されている。しかし、ミクロレベルでは、企業の無形資産の蓄積や無形資産の企業パフォーマンスへの影響に関する検証は現在のところ十分に行われているとは言い難い。企業の組織資本・人的資本の蓄積が会計上はほとんど全て他の費用と紛れて費用計上されており、また資産計上されることもないため、外部からは極めて把握が困難なのである。先述したBrynjolfssonや後述するBloom and Van Reenen (2007)など海外での先行研究においてもこの点は同様であり、彼らは企業ヒアリングやアンケートによりデータ収集を試みている。
少子高齢化が急速に進むわが国では、経済成長を維持するために生産性の向上が不可欠であり、組織資本・人的資本の増加が生産性向上をもたらすのであれば国のリソースを投じて組織資本・人的資本の促進を図る必要があろう。しかし、国民および政策立案者がこのような意志決定を行うためには、まず現在の日本企業が採用している経営管理手法が、組織資本・人的資本などの無形資産を蓄積するために適しているかどうかを検証する作業が必要だ。
東京地区151社のインタビュー調査
RIETIは、07年から宮川努学習院大学教授をリーダーとする「日本における無形資産の研究」プロジェクトを立ち上げている。同プロジェクトチームは、Bloom and Van Reenen (2007)のヨーロッパの製造業事業所を対象とした電話インタビュー調査を参考に、組織目標の企業理念との整合性および組織内外への浸透度、組織変革の度合いや組織改革(大規模な変革)時期、ならびに採用・評価等人事政策や人材活用における柔軟性などについてスコア化可能な質問票を作成し、製造業で4業種(電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、自動車・同付属品製造業、精密機械器具製造業)、サービス業で3業種(映像・音声情報制作業、情報サービス業、小売業)に属する企業1145社を対象に訪問インタビュー調査を実施している。
昨年12月には、先行して回答回収を行った東京地区258社(回答社数151社)を対象に、スコア分布およびスコアと企業パフォーマンスとの相関に係る分析を暫定的に行い、その結果をRIETIディスカッションペーパーとして取り纏めている。その結論の概要は、(1)単純な平均スコアと企業パフォーマンスとの間に有意な関係は見られない、しかし(2)組織改革後2年を経過した企業では、スコアが高ければ企業パフォーマンスを上げる効果があるというものであった。
経営改革と企業パフォーマンス
平均スコアと企業パフォーマンスに相関が見られなかったのはなぜだろうか。最も大きな理由は、企業パフォーマンスにかなりの相違が見られるにもかかわらず、各企業は同じような組織管理や人的管理の手法を取っているという点にある。この日本企業の同質性という特徴は、今回の世界金融危機で実体経済が最も大きく影響を受けた国の1つが日本であることと関連しているかもしれない。しかし、これら要因以外にも、結論(2)にも触れられているタイムラグが大きな影響を及ぼしている可能性がある。
経営改革の目的は、一般的には売上増かコスト削減による利益増である。そこで、売上高と営業利益率を指標として経営改革時期を中心に前後3期における変化を見てみると、両指標ともに3期前から低下し、経営改革実施期を底に上昇に転じ、2~3期で復するか上回る水準に達している(図参照)。経営改革前の下降局面では因果関係(業績悪化を背景に経営改革着手したのか、あるいは経営改革着手により本来業務にリソース不足が生じ業績悪化したのか)の確認は必要だが、改革後の上昇カーブは新たな組織体制に組織構成員が馴染むのに時間を要するため漸次上昇するということが企業ヒアリングからも分かっており、経営改革期を底に企業業績がU字を描くことは説得的である。今回の分析対象企業のうち約半数は05年以降に経営改革を行っており、それら企業の業績が下降局面に入っている可能性がある一方で、08年時点のスコアは少なくとも07年までの経営改革を反映したものとなっているので、スコアの高さと企業パフォーマンスとの間に相関が見られなかったとのディスカッションペーパーでの結論は理解できよう。
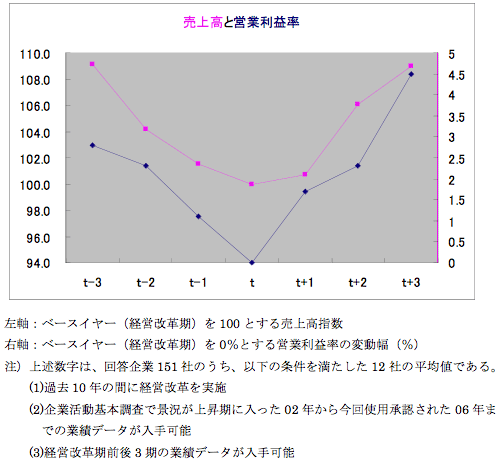
現在、プロジェクトチームは東京地区以外のデータ、インタビューと同時並行して実施された人事部アンケート調査およびIT関連情報を加えた分析に着手しており、新たな或いはより頑健な分析結果を創出しているところである。新たな知見が得られ次第、本コラムまたはシンポジウムなどのイベントにおいて多くの方々と情報共有したいと考えている。



