競争が激化する中で我が国企業が「勝ち組」と「負け組」とに二極化してきたという議論がある。たとえば、自動車産業ではトヨタが最高益を更新し、日産が業績を大幅に改善する一方で、三菱自動車は苦境が続いている。しかし、昔から業績の良い企業と悪い企業は存在した。グローバル化や規制緩和によって競争が激化したとすれば、非効率な企業は効率性を高めざるを得ず-あるいは撤退を余儀なくされ-企業間の業績のばらつきは小さくなるかも知れない。
利益率のばらつきは拡大していない
日本企業の業績が最近「二極化」してきたのか、以前から同様の格差が存在したのか、日本企業のマイクロデータを使用して検証した。具体的には、「企業活動基本調査」平成4年~14年の個票データ(対象年度は平成3年度~13年度)を使用し、利益率、売上高伸び率等の「ばらつき」が経年的に拡大しているかどうかを計測した。
全サンプル(各年2.5万~3万社)を対象に売上高経常利益率、総資産経常利益率の標準偏差を計算した結果が図1である。いずれの指標で見ても利益率のばらつきが傾向的に拡大しているとは言えない(統計的に非有意)。素直に見れば利益率のばらつきは非常に安定的である。
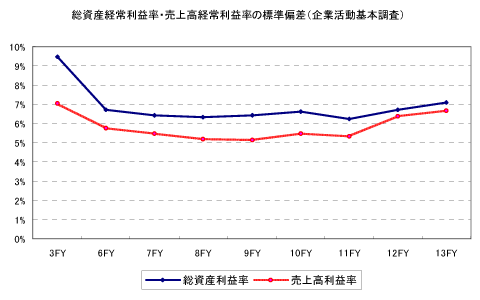
対象を製造業に限定して利益率の標準偏差を計算しても全体のパターンとほぼ同様だった。さらに、製造業主要業種別に同様の計算を行ったところ、輸送機械はばらつきが縮小、電気機械は最近やや上昇など業種によって違いがあるものの、ごく一部の業種を除いて利益率のばらつきは縮小傾向にある。すなわち、以前から「勝ち組」企業と「負け組」企業はあり、少なくとも1990年代以降、業績格差の拡大が進行しているとは言い難い(ただし、ごく最近の時期についてはデータがアベイラブルではなかったため確たることはいえない)。
企業の「浮き沈み」は激しくなっている
それでは、売上高の伸び率、利益率の上昇・下落といった「変動」についてはどうだろうか。「企業活動基本調査」のサンプル企業の中には、参入・退出、統計の裾切り、業種転換などの理由で継続して対象となっていない企業も多い。前年比での「変化」の経年的な推移を観察するためには、継続してサンプルとなっている企業を対象とすることが望ましい。このため、平成7年調査~14年調査まで継続して存在する企業のデータを接続して分析した。
計算の結果、図2に示す通り、売上高の前年比変動(自然対数の前年差)のばらつきは明らかに拡大傾向にある。利益率の前年差で同様の計算をすると、売上高の変化ほど明瞭ではないが、やはり最近になるほどばらつきが拡大していた。
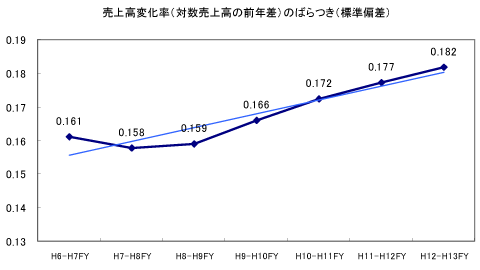
分析対象期間が短く、一般化するには慎重でなければならないが、少なくとも1990年代以降比較的最近まで、売上高や利益率の「変化」のばらつきが拡大しているということは、従来業績の悪かった企業の業績が急に回復したり、好調だった企業の業績が急に悪化したりする傾向が最近になるほど顕著になっている-「浮き沈み」が激しくなる傾向-可能性を示唆している。ただし、年々の業績の浮沈が激しくなる一方で、結果的な利益率のばらつきが時間とともに変化していないということは、好調な企業が業績を改善させ続ける一方で業績不振な企業がさらに悪化し続け、全体として格差が拡大していくという形にはなっていないことを意味する。好業績企業としてとどまり続けるのが困難になるとともに、逆転のチャンスも多くなっていると解釈できる。
*本稿は、森川正之[2004], 「日本企業の業績は二極化」しているか? 『企業活動基本調査』マイクロデータによる検証」(調査ワーキング・ペーパー, WP04-05)の要点を紹介したものである。


