RIETIの「企業統治分析のフロンティア」分析研究グループの成果として、『企業統治制度改革と日本企業の成長』が出版される予定です。
そこで各章の内容に関するコラムを連載していきます。
海外機関投資家の存在感の高まり
過去20年間、海外機関投資家の株式保有比率の上昇は、全世界に共通して観察されてきた現象である。たとえば、海外機関投資家の保有比率は、英国では、1990年代初頭の20%から2000年代半ばには45%を超え、ドイツでも、同期間に5%から20%程度にまで急上昇した。また、創業家一族による株式保有が顕著であった韓国でも、2000年代初頭に急上昇し、近年では30%を超えている。日本もその例外ではなく、1997年の銀行危機以降、従来の株式相互持ち合いが解体し、それに代わって海外機関投資家の保有比率が急増した。東証上場企業の海外機関投資家による株式保有の合計は、1996年の12%から2015年には33%に達している(図1)。
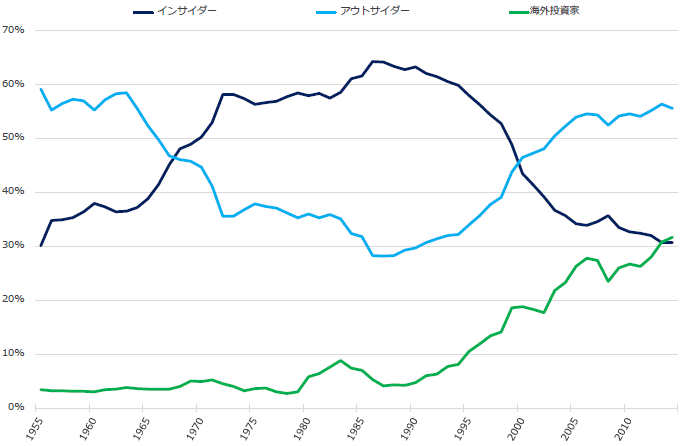
海外機関投資家を巡る2つの対立する見方
この海外機関投資家の保有比率の増大は、近年の株式所有構造の最大の変化の1つであるが、一方で、海外機関投資家の企業統治における役割とその帰結を巡っては、2つの対立する見方が並存している。
第1の見方は、海外機関投資家は、しばしば「灰色(grey)」と指摘される国内機関投資家よりも投資先企業からの独立性が強く、事前の銘柄選択能力と事後のモニタリング能力に優れているという肯定的な見方である。海外機関投資家の存在は、国際標準の企業統治制度(たとえば、独立性の高い取締役会や業績と強く連動した報酬体系の採用)を整備させる圧力として働き、その結果として、投資先企業のパフォーマンスの向上をもたらすという主張であり、ファイナンス学者から広く支持されている。
それとは対照的に、第2の見方は、海外機関投資家は、非対称情報に直面しているため形式的な銘柄選択(たとえば、規模の大きい企業、流動性の高い企業、認知度の高い企業)に終始し、また、個々の保有比率が断片的であるため投資先企業にコミットする意思を持たないという懐疑的な見方である。たとえ、海外機関投資家の保有比率と投資先企業のパフォーマンスに正の相関があっても、それは需要ショックによる見せかけの相関を捉えているか、海外機関投資家が優良企業を選好するという逆の因果関係を捉えているに過ぎない。また、仮に海外機関投資家が、独立性の高い取締役会や業績と強く連動した報酬体系の採用などの国際標準の統治制度を要求しても、それがすべての企業に適合し、パフォーマンスの向上をもたらすとは限らない。さらに、海外機関投資家は短期主義的であるため、経営陣の決定に対して近視眼的な(myopia)圧力を加えるという批判的な見方も根強い。
海外機関投資家によるモニタリングは何をもたらすか
そこで本研究では、海外機関投資家の銘柄選択とともに、海外機関投資家が企業の統治制度や経営政策に与える影響を実証的に検証することで、上記のどちらの見方が妥当するのかを解明した。分析の手順と結果の要点は、以下の4点にまとめることができる。
第1に、海外機関投資家の銘柄選択の決定要因を検証した。その結果、海外機関投資家の銘柄選択には、分析期間の1990年から2013年を通じて、一貫して非対称情報に起因する形式的な銘柄選択と解釈できる一種のバイアスが存在する。すなわち、規模の大きい企業、流動性の高い企業、業績の良い企業、認知度の高い企業を選好する傾向がある。
第2に、海外機関投資家が企業の統治制度、特に取締役会構成に与える影響を検証した。その結果、海外機関投資家は、国際標準の統治制度(独立性の高い取締役会)を求めるだけでなく、投資先企業のファンダメンタルズ、具体的には、事業の複雑性やエージェンシー問題の深刻度などに応じた合理的な取締役会構成の選択を促進させる。
第3に、海外機関投資家が企業の経営政策、特に設備投資、資本構成、株主還元に与える影響を検証した。その結果、海外機関投資家は、投資先企業の設備投資比率、負債比率、自己資本配当率を引き上げることがわかった。ただし、成熟企業の過大な投資や成長企業の過度な配当を助長することはなく、むしろ、投資先企業の経営政策の選択に対して、その企業の特性(ライフサイクル)に適合した形で影響を与えている可能性がある。
最後に、海外機関投資家による株式保有は、投資先企業のパフォーマンスを引き上げることがわかった。海外機関投資家の保有比率の増加は、投資先企業の株価収益率を実質的に上昇させる。その影響は大きく、分析期間を通じて、海外機関投資家の保有比率が5%上昇すれば、投資先企業の株価収益率は平均的に8%程度上昇する。また、高い海外機関投資家の保有比率は、トービンのQやROAで計測したパフォーマンスを、逆の因果関係(高パフォーマンス企業を海外機関投資家が選好するという関係)を慎重に考慮しても引き上げる。
以上の結果を総括すれば、海外機関投資家の銘柄選択は一定のバイアスを伴うものの、いったん海外機関投資家の保有比率が上昇すれば、投資先企業では、その企業に適合した統治制度の整備や経営政策の選択が促進され、その結果としてパフォーマンスが向上することになる。つまり、上述した海外機関投資家に肯定的な見方を支持する結果である。このことは、従来の日本型企業システムの根幹を担ってきたメインバンク制に代わって、海外機関投資家(外部投資家)によるモニタリングが企業の効率性を維持・向上させるメカニズムとして実質的に機能し始めていることを示唆している。
もっとも、以上の海外機関投資家のポジティブな効果が期待されるのは、規模の大きい企業に限定されていることに留意が必要である。図2は、それを明確に示している。1990年代初頭には、時価総額を基準とした大規模企業(第5五分位)と小規模企業(第1五分位)の間に、海外機関投資家の保有比率に大きな差はなかった。しかし、機関投資家の保有比率がピークを迎えた2006年には、大規模企業では25%を超える一方、小規模企業では依然として5%以下に留まっている。つまり、インサイダー(金融機関、事業法人、創業家一族など)による株式保有が高い、時価総額が小さく、流動性が低く、海外売上高比率が低い企業では、依然としてメインバンクや他のインサイダー大株主の果たす役割が大きいことに留意が必要である。
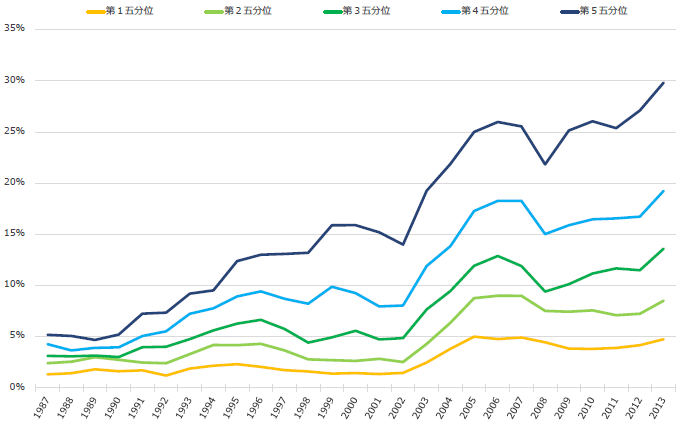
海外機関投資家が企業統治に影響を与えるメカニズム
では、海外機関投資家のポジティブな効果は、どのような経路を通じてその影響が実質的な意味を持つのか。この点の検討は今後の課題であるが、以下若干の展望を述べておこう。
一般に、海外機関投資家の株式保有の増加が、経営政策やパフォーマンスに影響を与える経路としては、(1)ブロック保有に基づいたアクティビズムと呼ばれる直接的な介入(株主総会における株主提案や委任状争奪戦など)、(2)独立(非業務執行)取締役によるモニタリングが想定される。
しかし、(1)の経路については、確かに、2000年以降、いくつかのアクティビストの行動が観察されたものの、その案件自体が著しく少ないうえ、実際に標的となった企業は、海外機関投資家の保有比率の低い、比較的小規模の企業であった。このことは、高い海外機関投資家による株式保有が、直ちに企業買収の可能性を直接引き上げた訳ではないことを意味する。また、たとえ株主アクティビズムが観察されたとしても、それが成功を収める事例は非常に限られている。
また、(2)の経路についても、同様に、2000年以降、海外機関投資家の選好に沿うように、日本企業の独立取締役の選任が進展したことは事実であるものの、独立取締役の選任が必ずしも企業の経営効率の向上をもたらすとは限らない。そもそも、独立取締役が影響を与えられるほど十分に選任されている企業は少なく、過半数が独立取締役という企業はほとんど存在しない。海外機関投資家の存在によって、独立取締役を選任する圧力が高まったとしても、その結果として企業パフォーマンスの向上がもたらされると解釈することはできないだろう。
以上の事実から、上記の直接的な経路が、海外機関投資家が日本企業に影響を与えてきた主たる経路であると想定することはできない。むしろ、現実的なのは、海外機関投資家による退出(voting with their feet)が企業経営に影響を与えるという間接的な経路である。
前述したように、海外機関投資家の保有比率の変化は株価収益率にプラスの影響を与えていた。しかも、この経済的規模は大きく、海外機関投資家の保有比率が5%増加すれば、株価収益率は約8%上昇する。この株価収益率の上昇の要因、つまり、海外機関投資家の事前・事後のモニタリングによるのか、海外機関投資家が株式を購入する際の需要ショックによるのかを十分に特定することはできなくとも、事実として、経営陣が、海外機関投資家による株式保有の増加が株価収益率の上昇をもたらすと認識するには十分なほどに大きい。
実際に、経営陣が株価の推移に関心を示すようになったことは、2000年代以降にIR活動や情報公開が進展した事実とも整合的である。さらに、筆者らが試みたアンケート調査でも、1990年代の調査結果とは異なり、近年では約9割の経営陣が株主価値を意識するようになったと回答している。
ただし、日本企業において、海外機関投資家が退出する上での経営陣の関心事は敵対的買収の脅威が増加することや持ち株(ストックオプション)の価値が減少することではないだろう。むしろ、より重要なことは、株価の低迷が経営陣の評判を悪化させ、内部者からの支持が得られなくなるからかもしれない。つまり、海外機関投資家の増減がもたらす株価の変動は、諸外国のように外部メカニズムを通じてではなく、内部メカニズムを通じて効力を持つ可能性がある。しかし、これは実証的に裏付けされたものではなく、推論の域を出ない。言うまでもなく、この推論を検証することが今後の課題である。



