経済全体の活動状況を新しく作成された経済活動指数により評価すると、経済活動は昨年7月に好転したあと、直近では消費税率引き上げ前の状況をやや上回る程度まで改善している。政府は先ごろ景気の基調判断を引き上げたが、新しい経済活動指数はそれを裏付けている。
新しい月次経済活動指数
実体経済の包括的な活動状況を量的に捉えることを目的に政府や民間機関により月次ベースの景気指標が作成されている。政府より公表される指標のうち代表的なものとして内閣府の景気動向指数(CI一致指数)と経済産業省の全産業活動指数が挙げられる。
前者は、景気変動の大きさやテンポ(量感)を測定するために生産や労働などさまざまな分野から景気に敏感に反応すると考えられる代表的な指標を選び出し、それら指標の変動を加重平均で集約することにより作成されている。現在、一致指数の作成には鉱工業生産指数、所定外労働時間指数、卸売業販売額(名目ベース)、小売業販売額(名目ベース)など11の経済指標が使われている。
しかし、経済活動の70%(付加価値額ベース)を占める第3次産業に関する指標は多く用いられていない。そのため、景気変動の大きさを的確に表現するという意味ではその指数は不十分であるとの意見が聞かれる。
後者は、建設業、鉱工業そして第3次産業(公務などを含む)における活動指数を基準年(5年ごとに更新)の付加価値額にもとづくウエイトで加重和することにより作成されている。景気動向指数(CI一致指数)とは対照的に、それは全産業のうち多くの部分をカバーしている。
しかし、全産業活動指数には期間を通じてデータに一貫性がないという欠点がある。それは主に第3次産業活動指数に起因している。基準年の改定に合わせて個別業種によっては活動指数を作成するのに用いるデータが変更されるためである。たとえば、1995年基準の改定では31業種において採用データの変更がおこなわれた。したがって、1995年基準の活動指数と1990年基準の活動指数は実質的にまったく別物であるといっても過言ではない。
採用データの変更は個別業種の活動状況をより的確に捉えるため必要に応じておこなわれてきた。それは活動指数の精度向上を図ることが業務目的の1つである統計作成部署にとって何らおかしなことでなく、むしろ当然のことである。こうした事情から長い期間にわたり一貫した方法やデータにもとづいて活動指数が作成されている個別業種の数は残念ながら多くない。
ところで、近年の月次データを用いた実証研究では実体経済活動の尺度として全産業活動指数を利用する研究が見られるようになってきた。しかし、長い期間にわたり連続して利用可能なデータが整備されておらず、したがって実証研究におけるその指数の利便性は現段階で著しく低い。
そのギャップを埋めるために1960年以降の期間について経済活動の包括的な状況を捉える新しい月次経済活動指数を作成した(注1)。基本的には全産業活動指数の作成方法に倣う。ただ、前述したように第3次産業活動指数に見られる欠点を注意深く丹念に補っている。具体的には、ある個別業種において現行の2005年基準で経済産業省により採用されているデータが過去に遡って入手可能な場合にはそのデータを用いる。
しかし、データの入手が難しい場合が起こりうる。その場合には1つ前の基準年で採用されていたデータが期間を通じて利用可能かどうか調べる。もし利用可能ならばそれを使用する。一方、利用不可能であればさらに1つ前の基準年で同様のことを試みる。このようなアプローチにより個別業種の活動指数を作成するのに用いるデータが決められる。
また、活動指数の作成に用いるデータは基本的に政府や民間から公表された生産量や販売量そして売上高といった個別業種の生産活動に関わる実績データである。そのようなデータが利用できない個別業種は作成対象から除外される。その結果、第3次産業において活動指数を作成する業種のカバレッジは経済産業省の2005年基準指数で作成対象となっている業種のうちのおよそ80%(付加価値額ベース)である。作成対象から除かれた業種として、たとえば金融業、公務そして公共サービス関連の業種が挙げられる。
実質GDPの動向を先取りできる新しい活動指数
こうして新たに作成された活動指数にはいくつか望ましい特徴が見られる。図1は1960年から2013年までの新しい活動指数と実質GDPの成長率(ともに前年同期比)を描いている。ここで使用している実質GDPの四半期データは国民経済計算年報のなかで報告されている確々報ベースであり、現時点で2012年第4四半期までデータの利用が可能である。図からは新しい活動指数が総じて実質GDPと似た動きを示していることが視覚的に見て取れる。
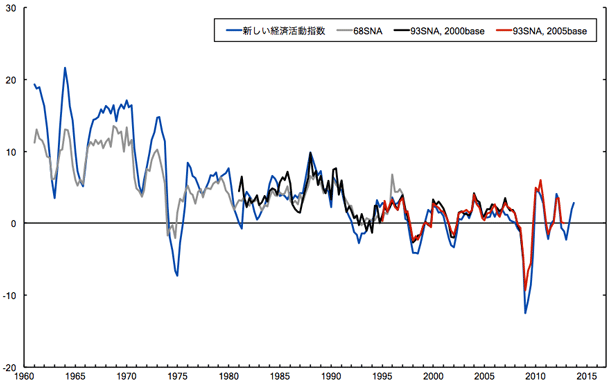
[ 図を拡大 ]
両者の動きが対応しているとすれば同時点における相関係数がもっとも高くなるはずである。表1ではそのことを確認するために活動指数の伸び率と実質GDP成長率の時差相関係数を報告している。68SNAのデータを用いたとき、当該四半期における活動指数の伸び率とそれと同時点(k=0)の実質GDP成長率の相関係数は0.93であり(表の1行5列)、他の時点の相関係数より大きい。93SNAのデータにおいても活動指数の伸び率と実質GDP成長率の相関係数は同時点で最大である。
| 体系基準年 | データの期間 | k | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1990年基準・68SNA | 1961Q1-1997Q4 | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.84 | 0.73 | 0.61 | 0.50 |
| 2000年基準・93SNA | 1981Q1-2008Q4 | 0.34 | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.84 | 0.76 | 0.70 | 0.65 | 0.55 |
| 2005年基準・93SNA | 1995Q1-2012Q4 | -0.16 | 0.13 | 0.44 | 0.78 | 0.94 | 0.73 | 0.41 | 0.07 | -0.20 |
さらに、新しい活動指数は景気後退に関するいくつかの指標と関連している。たとえば、活動指数の伸び率(トレンドからの乖離)が続けてマイナスを示す時期は内閣府経済社会総合研究所により設定された景気後退期と整合している。また、その時期は短観の業況判断D.I.が下降している時期と概ね対応している。これらの結果は新しい活動指数が月次ベースの実体経済活動の尺度として有用であることを示唆している。
新しい活動指数の直近の動き
図2の上のパネルは2012年以降の新しい活動指数(季節調整済)の前期比伸び率(年率)を実質GDP成長率(前期比年率)とともに描いている。図の点線は前にその特徴について述べた総合指数を表す。青い実線は直近の活動指数を作成するのにデータが利用できない一部の業種を除いて集約した活動指数を表す。その活動指数のカバレッジは総合指数のカバレッジのおよそ70%(付加価値額ベース)である。赤い実線は実質GDP(確々報ベース)を表す(注2)。灰色のエリアは内閣府経済社会総合研究所により暫定的に設定された景気後退期である。
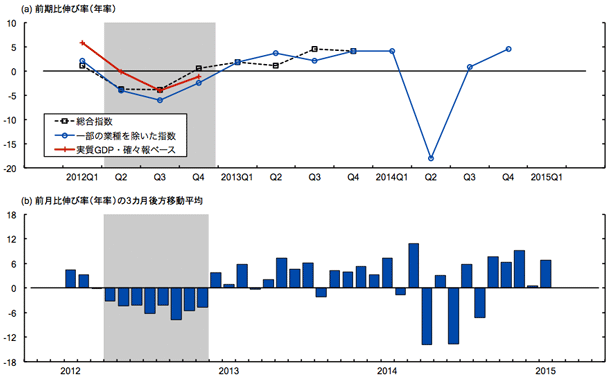
[ 図を拡大 ]
総合指数、一部の業種を除いた活動指数そして実質GDPの伸び率は類似した動きを示している。いずれの系列も2012年の景気後退期にはマイナスで推移している。唯一の例外は2012Q4における総合指数であり、わずかにプラスとなっている。
下のパネルは一部の業種を除いた活動指数の前月比伸び率(年率)の3カ月後方移動平均の推移を描いている。2014年以降の時期に目を向けると、4月と6月に伸び率が大きく低下している。これは4月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響によると考えられる。7月には活動指数の伸び率はプラスに転じ、その後はおしなべて消費税率引き上げ前の水準をやや上回る程度まで改善している。なお、8月に伸び率が大きく低下しているが、これは記録的な多雨や日照不足による天候不順で経済活動が一時的に低迷したことを反映していると考えられる。政府は先ごろ景気の基調判断を引き上げたが、新しい活動指数はそれを裏付けている。

