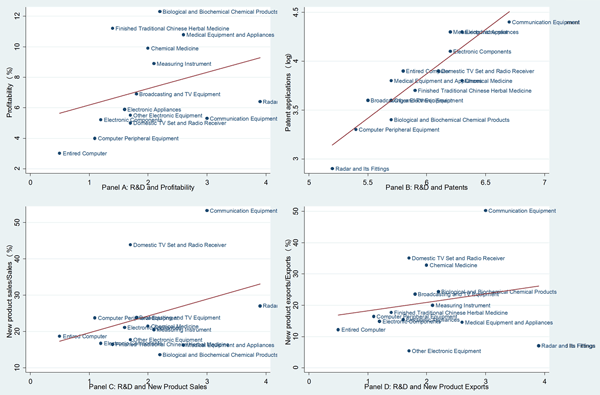中国国家統計局は、第三次経済センサス、China Economic Census 2013の主要結果に関する公報を2014年12月16日に公表した。今回の調査は、2013年第二次産業と第三次産業分野における事業所および企業の経済活動の実態、産業構造・産業技術の現状および各生産要素の構成を明らかにするとともに、サービス産業・戦略的新興産業・零細企業・ハイテク産業の発展状況を把握することを目的としている。本稿は、ハイテク産業に焦点を当ててセンサスの調査結果を整理し、ハイテク産業の発展についていくつかの視点を提供する。
高成長が続くハイテク産業
第三次経済センサスの調査結果によると、2008年(第二次経済センサスが実施)からの5年間、ハイテク産業の規模が拡大し、研究開発(R&D)支出が大幅に増加し、イノベーション能力の向上によって売上高に占める新製品の比率も上昇している。表1では、ハイテク産業のパフォーマンスを示す指標をまとめている。なお、ハイテク産業は、医薬品、航空機・同付属品、電子・通信設備、電子計算機・事務用設備、医療用機械器具・精密機械などの産業をさす。
| 2013年 (A) | 2008年 (B) | (A)/(B) | (A)-(B) | |
|---|---|---|---|---|
| (1)生産活動 | ||||
| 企業数(社) | 26,894 | 25,817 | 1,077 | |
| 雇用者数(万人) | 1,293 | 945 | 1.4 | 348 |
| 売上高(億元) | 116,048 | 55,729 | 2.1 | |
| 輸出/売上高(%) | 42.5 | 56.5 | -14 | |
| 労働生産性(売上高/雇用者数) | 90 | 59 | 1.5 | |
| 売上高利益率(%) | 6.2 | 4.9 | 1.3 | |
| (2)研究開発(R&D) | ||||
| R&D支出(億元) | 2,034 | 730 | 2.8 | |
| R&D集約度(%) | 1.75 | 1.31 | 0.44 | |
| R&D人員(フルタイム換算、万人) | 67 | 28 | 2.4 | 39 |
| (3)特許 | ||||
| 特許出願(万件) | 14.3 | 3.9 | 3.7 | |
| 発明特許出願(万件) | 7.4 | 2.6 | 2.8 | |
| 発明特許保有(万件) | 13.8 | 2.4 | 5.8 | 11.4 |
| (4)新製品 | ||||
| 新製品売上高(億元) | 31,000 | 12,879 | 2.4 | |
| 新製品売上高/売上高(%) | 26.7 | 23.1 | 3.6 | |
| 新製品輸出/輸出(%) | 24.8 | 20.1 | 4.7 | |
| 新製品輸出/新製品売上高(%) | 39.2 | 49.2 | -10.0 | |
| 出所:『第三次全国经济普查主要数据公报』、China Economic Census 2008 より筆者作成。 | ||||
(1)生産活動
2013年末に、ハイテク産業に属する規模以上工業企業(注1)の企業数は2万6894社、雇用者数は1,293万人、売上高は116,048億元、2008年より拡大している。輸出額が増加しているが、内需拡大によって輸出集約度は低下していると見られる。また、労働生産性が上昇しているとともに、企業収益も好況を保っている(2013年の利益率は6.2%)。
(2)研究開発(R&D)
R&D支出は、2,034億元(製造業全体の25.6%)にも達している。R&D集約度(R&D支出/売上高)は1.75%、2008年よりも0.44パーセントポイント高くなった。R&D人員の急増によって人的資本の蓄積も加速化している。大規模なR&D活動は、中国企業の「自主創新」(独自のイノベーション、indigenous innovation)を促進するには大きな役割を果たしていると考えられる(注2)。
(3)特許
特許出願件数は2008年より急増し、約14.3万件があった。中国においては、特許には、発明特許・実用新案・意匠の3種類が含まれている。特許出願件数の中、発明特許出願は7.4万件、うち、4.5万件が電子・通信設備製造業に集中している。
(4)新製品(注3)
新製品の生産規模が拡大し、売上高に占める新製品の比率も上昇している。興味深いのは、輸出集約度が低くなったが、輸出に占める新製品の比率は24.8%、2008年より4.7パーセントポイント高くなったことである。輸出財の品質向上、つまり輸出高度化(export sophistication)がうかがえる。また、新製品売上高に占める新製品輸出の比率は低下していることは、新製品の国内市場向けの販売増を意味しているので、中国国内需要の増加や所得水準の向上などが考えられる(注4)。
R&Dの効果
活発なR&D活動はハイテク産業の成長に貢献していると考えられる。ここでは、散布図によってR&Dの効果について簡単な検討を行う。図1は、R&Dと利益率・特許・新製品との相関関係を示すものである。Panel AからDまでは、すべての横軸はR&D集約度(ただし、Panel BではR&D支出の対数値)をとり、縦軸はそれぞれ売上高利益率、特許出願件数の対数値、売上高に占める新製品の比率、輸出に占める新製品の比率をとっている。図中の産業はハイテク産業の小分類産業である。すべてのPanelでは、回帰直線は正の傾きを持っている。産業によって異なるが、全体として、R&D集約度の高い産業ほど、利益率が高く、特許出願と新製品を多く生み出し、高品質な財を輸出していることを示している。これらは、先行の学術研究の発見を支持するものといえる。厳密な分析については、Jefferson et al. (2003, 2006)、Hu and Jefferson(2009)、張(2013)を参照されたい。
技術よりも制度の重要性
ハイテク産業の発展をもたらした主な原動力は生産性と技術力の向上だけではない。技術自身の進化よりも創造に有利な経済と社会制度の確立が重要である(呉, 2001)。
中国政府は2006年より「国家中長期科学技術発展計画(2006-2020年)」を実施し、2020年までにR&D支出の対GDP比率を2.5%以上に引き上げること、そして中国企業の「自主創新」(独自のイノベーション)を推進することを目指している。その実施に関する補完政策では、ハイテク企業のR&D投資に対する所得税徴収前の控除額の拡大、政策性金融・商業金融の自主創新に対するサポートの強化・誘導、イノベーション人材の育成・誘致、発明特許の審査期間の短縮などが盛り込まれた。こうした政策支援はハイテク産業の迅速な発展に大きな役割を果たせたという見方が多い。
しかし、政府の役割を過大に評価すべきではなく、市場原理も重視しなければならない。実際、中国政府もそれを意識しているようにみえる。たとえば、今回の公報公表に当たって、国家統計局局長馬建堂氏は、ハイテク産業の高成長について次のような見解を示した。政策支援は重要な役割を果たしているが、それよりもっと重要なのは、市場経済の進化につれて、市場メカニズムはより強く働いているようになったことである。近年、新しい業種やビジネス・モデル、新製品がどんどん現れてきている。また、市場競争もますます激しくなり、企業家のイノベーション意識が一層強くなってきた。このように、市場メカニズムの働きと政策支援は両立し、双方の力を合わせて中国ハイテク産業の発展を促進したともいえる。
また、公報公表のちょうど1週間前に行われた中国国務院常務会議では、北京市の「中関村自主イノベーションモデル区」で先行実施している6件の試行政策を全国に拡大することを決定した。具体的には、ストックオプション・配当の奨励、従業員研修費の税引き前控除、研究成果の使用処置と収益管理改革などが含まれている。これらの政策は政府の権限と利益を削減させ、企業によるイノベーションのインセンティブを一層高め、人的資本がその創造的な能力を十分に発揮できるような環境と条件を整えることを目的としている。今後、各種の改革措置を確実に実行すると同時に、ハイテク産業の発展に有利な制度が確立できれば、技術進歩とハイテク産業の一層の発展が期待される。