1993年以降、日本の電子製品輸出額は年間1000億ドルを上回っている。世界金融危機以前、日本の輸出総額の2割を電子製品が占めていた。近年日本を混乱に陥れている洪水、地震およびマクロショックは輸出にどのような影響を与えたのだろうか。
東アジアの生産ネットワーク内向けの電子製品輸出
日本の電子製品の輸出の多くは東アジアの生産ネットワーク内向けである。図1aは、日本からアジアの主要サプライチェーン諸国(中国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)向けの電子部品輸出額を表している。2008年9月のリーマン・ショックから2009年1月の底値の間に輸出額は100%(対数ポイント。以下同じ)減少し、3年半を経た現在も平均輸出額はリーマン前の水準を約25%下回っている。また、2011年3月の東日本大震災後、輸出額の減少は7%にとどまり、2011年6月には震災前の水準まで回復したことを示している。一方、図1bは、日本から東南アジア向けの電子部品輸出額を表している。2011年のタイ洪水に伴う輸出減少は主に対タイ輸出に限定され、タイ以外のサプライチェーン諸国への輸出額は影響を受けていないことを示している。
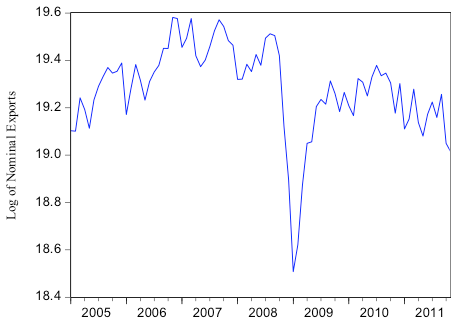
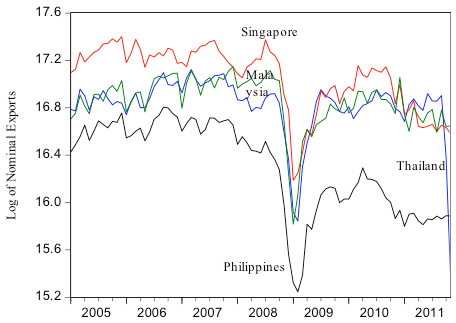
図2は日本からASEAN、中国、韓国・台湾等新興工業経済 (NIEs) 向けの電子部品輸出量を表している。2008年8月から2009年1月の間に輸出額は88%減少したが、その後急速な回復を見せ、2010年にはリーマン・ショック前の水準を上回った。
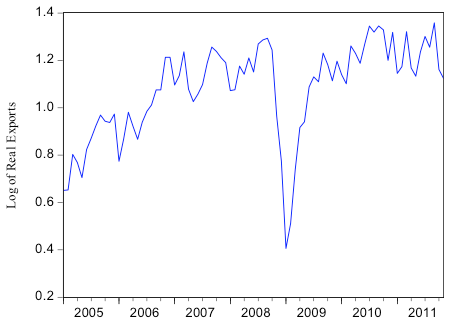
輸出量はリーマン・ショック前の水準を上回る一方で輸出額が回復していないという現状は、輸出価格の下落を示唆している。実際、日銀データによると電子部品・デバイス (ECD) 輸出の円建て価格は2005年1月から2011年11月の間に56%低下している。
為替変動と電子製品の輸出価格
筆者がRIETIで行っている研究によれば、短期的に見るとECD輸出価格は基本的に為替変動と一対一対応しているという結果を得た。これは、2007年6月から2011年末の間に28%円高になった結果、ECD輸出の円建て価格が28%下落したことを意味している。
以上の結果を解釈する上で難しいのは、東アジア生産ネットワーク内の貿易は多くの場合、ドル建て決済だという点である。1つの可能性は、日系多国籍企業が為替変動に対応する形で部品の円建て価格を変え、最終的な市場で製品を販売する際の輸入価格を調整していることである。たとえば、日系企業が日本製部品を用いて中国でコンピュータを組み立て、ヨーロッパで最終製品を販売する場合、中国に輸送する部品のドル価格は調整せず、ヨーロッパで販売するコンピュータのユーロ価格を為替変動に合わせて調整している可能性がある。
生産ネットワーク内で生産された最終電子製品の輸出に際して、日系企業が為替変動をパススルーできるか否かは、日本で生産された最終電子製品が為替変動をパススルーできているか否かを分析することで検証できる。日本製の最終財は、熟練労働者によって生産された高性能で知識集約型製品という傾向がある。一方、日系多国籍企業が中国などのサプライチェーン諸国で生産する最終財は、低価格で非熟練労働集約型製品という傾向がある。日系企業が日本製高級品に対する価格決定力を持っていなければ、低賃金諸国で組み立てられる同質な製品に対するする価格決定力を持っているとは考えにくい。
実証分析の結果、輸出先国通貨建て輸出価格のうち、日系情報通信機器メーカーがパススルーできているのは為替変動の20%以下であり、それ以外は各社とも値上げによって吸収していることがわかった。2007年6月から2011年末の間に28%円高になった結果、通信機器輸出品の円建て価格は22%下落していた。通信機器の円建て輸出価格は、同時期の円ベースのコストと比較して20%も下落したわけである。つまり、近年、円高によって電子機器企業の利益幅が大幅に圧迫されているのである。


