8月19日のニューヨーク外国為替市場で、円ドル相場は一時1ドル=75円95銭と戦後最高値を更新し、その後も70円台後半での円高が定着している。一方、ギリシャ財政危機問題からユーロ円相場もユーロ導入後ほぼ10年ぶりの円高水準である100-110円のレンジで取引されており、日本経済にとって厳しい局面が続いている。特に、対ユーロはヘッジも難しく、対欧州への輸出比率の高い企業は業績の下方修正が起きる、と市場では言われている。
名目と実質のAMU乖離指標は何を語るか?
日本にとって、対ドル、対ユーロと並んで重要なのが、対アジア通貨である。円は主要通貨に対してだけではなく、アジア通貨に対しても同様に円高となっているのだろうか? 対アジア通貨の円の動向は、アジア通貨13カ国から構成されるアジア通貨単位(AMU)に対する相場の基準年(2000-2001年)からの乖離度を測ったAMU乖離指標を見ることで判断することができる。図1は名目のAMU乖離指標の推移を表している。これによると、円のAMU乖離指標はリーマンショック後の2008年末から急上昇し、13カ国のアジア通貨の中で一番強い通貨グループ(円・中国円・シンガポールドル・タイバーツ)を形成していた。その後、2010年からは中国元は0(アジア通貨平均)前後に低下したのに対して、円・シンガポールドル・タイバーツは10(アジア通貨平均よりも10%切り上がりの水準)前後で推移していた。2011年8月に円が史上最高値を更新した頃から円のAMU乖離指標は単独で上昇し、2011年10月時点で13となり、アジア通貨の中でも円高が進行していることがわかる。
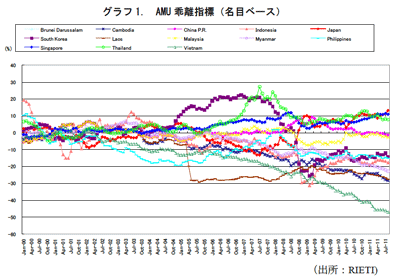
[ 図を拡大 ]
一方、物価変動分を調整した実質実効為替レートで比較すると、対ドルでも、現在の水準はそれほど円高になっているわけではないこともしばしば指摘されている。アジア通貨との関連でみれば、ここ十数年日本がデフレ傾向であったのに対し、中国をはじめとしてアジア新興国の物価は上昇しているため、日本と他のアジア諸国との間には大きなインフレ格差が存在してきた。主要アジア諸国の消費者物価指数の推移を表した図2によると、日本は2008年1月時点から消費者物価はほぼ横ばいから若干下落しているのに対して、中国・韓国・シンガポールはほぼ10%上昇しており、インドネシア・フィリピンは20%近く上昇していることがわかる。
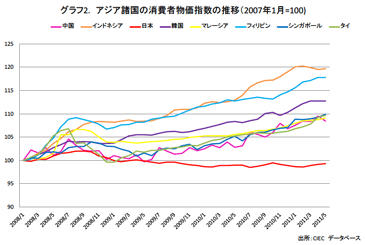
[ 図を拡大 ]
こうした物価面の関係を考慮すれば、物価上昇率の高かった国の通貨の名目価値が低くなり、逆にデフレであった日本の通貨の名目価値が高くなるのは、購買力平価に戻ろうとする力が働いているという当然の結果といえる。名目のAMU乖離指標をアジア各国のインフレ格差で調整した実質ベースにしてみた図3は、名目ベースでは一番強い円が実質ベースではアジア13通貨中で依然として一番弱いことを示している。これにより、いかに日本のデフレが、累積値として大きな値になっているかがわかる。
物価を基準に算出される実質為替レートはあくまで理論上のものであり、短期的な企業収益は名目為替レートで算出されるため、為替相場が実体経済に与える影響は名目値で考えるべきであるとの見方もある。しかし、円高によって海外移転を迫られる企業の業績を長期的に展望するならば、実質ベースでの為替相場にも注視する必要がある。たとえば、実質ベースでAMU乖離指標の差が大きい国向け輸出では、物価上昇に合わせて為替変動を販売価格に転嫁しやすい。一方で、実質AMU乖離指標が高い国に進出する場合は、物価や人件費の上昇リスクを考慮する必要があり、現地に生産拠点を持つよりも近隣のアジア生産拠点から輸出するなどの戦略も検討すべきである。
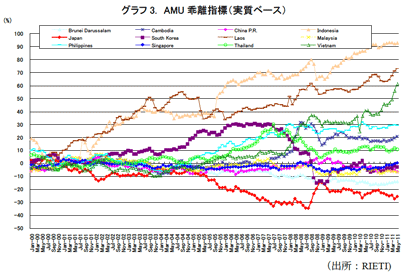
[ 図を拡大 ]
リーマンショック以降の円高が日本、中国、韓国の輸出にどのような影響を与えているかについて、各国の輸出額の推移を比較してみたのがグラフ4である。確かに、リーマンショック直後の貿易額の減少は日本が一番大きい(2009年第1四半期の対世界貿易額は対前年同月比で中国-19.7%、日本-40.52%、韓国-25.6%)。その後の回復は韓国に比べると出足は若干遅れたものの、日本の輸出額は2010年第4四半期にはリーマンショック前の水準まで戻しており、総額でみると名目ベースで円が中国元や韓国ウォンにたいして割高に推移しているほどには日本の輸出額が激減しているわけではない。
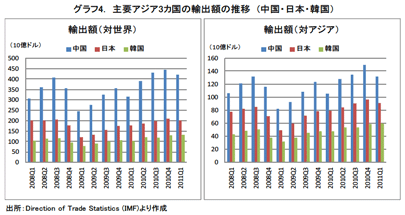
[ 図を拡大 ]
産業別にみた円の実効為替相場
2011年の円高が日本の輸出企業に与える影響については、特に対円で今年の9月末の1円15.32ウォン(対前年同月比、12%ウォン安)まで通貨安が進行した韓国の企業と競争の激しい輸送用機器や電気・機械分野で比較される場合が多い。そこで、RIETIで公表している産業別実効為替相場を概観してみよう(グラフ5)。RIETIの産業別実効為替相場は、産業別に円の競争力を見るということは新たな試みであり、各産業の輸出額の1%以上を占める国を「主要輸出相手国」とみなし、その貿易額で加重平均した名目実効為替相場(2000年1月3日=100)である。これを参考にすることにより、産業間の円高進行度の違いを比較検討することができる。たとえば、2008年以降のデータでは金属・銅製品分野が実効ベースで最も円高であり、精密機器分野と比較すると5ポイント以上差がある時期もあった。直近の推移を示したグラフ6は、2011年に入ってから8業種の中では輸送用機器分野で最も円高になっていることを示しており、緊急円高対策をどの業種に重点的に行うか、という政策に反映することができる。
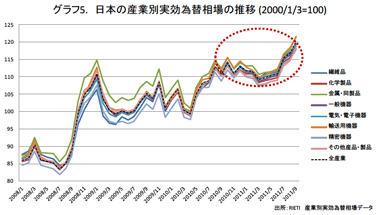
[ 図を拡大 ]
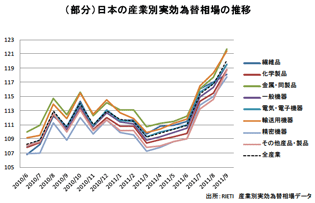
[ 図を拡大 ]
今、どのような政策が望まれるか?
これらの事実から、以下のような政策提言を導くことができる。
第1に、アジア域内の為替変動に着目すると、名目的には円が一番高くなっているものの、実質的には日本のデフレを反映して一番安いという対照的な状況にある。そこで、名目的に円が強い間にアジア地域への生産拠点移転やM&Aを推進し、今後の円高対策として部品や半製品をアジアの生産拠点から日本へ輸入する体制を築く。アジア域内では、ASEAN自由貿易地域(AFTA)を利用して日本企業がASEAN域内で生産と輸出を集中するという新たな戦略が生まれている。このように海外生産拠点から日本を含めて消費国へ製品を輸出できるようなFTA構想をさらに推進し、日本企業が国内外でより柔軟に生産拠点を変更するなどの環境を整備する必要がある。
第2に、生産拠点の海外移転はいたしかたないものの、日本国内には企画・開発の拠点を残し、グローバルな生産戦略、多通貨間為替リスク軽減、などの機能を充実すべきである。
第3に、物価が上昇している国への輸出については、為替変動分を現地での販売価格に転嫁しやすい。したがって、今後景気の減速が長期的に予想される欧米向けではなく、アジア向け輸出を目的とした生産構造に転換する。
第4に、国内で累積のデフレ効果が大きくなっていること、その結果としての「名目」円高を引き起こしている、したがって、実質為替レートが、歴史的円高とはいえない、あるいはむしろ円安であるということを認識すべきであり、短絡的な補助金に偏る「円高対策」で財政赤字を膨らませるようなことがあってはならない。
第5に、産業別実効為替相場が示すように、実効ベースで円高の影響が厳しい輸送用機器関連企業に対して緊急円高支援策を出動し、競争力維持のため規制緩和を推進する必要があるだろう。



