縮む市場、進まぬ改革
戦後から飛躍的発展を成し遂げた「日本の奇跡」は、もはや過去のものになった。いまや、少子高齢化の進展で人口は減少し、日本経済は縮小均衡に向かいつつある。このためか、日本全体に悲壮感が漂い、どのプレイヤーも生き残りに精一杯で短期的利害にとらわれ、長期的視点で日本全体の将来を考える余裕が消滅しつつある。国民の生活水準は1人あたりの生産量(GDP)で決まる。だから、人口減少下でも生活水準の維持・向上は可能であり、むしろ期待や希望をもち、日本の明日を託せる骨太の成長戦略が求められている。また、財政・社会保障の持続可能性が失われつつあるが、いまならばまだ、抜本改革による再生も間に合うはずである。だが、いまのところ、その具体像は、残念ながら見えてこない。本来は、骨太の成長戦略を構築し、持続可能な財政・社会保障改革の推進を図ることが「政治の王道」だが、さまざまな既得権の反発や政治力学の狭間で、政府はジレンマの状態に陥っており、なかなか改革は進捗しない。
このような状況において、日本が抱える諸問題の打開を模索する観点から、2008年6月には自民党の外国人材交流推進議員連盟が「今後50年間で1000万人の移民受け入れ」を提言するとともに、同年10月には経団連が「人口減少に対応した経済社会のあり方」を公表し、外国人材の積極的受け入れを提言した。しかし、これら提言は定性的議論に留まり、定量的に移民の効果を分析しているものではない。このため、移民受け入れが日本経済、ひいては各世代に如何なる影響を及ぼすのか、などの考察はできていない。そこで、本コラムでは、移民受け入れが各世代の効用に与える影響を分析した島澤諭・秋田大学准教授と筆者の共同研究の成果を交えつつ、「日本型・移民政策」の可能性を考察してみよう。
未熟練人材の受け入れは経済にマイナスか?
「熟練人材の受け入れは自国経済に一定の利益をもたらすものの、未熟練人材の受け入れは、その競合相手となる自国労働者の賃金低下を招き、経済に不利益をもたらす可能性がある」-これは、多くが支持する定説だろう。だが、これは部分的な議論に過ぎず、企業側の利潤が抜けている。一般に、熟練・未熟練にかかわらず、労働供給の増加は、労働者間の競争を促進して賃金を引き下げるものの、その恩恵から企業側の利潤は増加する。このため、企業側の利潤増加が、労働者側の賃金減少を上回るならば、経済全体に利益をもたらす。この場合、外国人材受け入れの問題の本質は、不利益を被った自国労働者に対して、必要な補償がなされるか否かとなる。この点で、Hatton and Williamson(2005) (注1)は、示唆に富む議論を展開する。1つは、未熟練の外国人材を活用する企業に対して、その活用で得た利潤増加分を超過しない範囲で一定の追加課税を行い、それを財源として、自国労働者に再分配するという議論である。実際、このような試みは、シンガポールにおいて実施されており、業種や熟練・未熟練の区分により金額が異なるものの、外国人材を雇う企業に一定の雇用税(Foreign Worker Levy)を課している。ただ、シンガポールでも議論となっているが、この雇用税が最終的にどの主体の負担として帰着するのか、という問題がある。つまり、雇用税の負担が、自国労働者のさらなる賃金引き下げという形で自国労働者にその負担が転嫁、あるいは商品の値上げという形で消費者にその負担が転嫁されるケースもあるので、その実行には留意を要する可能性もある。
もう1つは、未熟練の外国人材に一定の課税をするという議論である。そもそも、未熟練の外国人材が他国に職を求める動機には、母国よりも高い賃金を獲得できるという見込みもあるはずだ。すなわち、未熟練の外国人材も利益を得る。したがって、その利益を超過しない範囲で、未熟練の外国人材に一定の課税を行い、それを財源として、自国労働者に再分配するという議論である。さらに、この課税方式は、雇用税の負担の転嫁のような問題は起こらないという利点ももつ。
また、そもそも上記の議論は、それほど心配の必要がない可能性もある。近年、中村二郎・日本大学教授らは、外国人材の受入れが日本の労働者の賃金低下を招く可能性などを詳細に実証分析している(『日本の外国人労働力』日本経済新聞出版社)。その結果によると、一定の留意が必要であるものの、むしろ、比較的競合すると考えられる低学歴の日本人労働者の賃金を引き上げる効果をもつ可能性などを示唆している。
なお、現在、文部科学省を中心とする関係6省庁により、グローバル戦略や教育研究の国際競争力を高め、優れた留学生を獲得する観点から、2020年を目途に留学生30万人を目指す、いわゆる「留学生30万人計画」が進められている。また、政府は、外国人留学生の国内就職の拡大やその環境整備をはじめ、留学生採用に前向きな企業の求人開拓やマッチングの強化も検討している。このため、留学生の教育から就職までの流れが有効に機能すれば、一定の質を有する外国人材も獲得できる好機となろう。
外国人材の受け入れ拡充は、財政・社会保障負担を軽減する可能性をもつ
いずれにせよ、未熟練の外国人材の受け入れも、自国経済に寄与する可能性がある。むしろ、積極的な外国人材の受け入れにおいて問題となるのは、家族を呼び寄せるなどして、その滞在が長期化するケースである。この場合、外国人労働者やその家族に、教育や社会保障(年金・医療・介護)などの権利のうち、どの範囲までの権利を付与し、日本社会に組み込みつつ、その融合を図っていくのかという、いわゆる「社会的統合」に関する議論が発生する。
しかし、社会統合は、いくつかのメリットをもたらす可能性がある。たとえば、公的年金の負担軽減や、税収・消費拡大への寄与である。少子高齢化の進展によって、年金・医療などの支え手が減少していく中で、短期的に、若い外国人材の受け入れはその補完としての役割が期待できる。また、膨大な公的債務を抱え、市場が縮みつつある今、一定の収入がある外国人材であれば、税収や消費拡大への寄与も期待できよう。
だが、長期的には、受け入れた外国人材が労働市場から引退すると、逆に、年金の受取り手となり、将来の財政・社会保障を圧迫するデメリットもある。このメリットとデメリットのどちらの効果が大きいのかについては、厳密な分析を必要とする。そこで、筆者らは、Fehr et al. (2004) (注2)らの研究を参考に、2015年以降に毎年15万人の外国人材を受け入れた場合や、その半分の7万5000人を受け入れた場合の各世代の効用を、開放経済での世代重複モデルという方法で試算した。このモデルの「効用」とは、各世代が、その生涯賃金(勤労期に稼ぐ賃金から政府に支払う所得税や年金保険料などを差し引いた手取り賃金に、引退期に受取る年金を加えたもの)をベースとして、生涯にわたって消費できる量などから得られる満足感に対応する。このようなモデルのもと、できるだけ日本経済にフィットさせた上で、外国人材受け入れの効果を試算した結果が下記の図表1である。
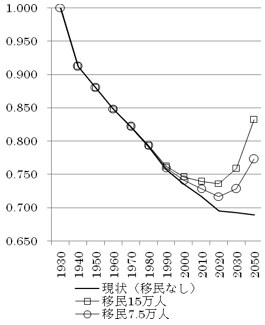
(出典)筆者ら作成
この図表1の横軸は各世代の生年、縦軸は1930年生まれ世代の生涯効用を1に基準化したときの各世代の生涯効用を表すが、外国人材の受け入れによって、1980年生まれ以降の世代の効用が改善していることが分かるだろう。これは、税・保険料の負担が軽減され消費が増えるなどの効果が働くからである。このため、外国人材の受け入れ拡充は、縮小均衡に向かう日本経済に一定の貢献を果たす可能性がある(図表2)。
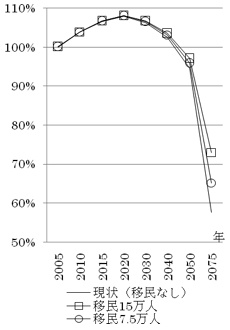
(出典)筆者ら作成
ただ、上記の議論は、あくまでも経済学的側面のみに偏ったものであり、外国人材の積極的受け入れは、日本の文化歴史面や治安面も含め、最終的には「この国のかたち」そのものを決める問題でもある。このため、冷静かつ慎重な検討が必要であることはいうまでもない。
しかし、少子高齢化の進展により、いまのところ、確実に日本経済は縮小均衡に向かいつつある。骨太の成長戦略の策定や財政・社会保障改革が、なかなか進展しない今、団塊の世代もこれから本格的に年金の受け取り手になっていく。このままでは、人口減少はこれからも日本経済にさまざまな歪みをもたらしていくことが予想され、何らかの対応は待ったなしの状況である。
このため、既成概念にとらわれず、こうした研究の蓄積も進めつつ、将来世代の利益も視野に、官民あげて、「日本版・移民政策」のあり方について、冷静かつ積極的な議論を進めていく必要もあろう。なお、日本では近年、正規雇用と非正規雇用の格差が問題になっている。特に、昨年以来、非正規や派遣社員の急な解雇が話題になっているが、未熟練の外国人は日本の非正規労働者以上に解雇の対象になりやすい。このため、外国人材との社会的統合までを視野に入れる場合は、その雇用環境や失業保険のあり方も重要な検討課題となろう。


