ミクロデータによる経済学研究の発展
社会科学において、コンピュータ・テクノロジーの進歩の最も大きな恩恵を蒙っている分野の1つとして、統計データを用いた実証経済研究(応用計量経済学分野)が挙げられる。かつて、経済統計分析というと、マクロ経済でおなじみのGDPや物価指数、失業率などの一国全体を対象とした年次統計データを用いて、グラフを作成したり、簡単な統計量を計算し、分析結果をまとめたものである。ところが、近年では、コンピュータの性能の向上により、大規模データによる分析も容易になり、その分析内容が高度化している。具体的には、失業率のような一国全体のマクロの数値ではなく、家族や個人、企業や工場を対象としたミクロのデータによる分析が増加しており、最近は白書でも数万件のデータを利用した統計分析結果に基づく研究成果が紹介されている。
こうしたトレンドは、むしろ欧米での進展が著しく、たとえば、1994年~1997年の間に、アメリカの8大経済学雑誌に掲載された応用計量経済研究のうち、ミクロデータを用いたものは42%にも達している。さらに、最近では、一時点のデータではなく、個々の家族・個人・企業・工場を時系列追跡したパネルデータを用いた研究が増加している(注1)。この背景には、欧米では政府機関と研究者が協力してミクロデータの整備が進められており、さらに政府統計の個票データの利用体制が充実していることがあげられる。わが国においても、政府統計データの目的外利用申請を経て入手したミクロデータを用いた研究が増加している(注2)。しかし、統計調査を行っている政府機関は集計データを公表することを目的としているので、ミクロデータ(個票データ)を時系列で接続したパネルデータの整備は遅れている(注3)。そこで、個票利用の承認を受けた研究者は各自でパネルデータを作成する必要がある。こうした現状を踏まえ、経済産業研究所では、国際経済学や産業組織論分野の研究者と協力し、政府ミクロ統計データ個票データからパネルデータを作成するノウハウを蓄積し、研究者がデータ整備に煩わされることなく、分析に取り組める環境整備(マイクロデータ計量分析プロジェクト(注4))を進めてきた。本コラムでは、その概要と作成されたデータセットによる研究事例を紹介する。
政府統計個票データのリンケージ
たとえば、海外生産が国内経済に及ぼす影響を調べようとするならば、海外生産額が増加した企業の国内における生産額や従業員数、生産性の変化を調べればいい。しかし、我が国においては、政府統計の個票データにアクセスしても、こうしたテーマを分析するためのデータセット作成には膨大な時間と労力が必要となるため、これまであまり取り組まれてこなかった。というのは、海外生産については「海外事業活動基本調査」、国内生産については「工業統計」、輸出や企業レベルの売上と雇用者数は「企業活動基本調査」という3つの異なる統計によって調査が行われており、政府統計部局では統計データ間の照合が行われていないからである。そこで、我々は、複数の研究者の協力を得て、これらの3つの統計をリンクさせるための企業・事業所番号対照表を作成し、図1のようなデータセットを作成した。さらに、個々の企業・事業所・海外現地法人は時系列で追跡できるよう固有の番号を割り振ったパネルデータを作成している。このデータセットにより、日本企業が世界のどこで、いつ、どんな製品を生産しているか、を把握できるようになった。こうした研究環境の整備によって、新しい研究が進められるようになってきている。ここでは、筆者が関与した2つの研究事例を紹介しよう。
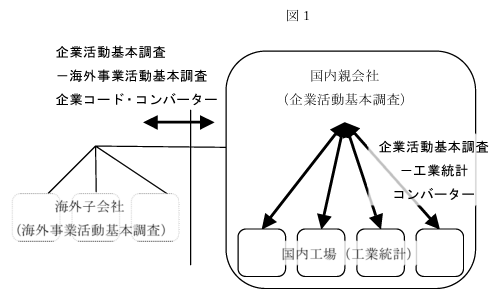
研究事例(1):海外進出企業の国内事業再編と生産性
海外進出企業は、国内企業に比べて生産性水準が高く、生産性の伸び率も大きいことが知られているが、その源泉はどこにあるのだろうか? 国内部門のリストラによって達成されているのだろうか? こうした問いに答えるためには、事業所(工場)レベルのデータと海外進出状況などの企業レベルのデータを接続したデータセットが必要となる。筆者と元橋一之教授(RIETIファカルティフェロー/東京大学)、藤澤三宝子氏(元RIETIリサーチアシスタント/現総務省)との共同研究(注5)では、事業所データと企業データをリンクさせたパネルデータを用いて、上記の問いに答えている。ここでは、企業の生産性上昇の源泉を、生産工程の効率化(事業所レベルの生産性変化)と事業部門再編(事業所の新設・廃止・事業転換)の2つに分類した。リストラによって効率改善が進んでいるとすれば、後者の寄与が大きくなるはずである。そこで、これを海外進出企業と国内企業で比較すると、海外進出企業の場合、前者の伸びが生産性改善にもたらす効果が相対的に大きいことが分かった。海外進出企業は、一般に、国内雇用を切り捨てて経営改善を進めているといわれているが、統計データで検証する限り、そういった効果は一部にすぎないことが分かった。
研究事例(2):日系海外現地法人の現地化の決定要因
日本企業は途上国において技術移転に関心が低く、「現地化」に消極的であると批判されることがある。その証拠として、日本企業は、親会社からの調達が多く、また、現地従業員の登用に消極的と指摘されるが、果たして本当だろうか? また、「現地化」に地域格差や企業格差があるとすれば、それはどんな要因によるものだろうか。
筆者と浦田秀次郎教授(RIETIファカルティフェロー/早稲田大学)らによる共同研究(注6)では、経済産業省「海外事業活動基本調査」から作成したパネルデータを用いて、個々の日系海外現地法人の現地調達率の変化、および現地法人の責任者の国籍変化に注目して、「現地化」の決定要因を分析した。その結果、2つの事実を明らかにした。第1に、「現地化」の程度は各海外現地法人の性格に依存するという点である。輸出拠点として設立された現地法人は、現地市場販売を目的とした現地法人に比べて、日本からの中間財調達率が高く、責任者が日本人である確率が高い。第2に、時間的な変化に注目すると、アジア等の途上国では、海外現地法人の操業年数が延びるほど「現地化」が進むことが分かった。これは、途上国に進出した企業にとって、進出当初は適当な人材や中間財取引に関する情報が不完全なので、日本からの人材や部品の供給に依存するが、操業経験が伸びると情報の不完全性が解消され、「現地化」が進むと解釈できる。途上国では、しばしば、外資系企業の「現地化」を進めるために、現地調達率や出資比率に規制が設けられることがある。しかし、我々の分析結果からは、むしろ外資系企業が安定的に操業できる環境整備が重要であると示唆される。


